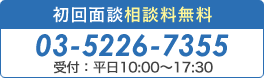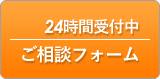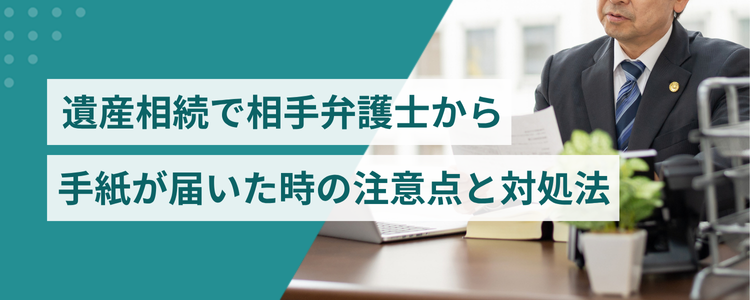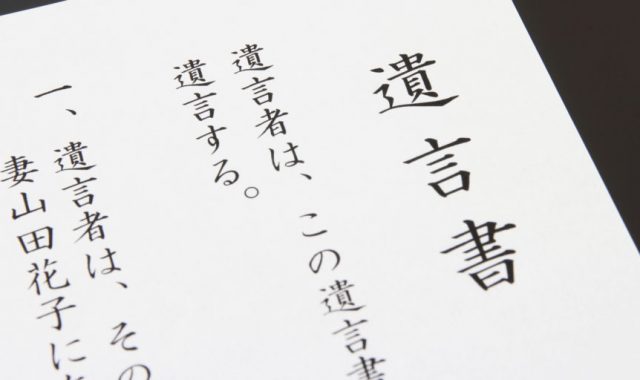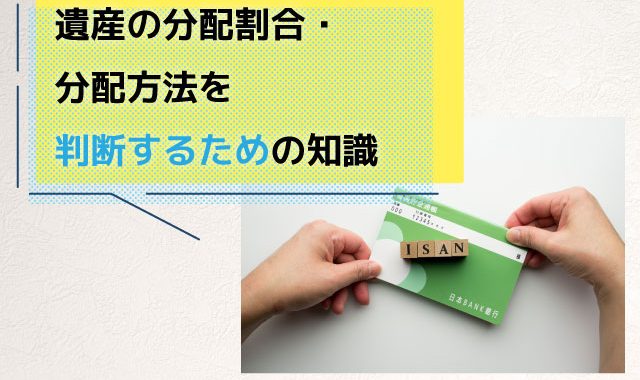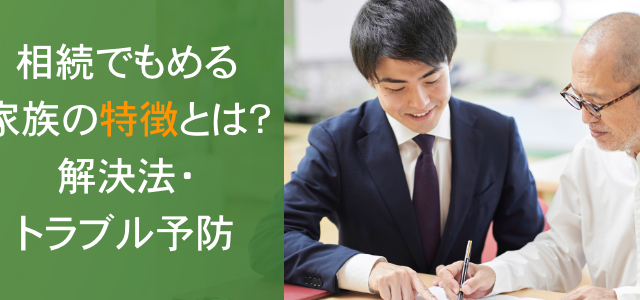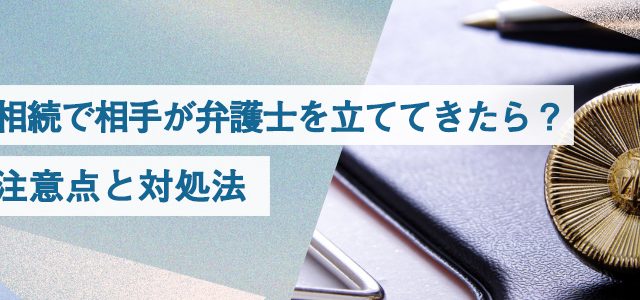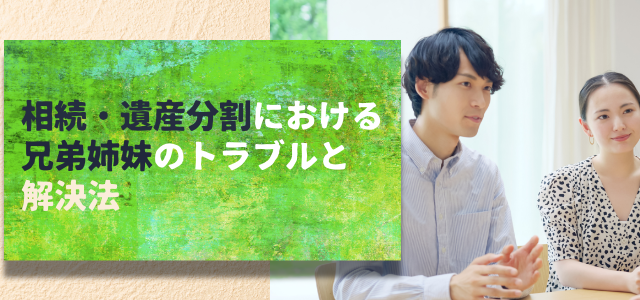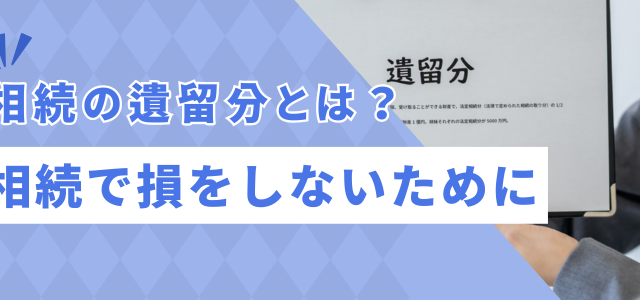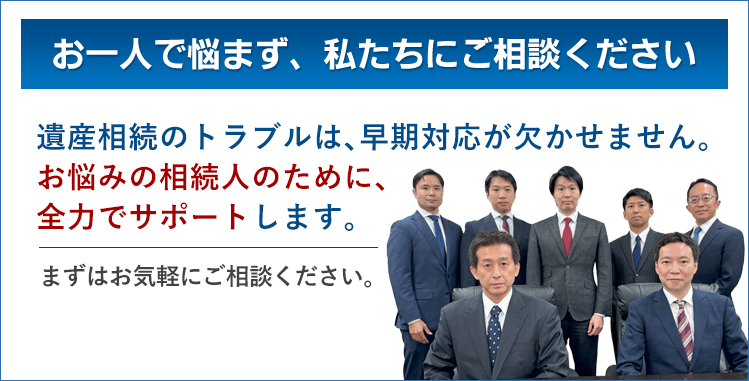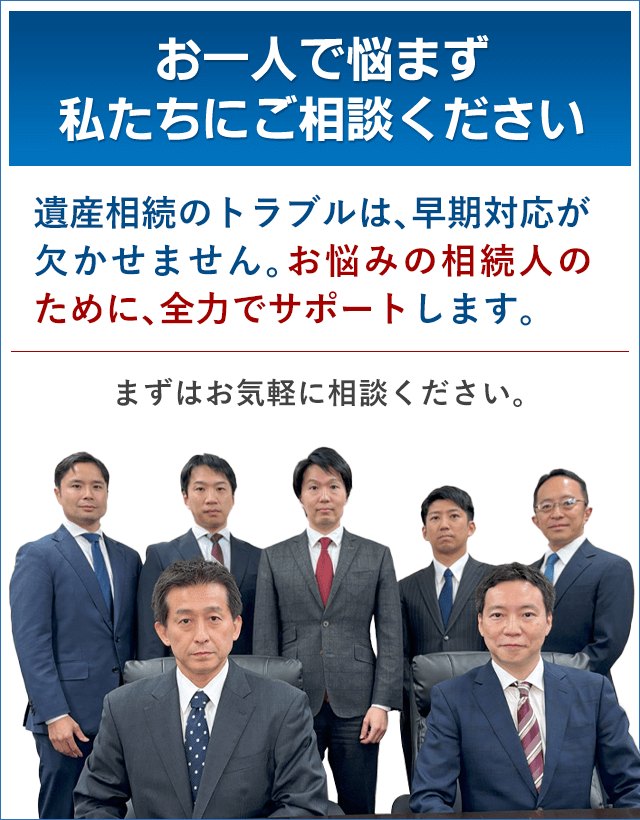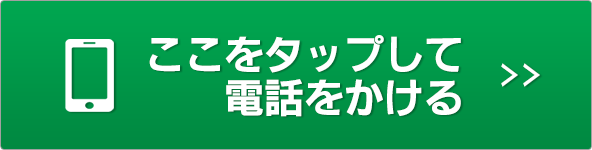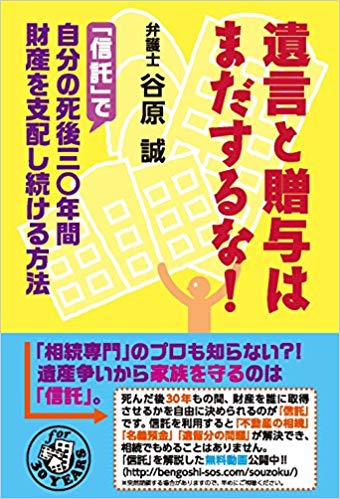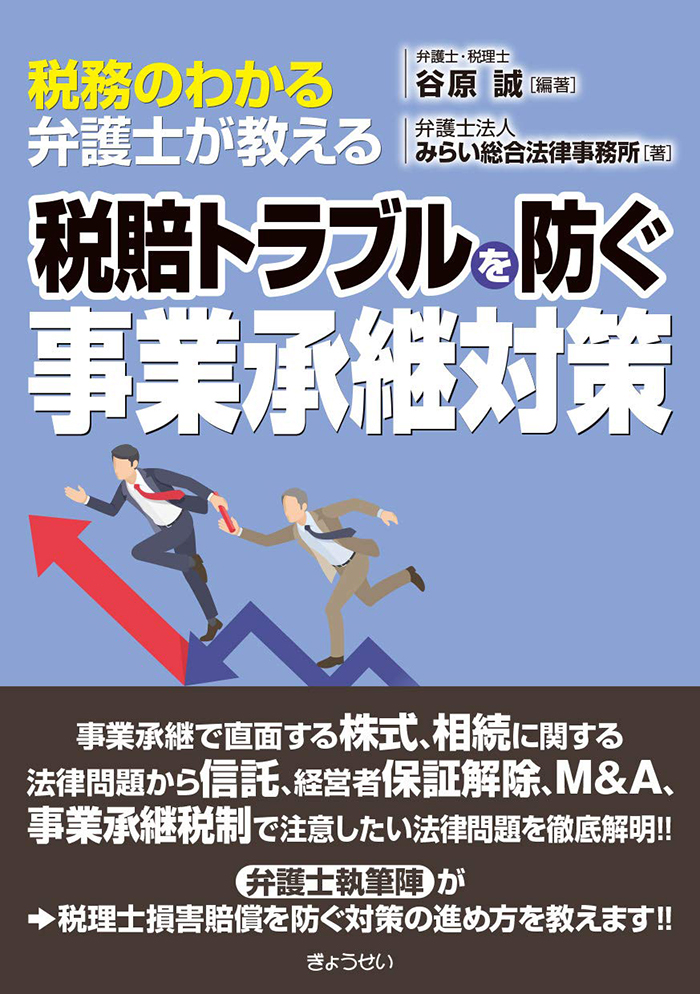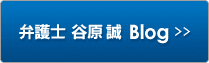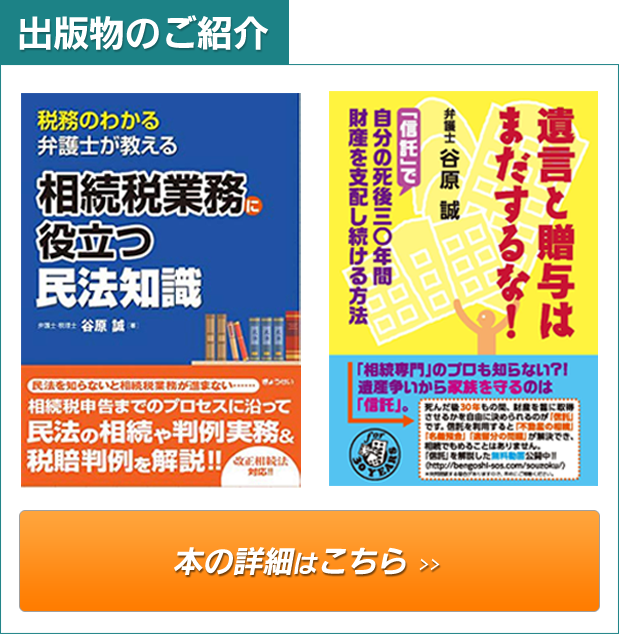遺産相続で相手弁護士から手紙が届いた時の注意点と対処法
面識のない弁護士から届いた
突然の手紙……
ある日、突然、法律事務所の弁護士から手紙が届いたら、あなたはどうしますか?
法的な問題を抱えていたり、トラブル解決の経験がある人なら驚かないと思いますが、弁護士と関わるのが初めてであれば、「ドキリ」としてしまうでしょう。
見覚えのない名前ですが、まずは封を開けてみます。
内容は、遺産相続に関わることのようです。
「今後は直接本人に連絡せず、代理人である弁護士◯◯宛てにご連絡ください」
といった内容が書かれています。
「本人」とは、あなたと同じ相続人のこと。
親の遺産であれば、兄弟姉妹、あるいは父親の再婚相手かもしれません。
つまり、相続人のうちの誰かが遺産相続の手続きを弁護士に依頼した、ということになります。
相手側の弁護士の主張に
どう対応すればいいのか?
さらに合わせて、「別紙の遺産分割協議書に署名・捺印の上、印鑑証明書●通を添えてご返送ください」などと、いきなり遺産分割協議書を送りつけてくる弁護士もいます。
あなたは、その遺産分割の条件については話したことも聞いたこともありません。
相手側が勝手に主張している割合、金額です。
さて、こんな時、あなたはどう対応すればいいでしょうか?
相手側の弁護士の言うことをそのまま信じたり、受け入れて、安易に応じてはいけません。
内容をしっかり確認しないままに、遺産分割協議書に署名・捺印して返送してしまえば、大きな損失を被る可能性があるのですから。
そこで本記事では、遺産相続が発生した際に、相手弁護士から手紙が届いた時の注意点と対処法について、その流れや注意するべきポイントなどを中心にお話しします。
法的な問題ですが、できるだけわかりやすく解説しています。
遺産相続で損害を受けないために、ぜひ最後までご覧になって、正しい知識を知っていただきたいと思います。
目次
- 1 遺産相続で必要な7つのプロセスと手続きについて
- 2 遺産相続で相手側の弁護士から手紙が届いた時の注意点と対処法を解説
- 2.1 ポイント① 手紙の内容を冷静に確認する
- 2.2 ポイント② 無視しない/感情的な反応は避ける
- 2.3 ポイント③ 相手側の本人と直接連絡・交渉をしない
- 2.4 ポイント④ 相手側の弁護士には安易に返答してはいけない
- 2.5 ポイント⑤ 文書への署名・捺印は法的な確認ができるまで行なわない
- 2.6 ポイント⑥ 相手側の弁護士から連絡がこない場合は放置しない
- 2.7 ポイント⑦ 期限を守って対応する
- 2.8 ポイント⑧ 記録を取って残しておく
- 2.9 ポイント⑨ 遺言書の有無と内容を確認する
- 2.10 ポイント⑩ 協議・調停・訴訟の選択肢を理解する
- 2.11 ポイント⑪ 財産の範囲と評価を把握する
- 2.12 ポイント⑫ 自分の権利を守る姿勢を持つ
- 2.13 ポイント⑬ 返答前には必ず自分も弁護士に相談・依頼する
- 3 遺産相続でおさえておきたい大切な知識
- 4 遺産相続で問題が起きたら弁護士に相談してください!
遺産相続で必要な
7つのプロセスと手続きについて
相手側の弁護士に対応する前に、まずは遺産相続が発生した場合に必要な基本的な手続きについて流れに沿って確認しておきましょう。
プロセス①
被相続人の死亡により
相続が開始/相続人の確定
親や兄弟など親族(被相続人)が亡くなると、遺産の相続が開始されます。
その時、まず必要なのは、誰が相続人になるのかを法的に確定させることです。
プロセス② 遺言書を確認/
検認・相続放棄など
次に、遺言書の有無を確認します。
遺言書があるかないかで、その後の手続きに違いがあることに注意が必要です。
遺言書がある場合
家庭裁判所の検認の後、遺言の執行に進みます。
ただし、公正証書遺言や自筆証書遺言を法務局に保管してある場合は検認の手続は不要です。
遺言書の検認とは?
遺言書の検認とは、次のような手続きです。
- 相続人に対し、遺言の存在や内容を
知らせる。 - 検認の日現在における遺言書の内容を明確にする。
※「遺言書の形状」、
「加除訂正の状態」、
「日付」、「署名」など - 遺言書の偽造や変造を防止する。
遺言書の保管者や相続人が
やるべきことは?
遺言書が見つかった場合は、その場では開封しないよう注意してください。
公正証書遺言でない遺言の開封は、家庭裁判所で立会いのもと行なう必要があるからです。
そのため、検認の申立てが必要になります(民法第1004条第1項・同条第2項)。
検認に際して、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求する必要があります。
【参考資料】:遺言書の検認(裁判所)
遺言書がない場合
まずは被相続人の負債額を確認して、「相続放棄」、「限定承認」、「単純承認」のいずれかを決定します。
相続放棄とは?
相続が開始されたら、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産を引き継ぐかどうか決定しなければいけません。
ここで注意が必要なのは、プラス分だけでなく、マイナス分(負債)も財産として相続の対象になることです。
いずれにしても、財産を引き継がないのであれば、相続放棄をしなければいけません。
相続放棄は、相続開始後(相続の開始があったことを知った時から)3か月以内(民法第915条1項)に、家庭裁判所に申し立てる必要があります(民法第938条)。
限定承認とは?
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
単純承認とは?
相続人が、亡くなった方の相続財産をすべて(プラスもマイナスも)、無条件で相続することです。
プロセス③ 準確定申告
準確定申告とは、納税者が亡くなった場合の確定申告のことで、4か月以内に行なう必要があります。
【参考資料】:No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)(国税庁)
プロセス④ 遺産調査
被相続人が亡くなった後は、遺産の種類や金額等を確定するために遺産調査を行ないます。
プロセス⑤ 遺産分割協議
相続人の間で遺産の分割について協議を行います。
遺産分割は、もめてしまうこともあるため、遺言書がない場合も含めて最終的には合意事項について効力をもたせるために「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書には、「誰が」「どの遺産を」「どれだけ取得するか」といったことを記載します。この文書により、亡くなった方の預貯金引き出しや、不動産の名義変更が可能になるので、重要なものであると理解してください。
【参考資料】:登記申請手続きのご案内(相続登記①/遺産分割協議編)(法務局)
プロセス⑥ 遺産分割調停
話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停に進むことになります。
遺産分割調停は、調停委員の立ち合いのもとで合意を目指した話し合いを行なう裁判手続きで、家庭裁判所で行なわれます。
およそ月1回、平日の昼間に行なわれることから仕事への支障が出る場合もあり、また精神的な負担にもなることを頭に入れておくべきです。
【参考資料】:遺産分割調停(裁判所)
プロセス⑦ 相続税の申告・納税
相続税の申告を行いますが、期限があることに注意が必要です。
被相続人が死亡したことを知った日(通常、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内となっています。
【参考資料】:No.4205 相続税の申告と納税(国税庁)
遺産相続で相手側の弁護士から
手紙が届いた時の
注意点と対処法を解説
では、前項の内容を踏まえながら、ここでは相手側の弁護士への対応について具体的に見ていきましょう。
遺産相続に関するトラブルに対しては、慎重に対応することが重要なポイントになります。
なぜなら、親族間の問題は感情的な側面と法的な複雑さが絡み合うため、一度こじれてしまうと解きほぐすのが困難になる場合もあるからです。
特に、兄弟姉妹など相手方の代理人として、弁護士から手紙(通知書、内容証明郵便など)が届いた場合は、直接的な接触、交渉を拒否していると考えられるので、冷静かつ戦略的に対処することが優先ポイントになります。
ポイント①
手紙の内容を冷静に確認する
まずは、手紙の内容を落ち着いて、丁寧に読み解いていきましょう。
弁護士からの手紙には、法的な主張や要求事項、期限などが記載されていると考えられます。
感情的になってしまい、それらの内容を読み飛ばしてしまうと、重要な情報を見落とす可能性があります。
- 差出人の情報:弁護士事務所の名称、代理人となった弁護士の名前など。
- 依頼者(相手方):誰の代理人として手紙を送ってきているか。
- 主張内容:遺産分割の方針、遺言の
有効性、特定の財産の帰属など。 - 要求事項:回答の期限、具体的な行動(協議への参加、資料提出など)。
- 法的根拠:民法や判例に基づく主張があるか。
ポイント②
無視しない/感情的な反応は
避ける
遺産相続は、家族・親族間の問題であることが多く、弁護士からの手紙に対して「これは脅しだ」、「一方的な主張で腹立たしい」などと感じることもあるかと思います。
しかし、届いた手紙を無視したり、感情的に反論したりというのは避けなければいけません。
弁護士は依頼者の代理人として法的な立場から主張しているだけであり、個人的な攻撃などをしているわけではないからです。
また、無視していると、弁護士は「話し合いによる遺産分割協議の成立の見込みがない」と判断し、遺産分割調停を申し立ててくる可能性があり、状況が複雑になっていくことも懸念されます。
まずは話し合いで解決することを考え、冷静に対応していくことが大切です。
ポイント③
相手側の本人と直接連絡・
交渉をしない
通常、相手側の弁護士からの手紙には「今後は直接本人には連絡せず、代理人である弁護士に連絡してほしい」旨が書かれていると思います。
この時点で、相手側は直接の交渉などを拒否しており、弁護士も「連絡がきても、直接交渉しないように」と伝えているはずです。
連絡しても無駄になるので、相手側の弁護士に連絡して、交渉を進めていくようにしてください。
ポイント④
相手側の弁護士には
安易に返答してはいけない
ただし、相手側の弁護士と話をする際は、質問に対して安易に、その場で返答しないようにしましょう。
優れた弁護士は交渉のプロですから、主導権を握りながら話を進め、有利な展開に持っていこうとするでしょう。
そして、依頼人に有利になる回答を、あなたから引き出そうとしてくるでしょう。
ですから、弁護士と交渉する時は、あなたにとって不利になる発言などを安易にしてはいけないのです。
ポイント⑤
文書への署名・捺印は
法的な確認ができるまで
行なわない
弁護士から届いた手紙には、こういった内容が書かれている場合もあるでしょう。
「別紙の遺産分割協議書に署名・捺印の上、印鑑証明書●通を添えてご返送ください」
いきなり遺産分割協議書を送りつけられて動揺し、焦ってしまうこともあるかもしれませんが、内容を法的に確認せず、すぐに署名・捺印して返信などは絶対にしないでください。
遺産分割協議書などは署名・捺印してしまうと、あとから取り消すことはほぼ不可能です。慎重に対応していきましょう。
ポイント⑥
相手側の弁護士から
連絡がこない場合は放置しない
相手側の弁護士に連絡しても、つながらない、返信をしてこない、対応しようとしない、といった場合があるかもしれませんが、じつはこれは、相手の戦略の可能性があるので注意が必要です。
相手側に、遺産分割をできるだけ先延ばしにしたい理由があるのかもしれません。
また、あなたを心理的に焦らせ、少しでも相手側が有利になるよう交渉を進めるためかもしれません。
このような場合は放置せず、あなたも早めに弁護士に相談・依頼するのがいいでしょう。
ポイント⑦
期限を守って対応する
弁護士からの手紙には、回答期限が設けられていることがあります。
これを無視すると、「協議に応じる意思がない」と判断され、調停や訴訟に発展する可能性があります。
たとえ回答を保留する場合でも、「現在検討中であり、〇日までに返答する予定です」といった意思表示をしておくのがいいでしょう。
ポイント⑧
記録を取って残しておく
手紙の原本はもちろん、今後のやり取り(メール、電話、面談など)についても、記録を残しておくようにします。
特に、相手方との交渉が長期化したり、調停・訴訟に発展した場合には、過去のやり取りが証拠として役立ちます。
- 手紙のコピーと受領日
- 返答文書の内容と送付日
- メールの送受信履歴
- 面談や電話の日時と内容メモ など
ポイント⑨
遺言書の有無と
内容を確認する
相手方の主張が遺言書に基づいている場合、その遺言書が有効かどうかを確認する必要があります。
前述したように、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、それぞれに法的な要件があります。
偽造や無効の可能性がある場合は、家庭裁判所での検認や無効確認の手続きを検討しましょう。
ポイント⑩
協議・調停・訴訟の選択肢を
理解する
遺産分割は、まず相続人同士の協議によって行なわれますが、協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停、さらに訴訟へと進むことがあります。
相手側の弁護士からの手紙は、協議の呼びかけであることもあれば、調停申立ての予告であることもあります。
あなたにとって最適な解決方法を選ぶためにも、弁護士と相談しながら、協議に応じるか、調停を申し立てるか、訴訟に備えるかを判断しましょう。
ポイント⑪
財産の範囲と評価を
把握する
相手方が主張する財産の内容が正確なものかの確認も必要です。
預貯金、不動産、有価証券、動産、債務など、遺産の範囲と評価額を把握することで、適正な分割案を検討できます。
必要に応じて、財産調査や鑑定を依頼することも視野に入れましょう。
ポイント⑫
自分の権利を守る姿勢を持つ
相手側の弁護士からの手紙に戸惑ってしまい、「言われるままに従うしかない」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、あなたの相続人としての権利は法的に守られていることを理解してください。
遺留分(一定の相続人に保障される最低限の取り分)や、寄与分(被相続人の財産形成に貢献した分)など、自分の立場を正しく理解し、主張すべき点はしっかりと主張していくことが大切です。
ポイント⑬
返答前には必ず
自分も弁護士に相談・依頼する
ここまで見てきたように、遺産相続には法的問題が絡んでくるので、相手側の弁護士からの手紙を受け取ってすぐに、法的な確認をしないまま返答するのは絶対にやめてください。
まずは、あなた自身も相続問題に詳しい弁護士に相談し、内容の妥当性や対応方針について助言を受けるのがいいでしょう。
そして必要であれば、正式に代理人を依頼して、相手側の弁護士に対応してもらう必要があります。
- 相手側の主張が法的に正当かどうか
判断できる。 - 自分にとって不利な条件を
見抜くことができる。 - 正しい対応を把握し、交渉の戦略を
立てることができる。 - 必要に応じて代理人として
法的に対応してもらえる。
遺産相続でおさえておきたい
大切な知識
ここでは、遺産相続について、さらに知っておきたい重要な知識について確認していきます。
正しい知識を得ることで、相手側弁護士から届いた遺産分割についての手紙・通知に対して適切に対処できますし、その後の交渉でも不利な状況を避けることができます。
遺産の相続順位と
相続分について
- 民法では、遺産を相続する人を
「法定相続人」と規定しています。 - 法定相続人には、第3順位までの相続順位と法定相続分(割合)が決められています。
- 配偶者がいれば、つねに相続人になります。
- 配偶者がいない場合は、血族の相続人がすべての相続財産を相続することになります。
<第1順位:子>
法定相続分:
配偶者が2分の1/子が2分の1
【注意ポイント】
1. 子が複数いる場合は、2分の1を人数で均等に分割します。子が2人なら、それぞれの相続分は4分の1ずつになります。
2. 子がすでに死亡している場合は、その子供 = 孫が相続人となります。これを「代襲相続」といいます。
3. 嫡出(婚姻関係にある男女、夫婦から生まれること、またはその生まれた子)か、非嫡出(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)か、については問題になりません。
<第2順位:親>
法定相続分:
配偶者が3分の2/親が3分の1
【注意ポイント】
1. 第1順位の人がいないときは親が相続人になります。
2. 両親がいる場合は、3分の1を2人で分けるので、6分の1ずつになります。
<第3順位:兄弟姉妹>
法定相続分:配偶者が4分の3/兄弟姉妹が4分の1
【注意ポイント】
1. 第1順位、第2順位の人がいないときは、兄弟姉妹が相続人になります。
2. 兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1をその人数で均等に分割します。
【参考資料】:No.4132 相続人の範囲と法定相続分(国税庁)
遺留分について確認する
「遺留分」とは、法定相続人が受け取ることができる最低限の相続財産であり、遺留分を請求できる権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
たとえば、兄弟の中でも長男だけに遺産が相続されることになっている場合や、再婚相手がすべての遺産を相続する、といった遺言がある場合、相続人間でトラブルになる可能性が高くなります
このように不公正な遺言内容であったとしても、法定相続人の遺留分は守られることを知っておくべきです。
遺産分割に関する資料の
開示を求める
相手側の弁護士からの手紙に、相続人関係図や遺産目録など遺産分割に関する資料が同封されていない場合もあるでしょう。
こうしたケースでは、遺産分割に関する資料の開示を必ず求めるべきです。
相手側の主張の根拠資料がなければ判断のしようがないからです。
特別受益や寄与分がある場合は明確に主張する
特別受益とは?
被相続人から、遺贈や生前贈与によって特別の利益を受けた法定相続人がいる場合、その受けた利益を「特別受益」といいます。
特別受益があった場合、その財産を相続財産に持ち戻して遺産分割をすることになっているため、必ず確認しておく必要があります。
ただし、相続開始の時から10年を経過した場合には、原則として持ち戻しはないことに注意が必要です。
寄与分とは?
遺産分割において、介護や家業に特別な貢献があったと認められた場合などで、その貢献を考慮して遺産分割を行なう仕組み・制度を「寄与分」といいます。
また、相続人ではない親族、たとえば相続人の妻などが、被相続人の介護を行なってきた場合などでは、「特別寄与料」が認められる可能性があります。
遺産分割においては、これらの有無も確認しておく必要があります。
遺産相続で問題が起きたら
弁護士に相談してください!
今回は、遺産相続問題で、相手側(あなた以外の相続人)が立てた弁護士から手紙が届いた場合の注意点や対処法について解説しました。
ご自分の独力で対応しようと考える方もおられるでしょうが、やはり法律問題では専門家である弁護士に任せたほうが安心ですし、早期に問題解決でき、満足がいく結果を得ることができると思います。
- 相手側が法定相続分以上の
要求をしていないか? - 相手側が特別受益を受けている事実はないか?
- 寄与分の主張がある場合、
それは妥当か? - 現物分割ではない分割方法
(換価分割や代償分割など)による
遺産分割はできないか? など
こうした問題を抱えている場合、相続に強い弁護士であれば、相手側の主張が法的に妥当なものか判断し、交渉で的確に有利に対応することができます。
まずは無料相談の利用をおすすめしています(※随時受け付けていますが、事案によるので、お問い合わせください)。
依頼を検討する場合は、事務員ではなく、必ず担当してくれる弁護士と話をしてみましょう。
法律相談は弁護士しかできないので、直接弁護士と面談し、説明がわかりやすいか、案件の経験が豊富か、相性は合うかなどを確認してください。
遺産相続の問題は一人で悩まないでください。
あなたからのご連絡をお待ちしています。