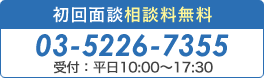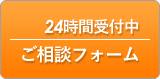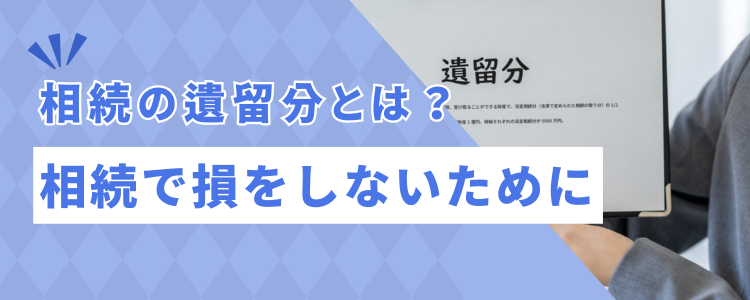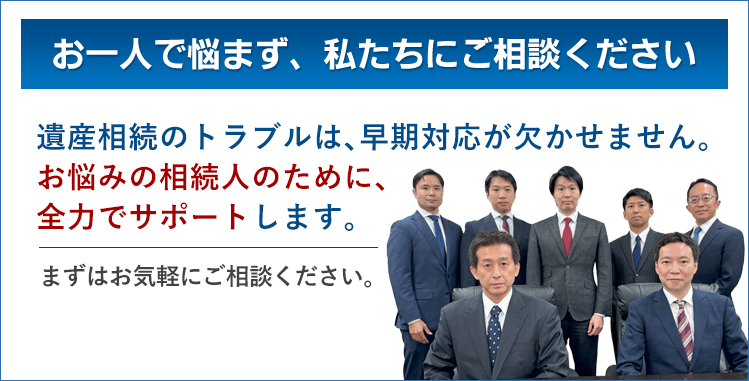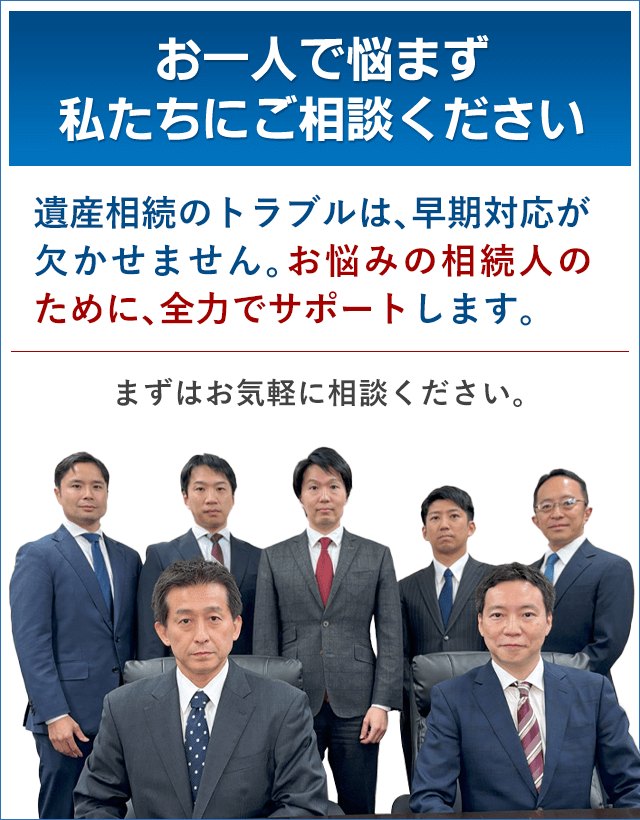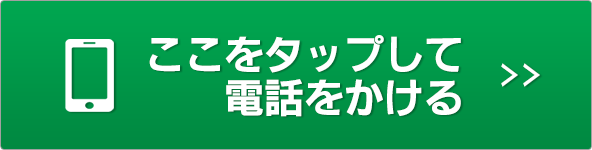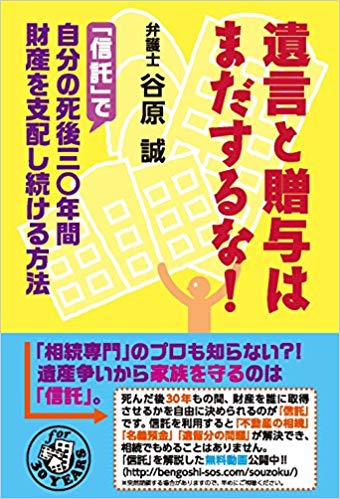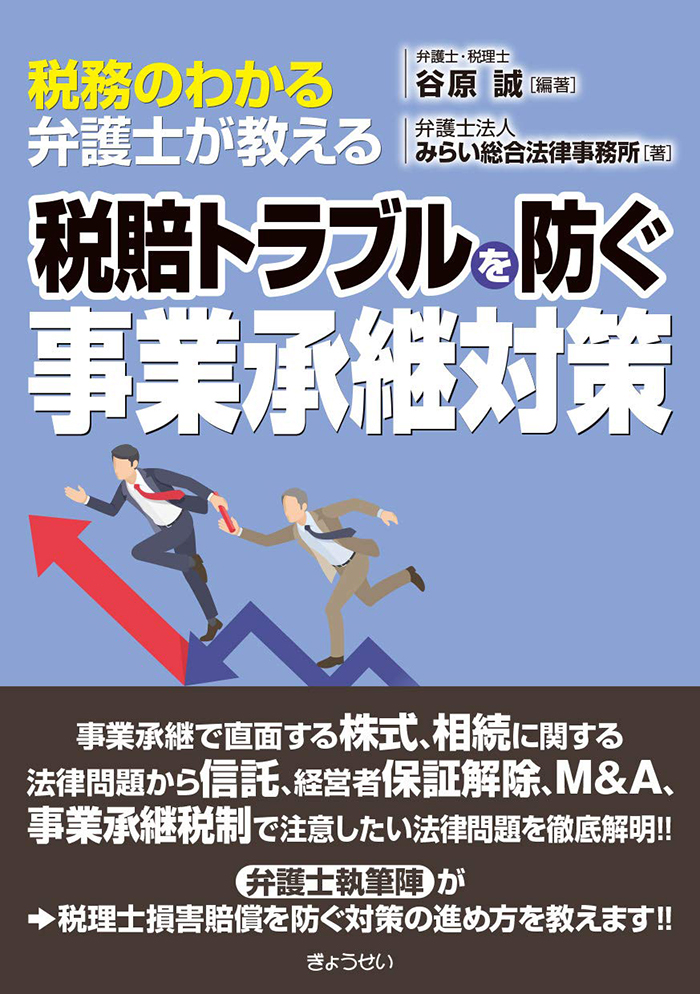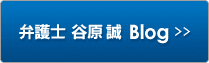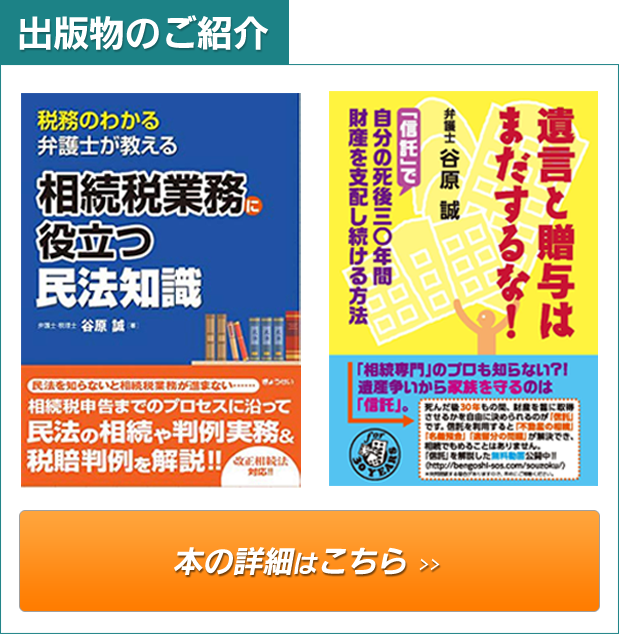相続の遺留分とは?|相続で損をしないために
相続には遺留分というものがあり、遺留分についてしらなければ相続で損をする可能性があります。
法定相続人には、遺留分として最低限の相続財産の取得が金銭的に保障されています。
そのため、遺言によって相続が一定の人に偏りがある場合でも、遺留分侵害額請求をすれば、法律で定められている最低限の遺産を相続できるかもしれません。
ここでは、相続の遺留分について解説しているので、相続で損しないためにも遺留分についての理解を深めましょう。
相続の分割方法
相続方法は、「遺言がない場合」と「遺言がある場合」で違いがあります。
遺言がない場合は法定相続分を目安にしながら遺産分割協議で相続の割合について決めます。
一方で、遺言がある場合は基本的に遺言通りに相続が行われますが、法定相続人には遺留分を主張する権限が与えられています。
まずは、相続の分割方法についての理解を深めていきましょう。
遺言がない場合
遺言がない場合は、被相続人の相続人と財産を調べたあとに遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、どのように遺産を分割するか相続人全員で話し合うことを指します。
話し合いなので相続人がそれぞれ自由に意見を述べることはできますが、全員の意見を取り入れると遺産分割は進まないことがあります。
そのため、法律で定められている法定相続分を目安にしながら遺産分割協議を行うことが一般的です。
法定相続分は、以下のように定められています。
| 相続人の構成 | 法定相続分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟姉妹 | |
| 配偶者のみ | 全て | - | - | - |
| 配偶者+子ども | 1/2 | 1/2 | - | - |
| 子どものみ | - | 全て | - | - |
| 配偶者+父母 | 2/3 | - | 1/3 | - |
| 父母のみ | - | - | 全て | - |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |
| 兄弟姉妹のみ | - | - | - | 全て |
| 相続人の 構成 | 法定相続分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟 姉妹 | |
| 配偶者 のみ | 全て | - | - | - |
| 配偶者+ 子ども | 1/2 | 1/2 | - | - |
| 子ども のみ | - | 全て | - | - |
| 配偶者+ 父母 | 2/3 | - | 1/3 | - |
| 父母のみ | - | - | 全て | - |
| 配偶者+ 兄弟姉妹 | 3/4 | - | - | 1/4 |
| 兄弟姉妹 のみ | - | - | - | 全て |
ただし、上記の法定相続分に強制力はなく、あくまでも目安です。
相続人全員が合意すれば、法定相続通りの分割にする必要はありません。
遺言がある場合
被相続人によって作成された遺言がある場合は、遺言に沿った遺産分割が行われます。
そのため、法定相続分とは異なる割合で相続を指定することや、法定相続人以外の人に財産を相続することが可能です。
原則的には被相続人の意思が尊重されるので遺言通りの相続が行われますが、相続人全員の意見が合意すれば異なる遺産分割をすることができます。
また、遺言内容が法定相続人の遺留分を侵害している場合、その法定相続人は遺留分侵害額を請求することが可能です。
遺留分については、次の項で詳しく解説していきます。
遺留分とは
法律では、相続におけるさまざまな規定が設けられています。
遺留分制度もそのひとつであり、遺留分制度は、遺族の生活保障と遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の精算などの意義を有しています。
遺留分とは、法定相続人に保証される最低限の保障です。
前項で遺産相続の方法について説明していますが、遺言がある場合は原則として遺言の内容通りに遺産相続が行われます。
しかし、遺言の内容が「愛人が全ての遺産を相続する」「兄弟の中でも長男だけに遺産が相続されることになっている」など特定の人に相続が集中する内容になっている場合、相続人間でトラブルになる可能性が高くなります。
こうした場合に、遺言通りでは遺留分以下の受取になってしまう法定相続人は、遺留分侵害を請求することが可能です。
つまり、不公正な遺言内容であったとしても、法定相続人の遺留分は守られます。
遺留分の範囲と割合
法律では、被相続人の意思が尊重されることを認めると同時に、遺留分制度によって法定相続人にも最低限の財産が引き継がれるように配慮されています。
それでは、遺留分が認められる範囲や割合はどのようになっているのでしょうか?
遺留分が認められる範囲
遺留分が認められる法定相続人の範囲は、以下の通りです。
- ・配偶者
- ・直系卑属(子ども、孫)
- ・直系尊属(親、祖父母)
兄弟姉妹は遺留分の範囲の対象外になります。
兄弟姉妹に遺留分が認められない理由には、遺留分が被相続人に養われていたと想定される近親者の生活を保護するための制度になることなどが挙げられます。
・兄弟姉妹に遺留分がない理由と遺産を受け取る方法
遺留分が認められないケース
遺留分の対象になる相続人であっても、場合によっては遺留分の請求が認められないケースがあります。
遺留分の対象であるにも関わらず、遺留分が認められないケースは、以下の通りです。
相続放棄した場合
相続放棄をしている場合、遺留分を請求しても認められません。
なぜならば、相続放棄をすると、始めから相続人ではなかった、とされるからです。
ここでいう相続放棄をした状態とは、家庭裁判所にて相続放棄申述を行っているケースです。
相続人間にて口頭で相続放棄を伝えているだけの状態では、相続放棄は成立していません。
相続人の廃除になった場合
相続人の廃除とは、相続権を持つ相続人を相続から外すことができる制度です。
被相続人へ虐待や重大な侮辱を行っていた場合、被相続人の財産を不当に処分した場合、犯罪行為があった場合などが挙げられます。
夫婦であれば、相手に不貞行為があった場合などに有効です。
被相続人が遺言で相続人の廃除をした場合や、家庭裁判所に申し立てていた場合には、遺留分を有する相続人であったとしても相続から廃除され、遺留分も受け取れなくなります。
相続欠格になった場合
相続欠格とは、相続人に民法で定められた欠格事由がある場合に、相続権をはく奪する制度です。
相続欠格になった場合、一切の遺産の相続ができなくなるため、遺留分も受け取ることはできません。
相続欠格に該当するケースは、自分に相続が優位になるように殺人や詐欺、脅迫を行った場合などです。
遺言の偽造や破棄、隠匿なども該当します。
遺留分を放棄した場合
当然ですが、自ら遺留分を放棄している場合も遺留分は認められません。
遺留分の放棄は、相続が開始する前に家庭裁判所にて手続きを行います。
相続開始後に遺留分を放棄する場合は、権利を行使しなければ遺留分を放棄することになります。
・遺留分の放棄とは?手続や相続放棄との違いについて解説
遺留分の割合
一定の法定相続人には遺留分が認められていますが、遺留分の割合は全員が同じではありません。
遺留分の割合は民法第1029条に定められており、相続の順位によって遺留分の割合も異なります。
遺留分の割合は、以下の表の通りです。
| 相続人 | 遺留分 | 法定相続人の遺留分の割合 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟姉妹 | ||
| 配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 配偶者と子ども | 1/2 | 1/4 | 1/4 | - | - |
| 配偶者と親 | 1/2 | 1/3 | - | 1/6 | - |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 子どものみ | 1/2 | - | 1/2 | - | - |
| 親のみ | 1/3 | - | - | 1/3 | - |
| 兄弟姉妹のみ | - | - | - | - | - |
| 遺留分 | 法定相続人の 遺留分の割合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子ども | 父母 | 兄弟 姉妹 | |
| 相続人:配偶者のみ | ||||
| 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 相続人:配偶者と子ども | ||||
| 1/2 | 1/4 | 1/4 | - | - |
| 相続人:配偶者と親 | ||||
| 1/2 | 1/3 | - | 1/6 | - |
| 相続人:配偶者と兄弟姉妹 | ||||
| 1/2 | 1/2 | - | - | - |
| 相続人:子どものみ | ||||
| 1/2 | - | 1/2 | - | - |
| 相続人:親のみ | ||||
| 1/3 | - | - | 1/3 | - |
| 相続人:兄弟姉妹のみ | ||||
| - | - | - | - | - |
上記の表から、基本的に遺留分の割合は、法定相続分の半分であることが分かります。
遺留分の対象になる財産とは
遺留分侵害を請求する場合、遺留分の対象になる財産を把握する必要があります。
遺留分の対象になる被相続人の財産は、以下の通りです。
相続開始時の財産
相続開始時に被相続人が所有していた財産は、全て遺留分の対象です。
預貯金や不動産、車、株式などが対象になります。
ただし、借金や滞納税などの負債も相続財産に含まれるため、注意が必要です。
生前贈与した財産
相続開始より1年前以内に生前贈与した財産は、遺留分の対象になります。
例えば、被相続人が亡くなる半年前に不動産を生前贈与していた場合、その不動産も遺留分の対象財産になります。
また、1年以上前の生前贈与であったとしても、贈与する側と贈与される側が遺留分を侵害することを知っていて贈与を行っていた場合、その贈与は遺留分の対象になります。
特別受益による財産
(10年以内のもの)
特別受益とは、複数人の相続人がいる中で相続人が生活のための生前贈与などにより被相続人の財産を受け取った利益を指します。
相続開始より前10年以内の特別受益は、遺留分の対象財産として扱われます。
特別受益も遺留分の対象になる理由は、相続人間の公平性を保つためです。
10年以上前の生前贈与であったとしても、贈与する側と贈与される側が遺留分を侵害することを知っていて贈与を行っていた場合、その贈与は遺留分の対象になります。
死因贈与する財産
死因贈与とは、被相続人が自身の死亡の際に特定の人へ財産を渡すことを約束するものです。
遺言は遺言者が一方的に相続内容を決めるものですが、死因贈与は契約なので受け取る側の合意が必要になるという違いがあります。
死因贈与された財産も遺留分の対象になります。
・遺留分の計算
遺留分が侵害されていた場合に
できること
遺言の内容が不公平で遺留分が侵害されていることが判明した場合、泣き寝入りすれば相続で損をすることになります。
遺留分侵害があった場合にできることや、その対処法の流れについて解説します。
遺留分侵害額請求を行える
遺言による相続内容の通りに相続をすれば遺留分が侵害される場合、遺留分が侵害される相続人は「遺留分侵害額請求」を行えます。
遺留分の権利者である相続人には遺留分を請求できる権利があるため、遺留分侵害が認められれば、遺留分を取得することができます。
ただし、遺留分は自動的に配分されるわけではありません。
遺留分を受け取りたい場合は、遺留分以上の財産を受け取った相手に対して請求をする必要があります。
遺留分侵害額請求は、話し合いから始めることが一般的です。
話し合いで解決しなければ、調停や訴訟で争うことになります。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求を行う場合は、以下のような流れで遺留分侵害額請求を行います。
相続財産の調査、相続人の確定
遺留分侵害額請求を行うには、まず相続財産の調査と相続人の確定が必要です。
なぜならば、相続人の組み合わせや相続財産の金額によって遺留分が変わるからです。
被相続人の戸籍謄本を確認すれば、相続人を確定できます。
相続財産を調査するには、被相続人の財産を全て洗い出す必要があります。
財産が多いほど調査は複雑になるため、弁護士など専門家に依頼することもできます。
当事者で話し合いをする
遺留分損害を請求する相手に内容証明〒で通知を行い、まずは当事者同士で話し合いをします。
内容証明は請求したことを証拠として残すことができるため、必ず送付することを推奨します。
話し合いに関しては、書面や電話、直接会うなど話し合いの方法は自由です。
ただし、あとから「言った・言わない」というトラブルを避けるために、話し合い後に決まった内容は書面に残しましょう。
調停を申立てる
話し合いで解決しなければ、家庭裁判所へ遺留分侵害額の請求調停を申立てます。
裁判官と調停委員が双方の話を聞き、意見をまとめて解決を目指します。
双方が合意した場合には、調停条項を確認して調停証書を作成します。
しかし、調停が不成立になった場合は、調停手続は終了します。
訴訟を提起する
調停でも解決しなかった場合は、裁判にて遺留分侵害額の請求訴訟を争うことになります。
訴訟になれば、最終的に裁判官による判決が下されるため、何らかの結果が出ることになるでしょう。
訴訟では、一般的に1ヵ月~1ヶ月半ごとに双方が交互に主張を行います。
訴訟となると、弁護士に依頼することをおすすめします。
・簡単に遺留分を請求する方法
【5ステップ 】
相続の遺留分における注意点
相続で損をしないためには遺留分について把握し、遺留分侵害がある場合は侵害額請求をすることができます。
ただし、遺留分侵害額請求では注意すべき点がいくつかあります。
遺留分侵害額請求権には時効がある
遺留分侵害額請求権には消滅時効があります。
時効は、「遺贈等があったことを知った時から1年間権利を行使していない場合」もしくは、「遺留分侵害を知らず、相続開始の時から10年を経過した場合」です。
時効が過ぎてから遺留分を請求したいと考えても、消滅時効によって遺留分の侵害額請求は認められません。
そのため、遺留分侵害額請求を検討している場合は、できるだけ早く請求を行いましょう。
・遺留分 侵害額請求権の時効
遺留分も相続税の申告が必要
遺留分に関する金銭等を取得した場合は、相続税の課税対象です。
遺留分侵害額請求で取得した財産を受け取った場合、相続税が課税されます。
法定相続人に最小限保障されている相続だから非課税になるというわけではありません。
課税要件を満たす場合は、必ず相続税申告を行いましょう。
まとめ
相続で損をしないためには、相続財産を把握して自身の遺留分が侵害されていないか把握することが大切です。
遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を行いましょう。
話し合いで解決することもありますが、調停や訴訟になる場合もあります。
正しく相続財産を把握して遺留分侵害額請求をスムーズに行うためには、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士ならば代理人として話し合いを行い、調停や訴訟になった場合も手続きなど全てを任せられます。
・遺留分を弁護士に相談する7つの
メリットと2つの注意点
遺産相続の遺留分は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡いただければと思います。