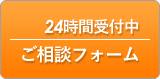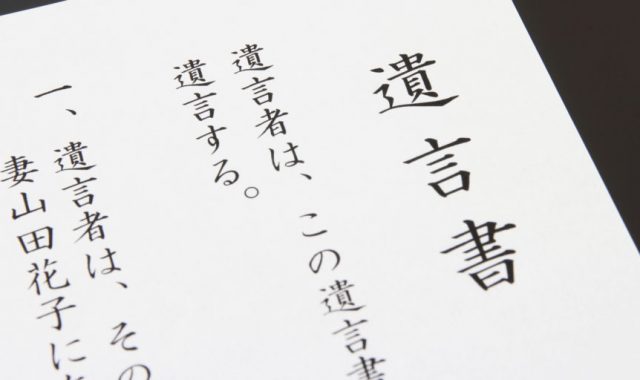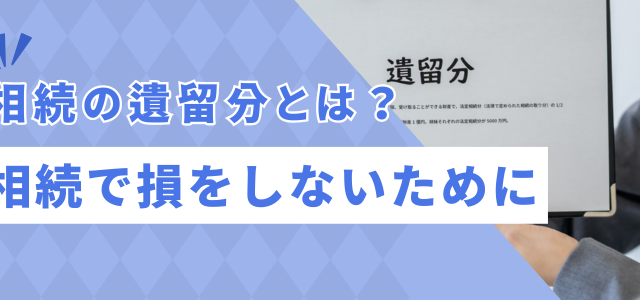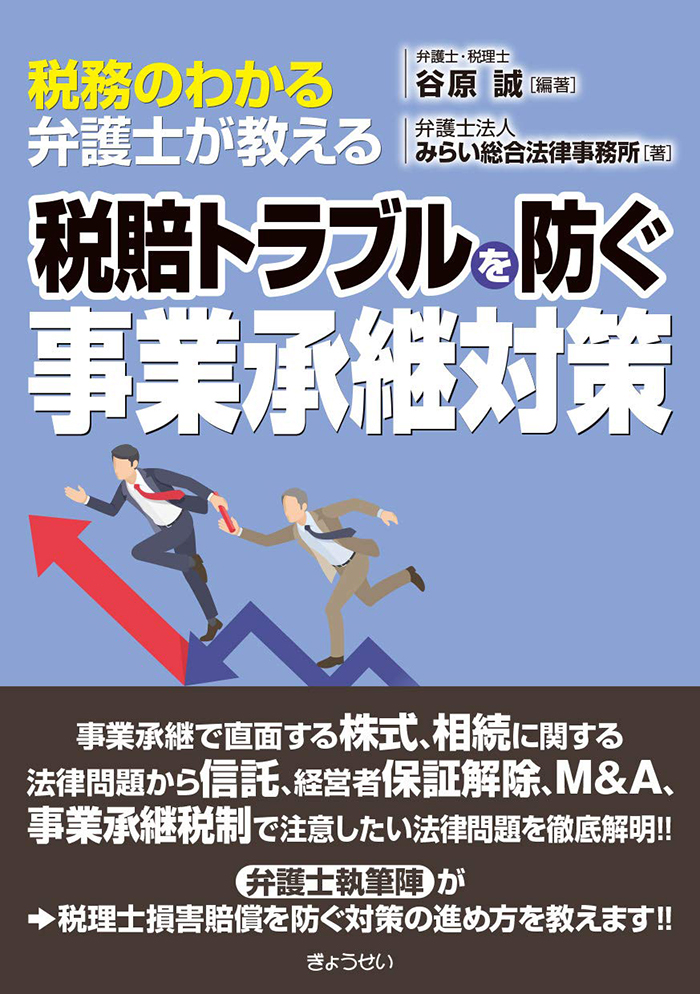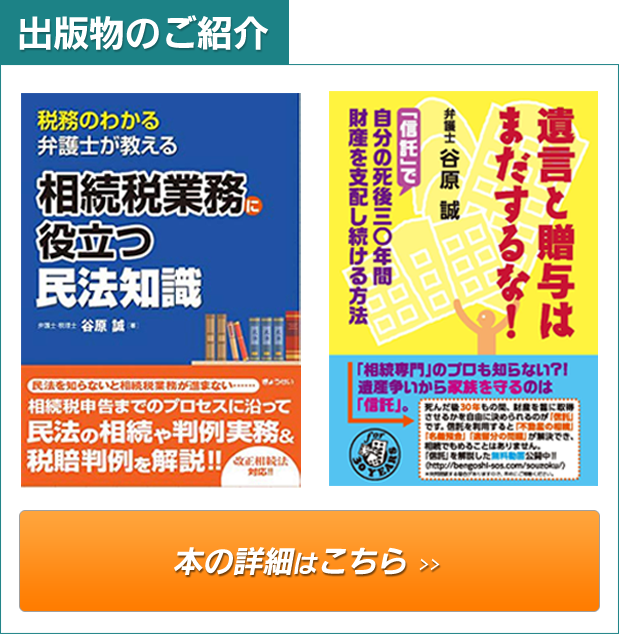遺産相続で遺言書の正しい書き方と間違った書き方
遺言書があると相続のトラブルを回避できる!?
遺言書というと、多くの人がその存在自体はご存知のことと思います。
しかし、「どういった内容で、どのように書けばいいのか」について正確に答えられる自信がない、という方も少なからずいらっしゃるでしょう。
相続は、被相続人(親など)の死亡によって開始します(民法第884条)。
その時、子供などの相続人はまず遺言の有無を確認することが必要になります。
というのは、遺言があるかどうかで遺産分割の要否が異なるからです。
遺言書がある場合は、記載されている内容に従って相続を進めていきます。
つまり、被相続人の立場からすると、遺言書は自分が死んだ後、自分の財産をどう承継していくかを自分で決められる制度であり、自分の意志を相続に反映させることができるものといえるのです。
一方、遺言書がない場合は相続人同士で分割方法や割合などを決定するために、「遺産分割協議」を行なう必要があります。
遺産相続において遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割をしなければ遺産を相続することができないからです。
通常、遺産分割の内容は「遺産分割協議」によって決定しますが、協議が調わない場合には「遺産分割調停」、さらに調停が成立しない場合は「遺産分割審判」の手続を経る必要があり、場合によっては解決までに何年もかかってしまいます。
そこで、相続人の間の争いをなくすために、近年では遺言書を遺しておく人が増えているのです。
【参考資料】:遺産分割調停(最高裁判所)
遺言書を作成したほうがいい人
とは?
本記事では、遺言書に関する次のような項目について、できるだけわかりやすく解説していきます。
- どういった種類があるのか?
- どのようなメリットがあるのか?
- 正しい書き方は?
- 無効とされないために気をつけるべきことは? など
また、次のような方は遺言書を作成するほうがいいので、最後まで読んでください!
- 法定相続人以外の人に
遺産を相続させたい(内縁の妻など) - 子供の配偶者や孫などに
遺産を渡したい - 特定の相続人に多くの財産を渡したい
- 子供がいない夫婦
- 離婚した前妻や前夫の子がいる
- 相続人(子など)同士の仲が悪い
人生において、遺産の相続は避けては通れないものの一つともいえます。
この機会に、相続と遺言書について深く知ることでトラブルのない、よりよい相続を実現していただきたいと思います。
目次
まずは“遺言”で知っておきたい
6つのこと
遺言/遺言書とは?
自分の死後、財産を “誰に” “どのように” 残したいのか──生前にその想いや意思を家族に伝え、残すための手段として「遺言」があります。
被相続人(故人)の最終意思を尊重する制度が遺言であるため、遺産相続の内容や配分は自分で自由に決めることができます。
遺言は、民法で定められた所定の方式によらなければいけません。
そのため、親などの被相続人が子供などの相続人に対して、口頭で伝えても有効な遺言にはならないことに注意が必要です。
そこで遺言の内容を文章で記載した、法的な効力のある書類が「遺言書」になります。
なお、遺言には「ゆいごん」と「いごん」の2つの読み方があります。
「ゆいごん」は、広い意味で使われる一般的な読み方です。
それに対し「いごん」は法律用語で、法的効力を持つ意思表示としての「遺言」の場合に使われます。
通常、弁護士や司法書士などが法的・専門的な文脈で使うもののため、法的効力を持つ遺言書は「いごんしょ」と読み、発音します。
遺言は、遺言者の最終的な意思を尊重するため、いつでも撤回することができるとされています。
遺言は、遺言者の死後に効力を生じるものであり、受遺者(遺言によって財産を受け取る人で個人、法人、血縁関係のない人も含む)は遺言者の生存中は何らの権利もありません。
遺言書は全部で7種類
民法は、遺言の形式を次の7種類に限定しています。
【普通方式】
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
【特別方式】
<危急時遺言>
④死亡危急者遺言
⑤船舶遭難者遺言
<隔絶地遺言>
⑥伝染病隔離者遺言
⑦在船者遺言
これらの中でも、自筆証書遺言(民法968条)と公正証書遺言(民法969条)を利用するのが一般的です。
正しい書き方や注意するべきポイントなどについては、後ほど詳しく解説します。
遺言書の8つの効力/
記載できる内容について
民法では、遺言書に記載した内容について法的効力が認められる範囲が定められています。
- 財産の分配・処分に関する事項
(誰に、何を、
どれだけ相続させるか) - 身分に関する事項
(子などの近しい人の
身分の指定など) - 遺言の執行に関する事項
(遺言書に残しておかなければ
有効にはならない)
遺言書に記載できる内容は次の8点です。
記載することによって法的な効力(拘束力)をもたせることができるので具体的に見ていきましょう。
相続分の指定
(民法第902条1項)
遺産のうちの、何を、誰に、どのくらい相続させるかについて、基本的には自由に指定することができます。
ただし、相続人には遺留分があるので、これを侵害することは遺言でもできないことに注意が必要です。
遺産分割方法の指定
(民法第908条)
「長男には不動産(家と土地)を、長女には預貯金を相続させる」
「主な遺産は自宅なので、これを売却して得た金額を長男と次男で2分の1ずつ相続させる」
といったように、遺産の分割方法を遺言書で指定することができます。
ただし、遺言書の分割方法は絶対ではありません。
遺産分割協議で、すべての相続人が同意すれば、遺言書とは異なった分割方法を選択することもできます。
遺贈の指定(民法第964条、
第986条~第1003条)
遺言によって他人に遺産の一部またはすべてを渡すことを「遺贈」といいます。
たとえば法律上、子が亡くなっていなければ代襲相続で孫に相続させることはありませんが、かわいい孫に遺産の一部を渡したい場合などでは、遺言書で遺贈について指定することができます。
非嫡出子の認知
(民法第781条2項)
「非嫡出子」とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことです。
遺言者は、遺言で非嫡出子を認知する旨の記載をすることで、認知することができます。
未成年後見人の指定
(民法第839条1項)
「未成年後見人」とは、親権者の死亡などで未成年者に対して親権を持つ人がいない場合に、未成年者の代理人となって監護養育や財産管理、契約などの法律行為などを行なう人のことです。
未成年の子供がいて遺言者の死亡により親権者いなくなる場合、遺言書によって未成年後見人を指定することができます。
相続人の廃除(民法第893条)
生前、遺言者が特定の相続人から虐待や重大な侮辱などを受けるなどしていたために、絶対に相続させたくないと思わざるを得ないような事情があった場合に限り、その相続人の地位をなくして権利を奪うことができます。
生命保険金の受取人を変更
(保険法第44条)
保険金の受取人を変更する場合、通常であれば契約変更の手続きが必要です。
しかし、遺言書に受取人を変更する旨を記載することで、契約変更の手続きをせずに受取人を変更することができます。
遺言執行者の指定
(民法第1006条1項)
遺言者の死後、「遺言執行者」は遺言の内容に従って、財産目録の作成、金融機関での預貯金の名義変更、不動産の相続登記などの実務を行ないます。
遺言執行者を指定したい場合は、遺言書にその旨を記載します。
なお、遺言執行者は未成年者と破産者以外であれば誰でもなれ、法人もなれます。
遺言書に記載しても法的効力が発生しないこととは?
前述の8つの項目以外については、遺言者が遺言書に記載しても法的な効力が発生しない(無効になる)ため注意が必要です。
具体的な例として、ここでは次の2つの事柄について解説します。
遺留分を侵害する内容
遺留分とは、遺言によっても侵害することができない相続人の最低限の権利のことで、民法により保証されているものです。
たとえば、亡くなった父親(被相続人)が残した遺言書に、
「全財産は長男に相続させる」
「遺産は再婚相手とその子供に相続させ、前妻との間の子供には相続させない」
といった内容が記載されている場合、法定相続人・相続分よりも遺言書が優先するとはいえ、遺留分は守られるため、記載以外の相続人も受け取ることができるわけです。
そのため、たとえ遺言書に「遺留分は認めない」などと記載しても、侵害された遺留分に相当する金銭の支払い請求を無効にすることはできないので注意してください。
付言事項(法定遺言事項以外の希望や想いなど)
家族への気持ち(感謝の想いや願いなど)や自分の希望(葬儀や法要についての希望など)を遺言書に書いておきたいと考える方もおられると思いますが、こういった事柄(付言事項)には法的効力はないことを知っておいてください。
会社経営者が自分の死後、誰に会社を引き継いでほしいかといった事業承継や、あるいは売却などの希望の記載も法的効力はありません。
遺体の処置方法や臓器移植への提供といった希望の記載も法的効力はありません。
ただし、こうした付言事項を記載しても遺言書が無効になることはありません。
そのため、ご自身の希望などを記載しておくかどうかは自己判断であり、法的に問題にはなりません。
遺言が重要な理由/
作成するメリット
遺言があれば自分の財産を
自由に処分できる
日本国憲法により私有財産権が保障されていることから、私たち日本国民は生前に自分の財産を自由に処分することができます。
遺留分制度など一定の制限はありますが、遺言制度は被相続人の意思を尊重する制度でもあるため、原則として遺言内容のとおりに実現されます。
なぜなら、遺言制度というのは私有財産権を死後にまで広げたものでもあるからです。
そのため、遺言があれば自分の財産を自由に処分できるわけです。
なお、法的には15歳以上の人が遺言をすることができるとされています(民法第961条)が、自分の財産を処分するだけの意思能力を備えていることが必要となります。
相続トラブルの防止になる
遺言は、被相続人の死後の紛争回避にも役立ちます。
遺言がない場合、被相続人の遺産は遺産分割により分割されますが、遺産分割協議は必ずしも円満に行なわれるとは限りません。
特に遺産に不動産があるような場合では、相続人のうちで誰が不動産をどういった割合で相続するのか、不動産の評価額はどうするのか、などで紛糾することがしばしば起こります。
しかし、遺言によって、誰が、どの遺産を相続するのかを明確にしておけば、遺産分割協議が不要になるので紛争を回避することができます。
また、推定相続人の状況によっては、配偶者の生活保障を図ることもできます。
たとえば、夫が被相続人で夫婦には子供がおらず、夫には兄がいるという場合で考えてみます。
夫(被相続人)が死亡した場合の相続人は配偶者である妻と兄で、法定相続分は、妻が4分の3、兄が4分の1と定められています。
そこで、こうしたケースでは、夫が遺言に「すべての遺産を妻に相続させる」としておくと、そのとおりの効果を得られます。
それは、遺言があっても遺留分を侵害することはできませんが、兄弟姉妹は遺留分を受け取ることができないからです。
したがって、兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合には、それ以外の人に遺言により遺贈などをすることによって、その意思を実現することができるわけです。
なお、相続開始から5年以内であれば遺産分割を禁じることができます。
遺留分対策でも役立つ
前述のとおり、遺言は遺留分対策にもなります。
遺言がない場合、遺産は法定相続人の間で遺産分割により分割されます。
しかし、被相続人としては、法定相続人以外の人に遺産を渡したい場合もあれば、公益団体に寄付をして公益的目的に遺産を使用してほしい、といった希望があることもあります。
このような場合にも遺言をしておくことにより、その意思を実現することができます。
さらに、法的効果ではなく事実上の効果ではありますが、相続人からの「遺留分侵害額請求」の行使を抑制する効果があります(旧民法では遺留分減殺請求権)。
たとえば、夫が被相続人で、推定相続人が妻と長男のケースで考えてみます。
全遺産を妻に相続させるという遺言内容の場合、長男には遺産の4分の1の遺留分を受け取る権利があるので、母(被相続人の妻)に対して遺留分侵害額請求をした場合は、その通りの割合が長男のものになります。
ただし、ここで考えておきたいのは、被相続人と相続人の気持ち、想いです。
被相続人が遺言書に、すべての遺産を妻に相続させたい気持ちや理由をていねいに記していた場合、それを読んだ長男としても父親の気持ちを大切にしたい、という想いが生まれてくる可能性があります。
その場合は、遺留分侵害額請求を思いとどまるケースもあるでしょう。
前述したように、このような記載を「付言事項」といい法的な効果はありませんが、事実上の効果が期待できる可能性があるわけです。
遺言書に有効期限はあるのか?
遺言書には有効期限はありません。
遺言者が生存している間は、遺言書の法的な効力は生じません。
遺言者が亡くなった瞬間から遺言書の法的効力は発生し、内容や形式に不備がなければ無期限でその効力は有効となります。
遺言書の正しい書き方/
間違いだらけの書き方
ここでは、遺言書の中でも一般的な普通方式遺言の「自筆証書遺言」(遺言者が自筆する)と「公正証書遺言」(公証人と呼ばれる専門家に作成してもらう)について、その内容や正しい書き方、メリットとデメリットなどを解説していきます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは?
- 自筆証書遺言は、遺言者(遺言を遺す人)が自筆で書くものです。
- 法が定める方式に従っていれば効力を生じるので、証人や立会人は必要ありません。
メリットとデメリット
- 費用がかからない。
- 自分1人で作成できる。
- いつでも手軽に書き直すことが
できる。 - 遺言の内容を他人に秘密にできる
(証人が必要ないため)。 など
- 紛失したり、忘れられる場合がある(自分しか知らないため)。
- 見つけた人が勝手に捨てる、
隠してしまう、
書き換えるなどのおそれがある。 - 法律の要件を満たさない場合は
遺言自体が無効になる。 - 有効性を争われやすい
(遺言者の意思能力や本人の意思に基づいたものであるか
どうかなど)。 - 遺言者の死亡後、検認の手続が
必要になる(遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に
遺言書を提出する)。
ただし、法務局の遺言書の保管制度を利用している場合は不要。
自筆証書遺言に記載する項目
自筆証書遺言が成立するためには、次のことを自書し、押印する必要があります。
- 1.遺言の全文
- 2.日付
- 3.氏名
注意するべきポイント
<自書について>
- 遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できません。
※ただし、民法改正により、2019(平成31)年以降は、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになっています。 - 相続財産の全部または一部の目録(預貯金通帳の写し・不動産の登記事項証明書など)を添付する方法で作成する場合は、すべてのページ1枚1枚に署名と押印が必要です。
※各目録の記載がその両面にある場合は、その両面に署名・押印する必要があります。 - 録音や録画による遺言は無効とされます。
- 裁判例には次のものがあります。
カーボン紙による複写を有効としたもの(最高裁平成5年10月19日判決、家月46巻4号27頁)。
視力や体力などに問題があり自力で筆記できない場合に、他人の添え手の補助を受けたとしても、他人の意思が介入した形跡がないことを筆跡から判定できる場合は自書として有効、としたもの(最高裁昭和62年10月8日判決、民集41巻7号1471頁)。
<日付について>
何年何月何日なのか、明確に特定が必要です。
※その理由としては、「遺言をした時に遺言能力を有していたことが必要となること」、「遺言をした後にその遺言と異なる遺言をした時は、後の遺言と抵触する前の遺言の箇所は撤回したものと見なされるため、いつ遺言をしたのかが重要となること」などがあげられます。
※「2025年10月吉日」などの記載は、日付を特定できないため無効になります。
一方、「2025年の私の誕生日」という記載は、日付を特定できるので有効となります。
<氏名について>
遺言者を特定できるなら、通称や雅号、ペンネーム、芸名でも有効とされています。
<押印について>
三文判でも有効です。
ただし、実印のほうが遺言者の意思が明確であることを立証しやすいといえます。
裁判例には次のものがあります。
指印は有効としたもの(最高裁平成元年2月16日判決、民集43巻2号45頁)。
花押(図案化された署名の一種、署名の代わりに使用される記号・符号)は無効としたもの(最高裁平成28年6月3日判決、民集70巻5号1263頁)。
遺言書の署名に押印がないが、遺言書を入れた封筒の封じ目に押印があった事例で有効としたもの(最高裁平成6年6月24日判決、家月47巻3号60頁)。
<財産について>
誰に、どの財産を、どのぐらい残すかを具体的に記載する必要があります。
まずは、自分の財産をリスト化して、整理しておくのがいいでしょう。
<保管について>
自宅などの好きな場所で保管することができますが、より安全を望むなら直筆証書遺言を作成して法務局で保管する方法もあります。
自筆証書遺言書は、民法に定められた最低限守るべき要件を満たしていないと無効になってしまうので注意が必要です。
・遺言書(ひな形)
【参考資料】:遺言書の記載例①(法務局)
【参考資料】:遺言書の記載例②(法務局)
自筆証書遺言書保管制度に
ついて
せっかく作成した自筆証書遺言書が次のような理由で無効になってしまうことは、避けたいところです。
- 作成した遺言書に不備があった
- 遺言書を自宅で保管している間に
改ざん・偽造されたり、紛失した - 遺言書の存在に遺族が
気づかなかった
そこで、これらの問題を解消するため、相続法改正により2020年7月10日以降、法務局による自筆証書遺言書の保管制度が設けられています。
詳しい内容については法務省のサイトなどで知ることができます。
【参考資料】:自筆証書遺言書保管制度について(法務省)
【参考資料】:遺言書保管申請ガイドブック(法務省)
【参考資料】:遺言書の様式等についての注意事項(法務省)
公正証書遺言
公正証書遺言とは?
公証人が関与して作成し、原本が公証役場に保管される遺言です。
遺言の公正証書は3通作成され、原本は公証役場に保管され、正本と謄本は遺言者などに交付されます。
遺言者の死亡後、利害関係人は遺言の有無を検索することができます。
公正証書遺言と自筆証書遺言は優劣の関係にはないため、 公正証書遺言のほうが優先するわけではないことに注意してください。
公正証書遺言作成の手続き
- 1.遺言者が遺言の案文を事前に公証人に
交付し、これに基づいて公証人と
打ち合わせをして内容を確定させます。 - 2.証人2人以上の立ち会いで、
遺言者が遺言の趣旨を
公証人に口頭で伝えます。 - 3.公証人が口述を筆記し(公証人が
事前に証書を作成しておく場合が多い)、
その遺言を公証人が遺言者および証人に
読み聞かせ、または閲覧させます。 - 4.遺言者および証人は、筆記が正確なことを承認し、署名・押印します。
- 5.公証人が方式に従って作成したことを
付記して、署名・押印します。
メリットとデメリット
- 遺言者の意思に基づいて作成されたことを証明しやすい
(公証人が関与して作成される
ため)。 - 紛失・偽造・改ざんのおそれがない(原本が公証役場に保管される
ため)。 - 家庭裁判所の検認の手続きが
必要ない。
- 作成手数料がかかる。
- 遺言の内容が証人と公証人に
知られてしまう。
【参考資料】:自筆証書遺言と公正証書遺言の違い(法務局)
【参考資料】:遺言(日本公証人連合会)
遺言書作成の前後で
大切なポイントまとめ
遺言書が見つかったら
家庭裁判所の検認を受ける
相続開始を知った後、遺言書が発見されたなら、公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所に提出して検認の手続をする必要があります(民法第1004条)。
管轄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
遺言書が封印されている場合は、相続人またはその代理人の立ち会いを得て、家庭裁判所で開封される必要があります。
そのため、遺言書は勝手に封印を開封してはいけません。
家庭裁判所以外で開封した場合、また検認手続を得ないで遺言を執行した場合は、5万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります(民法第1005条)。
ただし、遺言が無効になるわけではありません。
家庭裁判所による検認の手続は証拠保全を目的とするため、遺言書の有効性や効力については判断されません。
遺言書の有効性に疑問がある場合は、検認手続後、訴訟などで争うことが可能です。
自分に不利な内容が書いていること知ったなどの理由で、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿をした場合は、相続人の欠格事由に該当するため(民法第891条5号)、相続人になれなくなるので注意が必要です。
自筆証書遺言の保管制度を利用した場合は、検認は不要となります。
【参考資料】:遺言書の検認(裁判所)
遺言書が無効とされないために
大切なこと
法律で定める要式に従って
作成する
遺言は、遺言者の死後に効力を生じるものであり、遺言の効力発生時に遺言者に真意を確認することができません。
そのため、遺言者の真意を明確にし、他人の偽造・変造を防止するために法律で定める要式に従って作成することが要求されています。
代理は認められない
遺言は、遺言者の最終的な意思を尊重することから、本人の独立した意思が必要であり、代理も許されません。
【参考資料】:知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方(政府広報オンライン)
公正証書遺言の有無を
調べてみる
被相続人が公正証書遺言を作成していたかどうかがわからない場合は、最寄りの公証役場で遺言書の有無などを検索することができます。
全国の遺言者のデータを日本公証人連合会がコンピュータで管理しており、このデータから調べることができるわけです。
なお、データには氏名、生年月日、公正証書を作成した公証人名、作成年月日など含まれますが、遺言内容は含みません。
申請できるのは相続人などの利害関係人に限られますが、遺言検索システムを利用するには利害関係を証明しなければいけません(除籍謄本、戸籍謄本、自分の身分証明書などが必要)。
なお、相続開始前は推定相続人であっても申請できません(何の権利も発生していないため)。
遺言で不安があれば
弁護士に相談してください!
ここまで遺言と遺言書について解説してきましたが、どうでしょう?
ご自身で「遺書」を作成したい場合は、自由に書くことができますが、「遺言書」の場合は法的な手続きなどが必要になるため、思った以上に難しいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
被相続人の方が遺言書を作成する場合や、相続人の方が遺言書を発見した場合は、まずは一度、弁護士に相談してください。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
あなたからのご連絡をお待ちしています。