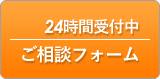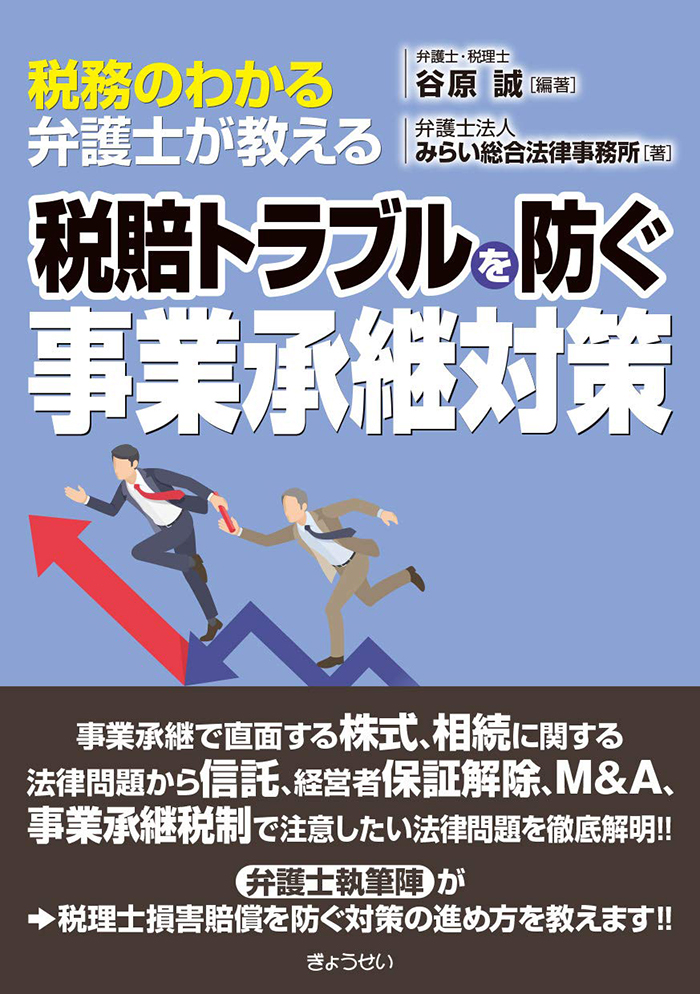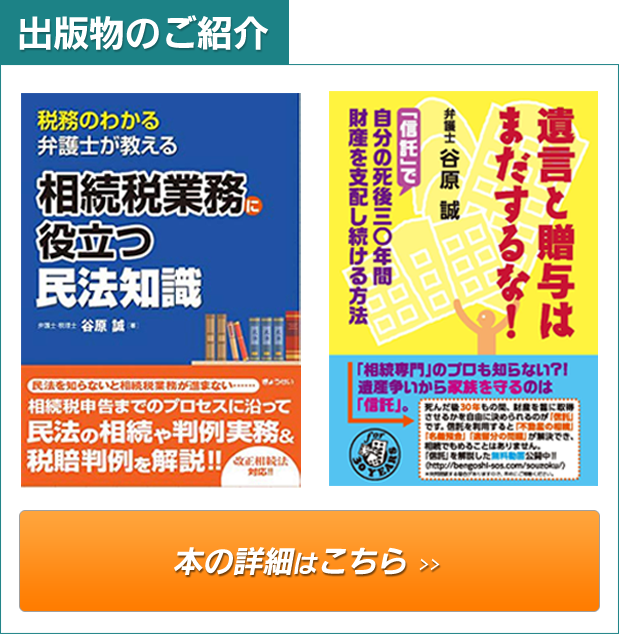遺言で遺産を贈与する遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産を無償で第三者に与える行為です。
特定の財産を遺贈することを「特定遺贈」、財産の全部または一定の割合を遺贈することを「包括遺贈」といいます。
たとえば、お世話になったAさんに自宅土地建物をあげたいときに、「自宅土地建物をAに遺贈する」というように、財産を特定して遺言書に記載すると、「特定遺贈」となります。
これに対し、財産を特定せずに、「遺産の3分の1をAに遺贈する」というように記載すると、「包括遺贈」となります。
ただし、「相続人」に対して遺言書で特定の財産を相続させる旨の遺言書は、「その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではなく」、遺産分割方法の指定と解されています(最高裁平成3年4月19日判決、民法百選Ⅲ86)。
遺言は、遺言者の死亡のときにその効力を生じます(民法第985条1項)。
そして、相続人が遺贈の義務を履行することになります。
ただし、遺言執行者があるときは、相続人ではなく、遺言執行者が遺贈の義務を履行します。
特定遺贈とは
特定の財産を遺贈することを「特定遺贈」といいます。
特定遺贈は、「自宅土地建物(実際には、地番、地積、地目等で、間違いないように特定します)」のように、すでに特定されている財産でも、「金の延べ棒3本のうち1本」というような不特定物でも認められます。
すでに特定されている特定物の遺贈の場合には、遺贈の効力が発生すると同時に所有権が受遺者に移転します。
不特定物の場合には、受遺者は目的物を特定して自己に移転するよう請求する権利があり、遺贈義務者が目的物を特定したときに、遺贈の目的物の所有権が受遺者に移転するとされています(東京高裁昭和23年3月26日判決、高民集1巻1号78頁)。
ただし、特定遺贈の場合には、所有権の移転を第三者に対抗するには、対抗要件を具備する必要があります(最高裁昭和39年3月6日判決、民法百選Ⅲ73)。
たとえば、太郎が、遺言でAに自宅土地建物を遺贈したにもかかわらず、太郎の相続人であるBが相続を原因とする所有権移転登記をし、自宅土地建物を第三者であるCに譲渡して所有権移転登記をしたとします。
この場合には、Aは、所有権移転登記をしていないので、第三者であるCに対抗できず、その結果、自宅土地建物の所有権移転登記を得ることができません。
この場合には、Bに損害賠償請求をすることになります。
ただし、この場合でも、遺言執行者がいる場合には、受遺者は登記その他の対抗要件を具備することなしに、第三者に対抗することができる、とされています。
しかし、このような異なる取扱では第三者の保護に欠けるため、改正相続法では、この場合でも、対抗要件なくして善意の第三者に対抗することはできない、とされました。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができます。
この場合には、遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます(民法第986条)。
受遺者が遺贈の放棄をするときは、相続放棄ではなく、遺贈義務者または遺言執行者に対する意思表示をすることになります。
ただ、いつでも遺贈の放棄をすることができるとなると、遺贈義務者の地位を不安定にしますので、遺贈義務者などの利害関係人は、受遺者に対して、相当の期間を定めて、遺贈を承認または放棄するよう催告することができ、受遺者がこの期間内に承認または放棄の意思表示をしないときは、遺贈を承認したものとみなされます(民法第987条)。
包括遺贈とは
財産の全部または一定の割合を遺贈することを「包括遺贈」といいます。
遺産の全部を遺贈することを「全部包括遺贈」、遺産の一定割合で示された部分を遺贈することを「割合的包括遺贈」といいます。
そして、包括遺贈の受遺者を「包括受遺者」といいます。
包括遺贈は、遺産の全部または一定の割合なので、積極財産だけでなく、消極財産も含みます。
包括遺贈をするには、たとえば全部包括遺贈の場合は、遺言書で「私の遺産の全てをAに遺贈します」のように記載し、割合的包括遺贈の場合は、「私の遺産の3分の1をAに遺贈します」のように記載します。
包括受遺者は、遺贈の効力発生と同時に遺産を承継します。
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民法第890条)。
ただし、相続人の誰かが相続放棄をした場合に、他の相続人の相続分が増加しますが、包括受遺者が遺贈される遺産が増加するわけではありません。
包括受遺者も、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができます。
この場合には、遺贈の放棄は遺言者の死亡のときにさかのぼってその効力を生じます(民法第986条)。
包括受遺者が遺贈の放棄をするには、自己のために包括遺贈があったことを知ったときから3ヵ月間の熟慮期間内に家庭裁判所に申述することによって行います。
限定承認も同様です。
相続放棄も限定承認もせずに熟慮期間を経過した時は、遺贈を単純承認したことになります(民法第921条2号)。
割合的包括遺贈の場合には、遺産の一定割合で示された部分を取得しますので、他の相続人や他の割合的包括受遺者と遺産を共有することになります。
そして、共有状態を解消するには、遺産分割手続を行うことになります。
包括遺贈の場合にも、所有権の移転を第三者に対抗するには、対抗要件を備える必要があります(大阪高裁平成18年8月29日判決、判例時報1963号77頁)。
遺言執行者がいる場合には、受遺者は登記その他の対抗要件を具備することなしに、第三者に対抗することができる、とされています。
改正相続法では、この場合でも、自己の法定相続分を超える部分の取得については、対抗要件なくして善意の第三者に対抗することはできないとされました。
包括遺贈の場合には、受遺者は積極財産だけでなく、消極財産も取得します。
相続財産に金銭債務のような可分債務が含まれている場合には、可分債務は、相続開始によって法定相続分に従って当然に分割承継されます(大審院昭和5年12月4日決定、民集9巻1118頁)。
したがって、債権者は、遺贈の如何にかかわらず、各法定相続人に法定相続分に従って分割承継された債務の支払を請求することができます。
改正相続法では、相続分の指定がなされた場合であっても、相続債権は各共同相続人に対して、その法定相続分の割合でその権利を行使することができますが、相続債権者が共同相続人の一人に対して指定相続分の割合による義務の承継を承認したときは、各共同相続人に対して、その法定相続分の割合でその権利を行使することはできず、その指定相続分の割合でその権利を行使することができることとされました。
条件または期限付遺贈とは
遺言者は、遺贈をするにあたり、遺贈の効力の発生に条件や期限を付すことができます。
遺贈の効力を条件にかからせる場合を「停止条件付遺贈」、期限にかからせる場合を「期限付遺贈」といいます。
たとえば、「孫が東京大学に入学することを条件に遺贈する」というような条件をつければ停止条件付遺贈となり、「孫の20歳の誕生日に遺贈する」というような期限をつければ期限付遺贈となります。
停止条件付遺贈の場合には、条件が成就したときに遺贈の効力が生じます。
期限付遺贈の場合には、期限が到来したときに遺贈の効力が生じます(民法第985条2項)。
遺贈の効力が生じるまでは、受遺者は遺贈義務者に対して履行請求をすることができません。
条件成就または期限到来の前に、相続税申告期限が到来する場合には、未分割として申告することになります。
この場合の処理については、相続税基本通達は次のように定めています。
11の2-8 停止条件付の遺贈があった場合において当該条件の成就前に相続税の申告書を提出するとき又は更正若しくは決定をするときは、当該遺贈の目的となった財産については、相続人が民法第900条((法定相続分))から第903条((特別受益者の相続分))までの規定による相続分によって当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。
ただし、当該財産の分割があり、その分割が当該相続分の割合に従ってされなかった場合において当該分割により取得した財産を基礎として申告があった場合においては、その申告を認めても差し支えないものとする。
(昭57直資2-177、平17課資2-4改正)
負担付遺贈とは
遺言者は、遺贈するにあたって、受遺者に対して一定の給付義務を課すことができます。
これを「負担付遺贈」といいます。
たとえば、「私の全ての遺産をAに遺贈する。
その代わりに、Aは、私が死ぬまで扶養すること。」などとする場合です。
負担付遺贈は、停止条件付遺贈などと異なり、遺言者の死亡によって効力を生じます。
効力が生じたうえで、受遺者の給付義務が残ることになります。
過大な負担が付された時は、受遺者は、遺贈の目的の価額を超えない限度でのみ、負担する義務を負うことになります(民法第1002条1項)。
遺贈に対して遺留分減殺請求権が行使されて、取得する遺産が減少した場合は、その減少した割合に応じて負担した義務を免れることになります(民法第1003条)。
受遺者が負担付遺贈を放棄したときは、受益者が受遺者になることができます(民法第1002条2項)。
受遺者が負担を履行しないときは、相続人および遺言執行者は、受遺者に対して、相当の期間を定めて負担の履行を求めることができ、期間内に履行されないときは、家庭裁判所に負担付遺贈の取り消しを請求することができます(民法第1027条)。
負担付遺贈の課税価格の計算については、相続税法基本通達で次のように定められています。
11の2-7 負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額によるものとする。