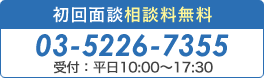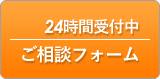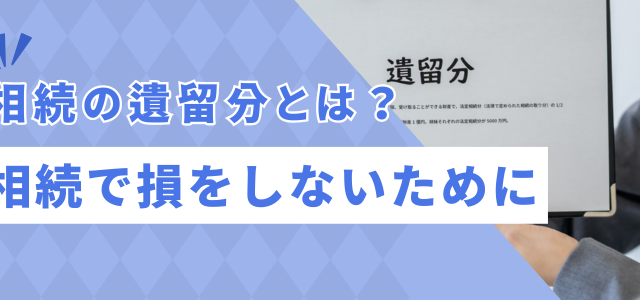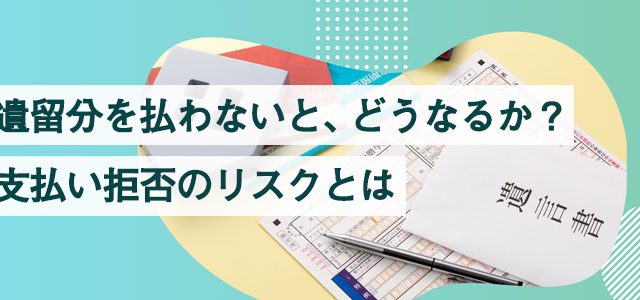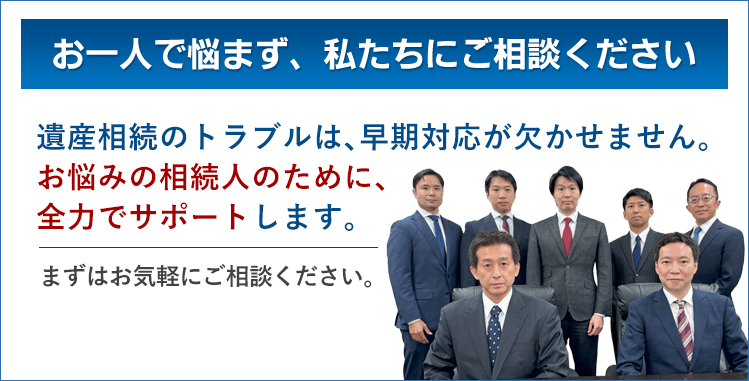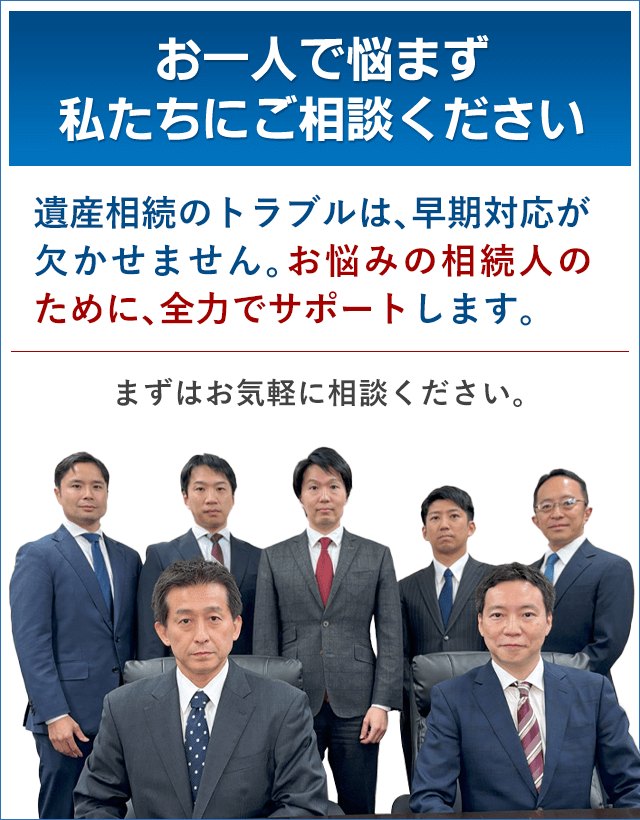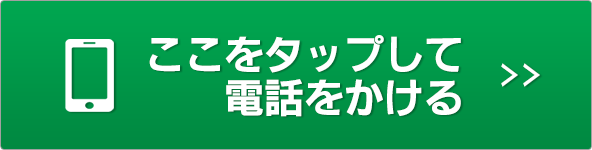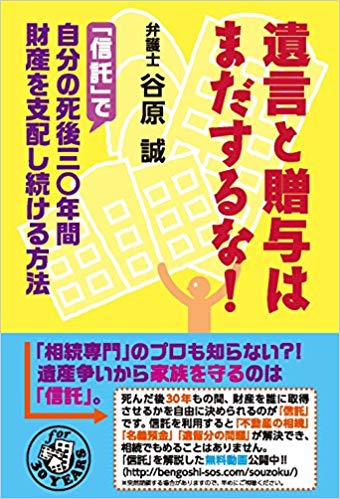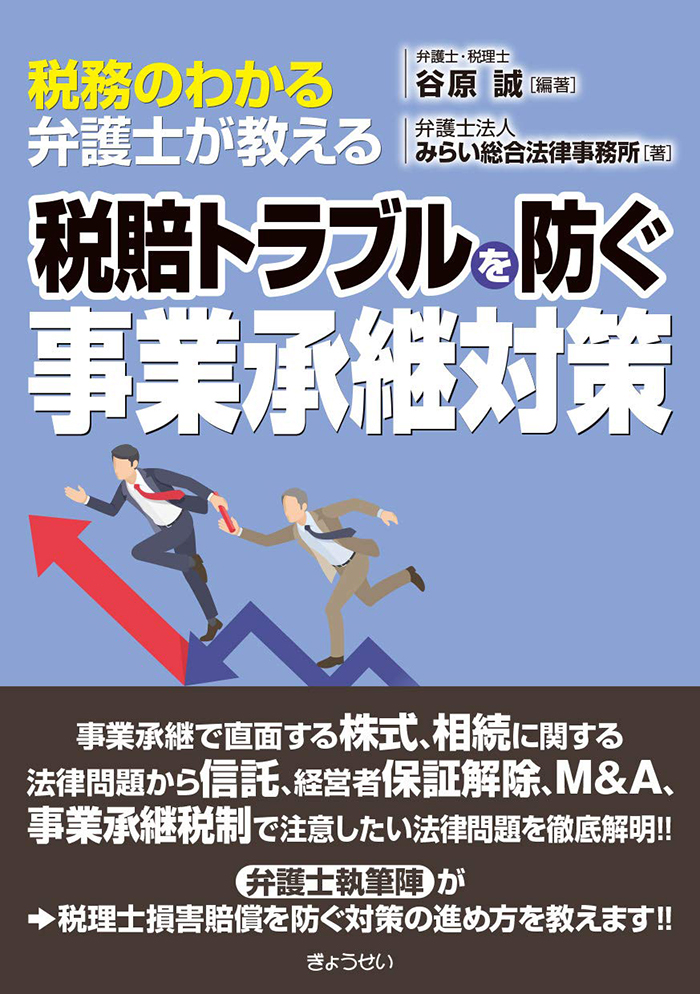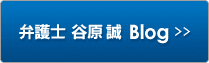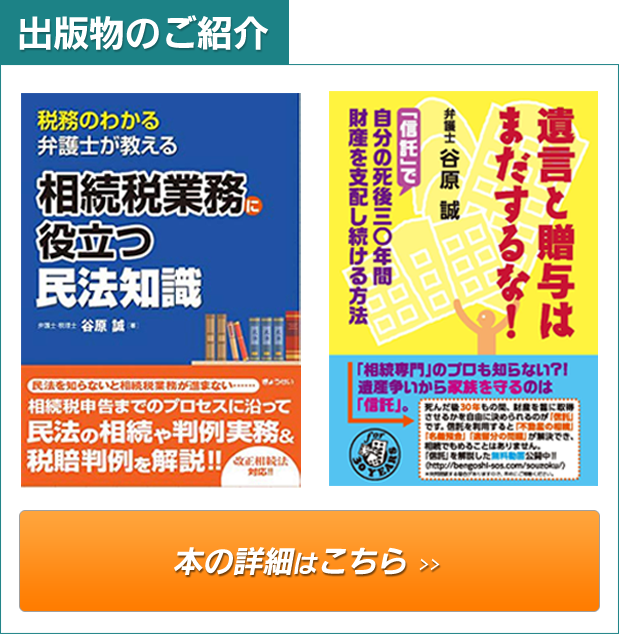遺留分の計算
親などの被相続人が亡くなった場合、遺言がなければ、配偶者や子供などの法定相続人が話し合い(遺産分割協議)を行なって、相続する財産の内容や割合について決定していきます。
一方、遺言があるなら、その内容が優先されるため、遺言に従って遺産分割を進めていくのですが、ここで問題になるケースがあります。
それは、遺言の内容が不公平なため、納得がいかない相続人がいて、親族間トラブルに発展する場合です。
こうしたケースでは、不公平に財産を侵害された相続人は、多く相続した人に対して「遺留分侵害額請求」をして、遺留分を受け取ることができます。
その請求が正当なものであれば、法的に遺留分の支払いが実行されるわけです。
そこで本記事では、遺留分に関する次のテーマについて解説していきます。
- 遺留分の概要
- 遺留分を受け取れる人/受け取れない人
- 遺留分の対象になる財産の種類
- 遺留分の計算方法
- 遺留分の請求で注意するべきポイント など
遺留分を請求された方、また遺留分侵害額請求をしたいと考えている方の双方とも、ぜひ遺留分の正しい知識を身につけて、相続問題の解決に役立てていただきたいと思います。
目次
これだけは知っておきたい!
遺留分の5つのポイント
遺留分とは?
法定相続人が受け取ることができる最低限の割合を「遺留分」といい、民法で保障されている権利です。
遺留分は、遺族の生活保障と被相続人の遺産形成に対する寄与という目的もあります。
そのため、遺留分は遺言によっても侵害することができません。
たとえば、被相続人が次のような遺言を遺したとします。
「遺産のすべてを長男に相続させる」
「全財産を内縁の妻に渡す」
しかし、他の法定相続人(長女や次男、次女、本妻など)はまったく遺産を受け取れないとなると被相続人に頼って生活していた相続人の生活が成り立たなくなったりするので、遺留分を受け取ることができる仕組みがあるわけです。
遺留分侵害額請求とは?
遺言のとおりの相続分では適正な遺産を受け取れない場合、その法定相続人は「遺留分侵害額請求」をすることができます。
一方、遺留分侵害額請求を受けた側の人は、次のポイントを確認する必要があります。
- 請求者は本当に遺留分権利者か?
- 遺留分侵害額請求権の時効は
成立していないか? - 適切な請求額か?
なお、遺留分侵害額請求を受けた場合は放置しないようにしてください。
遺留分侵害額請求に対して何ら対応しないまま放置すると、調停や訴訟に発展する可能性もあるからです。
いずれにしても、遺留分侵害額請求にまで発展した場合は弁護士に相談されることをおすすめします。
遺留分を受け取れる人と
その割合は?
遺留分が認められる法定相続人は次のとおりです。
- 配偶者(法律上の婚姻関係にある者)
- 子(直系卑属:実子、養子、
認知された子、および代襲相続人である
孫や
ひ孫) - 父母(直系尊属:父母、養親、
および祖父母)
※代襲相続:相続開始前に、本来であれば相続人となるはずだった人が死亡や相続権を失った場合に、その人の子や親が代わりに相続する制度。
たとえば、被相続人から見て、子供が亡くなっている場合、「孫」がいれば代襲相続人になる。
遺留分の割合は法定相続人ならすべて同じというわけではありません。
相続の優先順位によって次のように割合が決まっています(民法第1042条)。
- 配偶者や子が相続人の場合:
相続財産の2分の1 - 直系尊属のみが相続人の場合:
相続財産の3分の1
<遺留分の割合の早見表>
| 相続人 | 遺留分 合計 | 配偶者の 遺留分 | 子供の 遺留分 | 親の遺留分 | 兄弟の 遺留分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 のみ | 1/2 | 1/2 | – | – | – |
| 配偶者と 子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | – | – |
| 配偶者と親 | 1/2 | 1/3 | – | 1/6 | – |
| 配偶者と 兄弟 | 1/2 | 1/2 | – | – | – |
| 子供のみ | 1/2 | – | 1/2 | – | – |
| 親 のみ | 1/3 | – | – | 1/3 | – |
| 兄弟のみ | – | – | – | – | – |
遺留分を受け取れない人もいる
法定相続人であっても、兄弟姉妹、甥や姪には遺留分は認められないことに注意してください。
さらに、次に該当する人は、本来であれば遺留分の対象になる相続人であっても、遺留分を受取ることができないので注意が必要です。
相続放棄をした人
注意点として、相続人の間で相続放棄を口頭で伝えているだけの状態では相続放棄は成立しません。
家庭裁判所で相続放棄申述を行なっていることが条件になります。
相続人の廃除になった人
犯罪行為があった、被相続人へ虐待や重大な侮辱を行なっていた、被相続人の財産を不当に処分した、といった場合は相続人を相続から外すことができる制度があり、これを「相続人廃除」といいます。
被相続人が遺言で相続人の廃除をし、あるいは家庭裁判所に申し立てて家庭裁判所によって認められた場合、その人は遺留分を受け取ることができません。
相続欠格者になった人
相続人に民法で定められた欠格事由がある場合は、相続権をはく奪されます。
たとえば、自分に相続が優位になるように殺人や詐欺、脅迫を行なった場合や、遺言の偽造、破棄、隠匿等を行なった場合などが該当します。
相続欠格になった場合は一切、遺産の相続ができなくなるため、遺留分も受け取ることができなくなります。
遺留分を放棄した人
相続が開始する前に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行なった人も遺留分は認められません。
なお、相続開始後の場合は権利を行使しなければ遺留分を放棄することになります。
このように、遺留分が認められない人もいるので、遺留分を請求された側の人は、相手が遺留分権利者かどうかを調査する必要があります。
遺留分の対象になる
財産の種類について
次に、遺留分を請求できる財産の種類について見ていきます。
相続開始時のすべての財産
相続開始時に被相続人が所有していたすべての財産(現金、預貯金、不動産、株式、自動車など)は、遺留分の対象になります。
また、借金や税金の滞納分などの負債もすべて対象になります。
遺贈する財産
被相続人が遺言で指定した人に、自分が亡くなった後に財産の全部、あるいは一部を譲る(受け継がせる)ことを「遺贈」といいます。
法定相続人以外の人にも財産を譲ることができるのが相続との違いになります。
そのため、法定相続人が遺贈を受けた人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
生前贈与した財産
被相続人が生きているうちに、配偶者や子、第三者などに財産を譲り渡すことを「生前贈与」といいます。
法定相続人の遺留分が侵害されている場合、相続開始より一定期間前以内に生前贈与した財産は遺留分の対象になるため、贈与された人(受贈者)に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
相続人に対する生前贈与については、特別受益に該当する贈与であり、かつ相続開始前10年以内にされたものに限り、遺留分侵害額請求の対象となります。
相続人以外の者に対する生前贈与については、相続開始前1年以内にされたものに限り、遺留分侵害額請求の対象となります。
なお、上記各期間以上前の生前贈与でも、贈与する側と贈与される側の双方が、他の相続人の遺留分を侵害することを知っていて贈与を行なっていた場合は、その贈与は遺留分の対象になります。
死因贈与する財産
被相続人が死亡した際に、特定の人へ財産を渡す(贈与)ことを約束(契約)するのが「死因贈与」です。
死因贈与された財産も遺留分の対象になります。
遺留分の計算方法を解説します!
民法では、基礎となる遺留分額の計算について次のように規定しています。
財産の価額)
1. 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
これだけでは何を言っているのかわかりにくいので、ここでは基本的な手続きについて、できるだけわかりやすく解説します。
遺留分の計算:
基本の4ステップ
不公平な相続を強いられた相続人の方が、多く相続した相続人に対して、遺留分を請求する場合の計算方法について、流れに沿って解説します。
ステップ①
相続人の確定
- まずは、法定相続人を確定します。
- 配偶者の有無、子の数は通常であればわかると思いますが、念のため被相続人の戸籍謄本を取り寄せ、その他に子がいないかなど確認する必要があります。
- 前述のとおり、被相続人の兄弟姉妹への遺留分は認められません。
ステップ②
財産の調査と洗い出し
- 実際に財産がどのくらいあるのか、まずはプラスの財産(積極財産)を洗い出します。
- 現金、預貯金、実家やそれ以外の不動産、有価証券、自動車や宝石など金銭的価値のあるプラスの財産を合計します。
(※生命保険金や退職金は、受取人が指定されているなら、基本的にその人の固有の財産となります) - さらに、他の相続人などに生前に贈与された分や死因贈与分などがあれば、これらを合計し、プラスの財産に加えます。
- 負債(債務)があれば、それらを合計し、最終的にプラスの財産から引きます。
<加算される贈与の条件>
加算される贈与には、次のような条件があります。
相続開始前1年以内のもの。
2)相続人への贈与(特別受益)は、
相続開始前10年以内のもの。
3)贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って
行なわれた
贈与は、期間に関わらず加算。
※2)の特別受益とは、相続において特定の相続人が被相続人(故人)から、遺贈(遺言による贈与)によって受け、または婚姻や養子縁組のために贈与され、もしくは、生計の資本として贈与された特別な利益のことです。
※3)の「遺留分権利者に損害を加えることを知って」については、「贈与当時の財産状態で遺留分を侵害するという事実の認識」と「将来においても財産が増加し、その結果、遺留分が充足されることはありそうにないという予見」が必要とされています。
※贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行なわれた場合は、一般的な贈与は1年以上前のものでも、また特別受益は10年以上前のものでも、贈与時期に関わらず、すべて財産の価額に算入します。
<相続放棄をした場合の持戻しに
ついて>
特別受益を受けた相続人が、相続放棄をした場合の持戻しについては次のように考えます。
相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったことになります(民法第939条)。
そのため、相続人としての特別受益はなくなり、その観点からの持戻しはなされないこととなります。
そこで、この場合には、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与かどうかが検討されることになります。
相続開始前にされた贈与財産について、いつの時点での価額を遺留分算定の基礎財産に算入するかについては、多数説では相続開始時の貨幣価値に換算されるとされています。
特別受益として贈与された財産を遺留分算定の基礎財産に加える場合、それが金銭である場合には相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価する、とした判例があります。
(最高裁昭和51年3月18日判決(民集30巻2号111頁))
法的なことで判断が難しいため、実際の算定では弁護士に相談されることをおすすめします。
ステップ③
遺留分算定の基礎となる
財産額の計算
- 上記②でわかった財産の状況から、遺留分算定の基礎となる財産額を計算します。
計算式は次のようになります。
プラスの財産の合計額 + 贈与の合計額 -
負債額
ステップ④
遺留分額の算定
- 遺留分算定の基礎となる財産を計算したら、次に遺留分権利者の遺留分侵害額を個別に計算することになります。
- 各相続人の遺留分額は、 「遺留分算定の基礎となる財産額」に「遺留分の割合」を乗じて計算します。
前述したように、遺留分の割合は次のように規定されています。
配偶者や子が相続人の場合:
相続財産の2分の1
直系尊属のみが相続人の場合:
相続財産の3分の1
遺留分侵害額は、この遺留分額から、遺留分権利者が受けた遺贈や特別受益などを差し引いて算出されるので、最終的な計算式は次のようになります。
法定相続分の割合) -
当該遺留分権利者の特別受益額 -
遺留分権利者が
相続によって得た財産の額 + 遺留分権利者が負担すべき相続債務の額
遺留分計算の超シンプルな
具体例
遺留分の計算の例として、ここでは次の条件で考えて、シンプルに算定してみます。
- 相続財産の評価額/3,000万円
- 被相続人(母)の遺言あり
- 遺言の内容/「財産のすべてを長男に
相続する」 - 相続人/長男、長女
父はすでに亡くなっており、その際の遺産は妻(子たちの母)がすべて相続。
今回、この方が亡くなった際の遺言の内容が相続人の1人にとって不公平なものだったケースを想定してみます。
この場合、通常は、長女の法定相続分は長男と均等に分けて2分の1になるため、次のようになります。
そして、遺留分の金額は子供の場合、相続財産の2分の1になるため、次のようになります。
つまり、長女は長男に対して750万円の遺留分侵害額請求ができることになるわけです。
なお、特別受益など贈与がある場合や、負債がある場合は計算が複雑になってくるので、弁護士に相談されるのがいいでしょう。
遺留分はどのように
請求すればいいのか?
さて、ご自身が受け取るべき遺留分の金額がわかったなら、いよいよ遺留分侵害額請求を行なう段階に入ります。
その方法はシンプルで、相手側に対して内容証明郵便を送付して、遺留分侵害額請求の意思表示を行ないます。
相手が死亡している場合は、その相続人に対して内容証明郵便を送付します。
その際の注意点は次の2点です。
自分は遺留分権利者か/
自分の遺留分が
侵害されているかの確認
内容証明郵便を送る前に、「自分が遺留分権利者かどうか」、「その相続で自分の遺留分が侵害されているかどうか」を確認する必要があります。
内容証明郵便の作成・郵送は
弁護士に相談
内容証明郵便は法的なものですから、やはり作成・郵送する際は弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
遺留分侵害額請求では
ここに注意する!
遺留分侵害額請求権の時効に
要注意!
忘れてはいけないことの一つに、時効の問題があります。
ある一定の期間を経過してしまうと、権利自体が消滅してしまうのが「消滅時効」という制度で、遺留分侵害額請求権にも消滅時効制度が定められています(民法第1048条)。
- 遺留分が侵害されている事実を
知ってから1年以内 - 相続開始を知らなかった場合は、
相続開始から10年以内
消滅時効が完成すると、遺留分権利者は遺留分の請求ができなくなってしまうので、上記の期間内に請求をするようにしてください。
なお、時効期間を過ぎていても、相手側が消滅時効の主張をしなければ、遺留分侵害額請求権の効力が生じることは覚えておいてください。
遺留分の支払い拒否の
リスクについて
遺留分は民法で定められ、保障されている権利ですから、相手から遺留分侵害額請求され、それが法的な要件を満たしているなら、遺留分を支払わなければいけません。
もし、請求を無視してそのままにしていたり、遺留分を支払わないと次のようなリスクが発生する可能性があります。
相手側から調停や訴訟を
起こされる
相手側は「遺留分侵害額請求調停」の申し立てを行なう可能性があります。
さらに、調停を無視する、あるいは調停が不成立となった場合、相手側は訴訟を提起する可能性があります。
これらが長引けば、家庭裁判所に出頭する必要もあり、時間的、金銭的、メンタル的にも歓迎できるものではないのは、おわかりいただけると思います。
財産が差し押さえられてしまう
遺留分侵害額請求をした人が、裁判所に「強制執行の申し立て」を行ない認められたなら、請求された人は法的に財産を差し押さえられてしまいます。
たとえば、裁判所からの債権差押命令が発令され、申し立て時に特定した金融機関(支店)にあるあなたの口座の預貯金が差し押さえられてしまう可能性があるわけです。
このように、請求を受けた側の注意点として、遺留分の支払いを拒否した場合のリスクを知っておくことは非常に重要なことになります。
遺留分は請求しなければ
受け取れない
もう1つ、遺留分を侵害された方が知っておくべき重要な事実があります。
じつは、とても重要なことなのですが、遺留分は権利のある相続人が請求することで発生することを知っておいてください。
遺留分は請求しなければ受け取れない、ということに注意する必要があります。
遺留分侵害額請求は
弁護士にご相談ください!
以前は仲のよかった家族、兄弟が、遺産相続が始まったことで仲違いを起こしてしまうケースは、じつは少なくありません。
関係が近いがために、家族間の相続問題は後を引きかねず、関係の修復が困難になってしまう場合があります。
こうした事情でお悩みの場合は、まずは一度、弁護士にご相談ください。
相続の問題は当事者同士では解決が難しく、さらに複雑化する場合も多いため、第三者である弁護士に解決を依頼するのは、もっとも確実な方法の1つです。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
もちろん、秘密厳守ですから安心してご相談ください。
遺留分でお困りの時は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡ください。