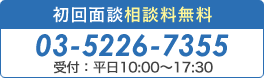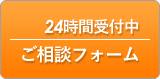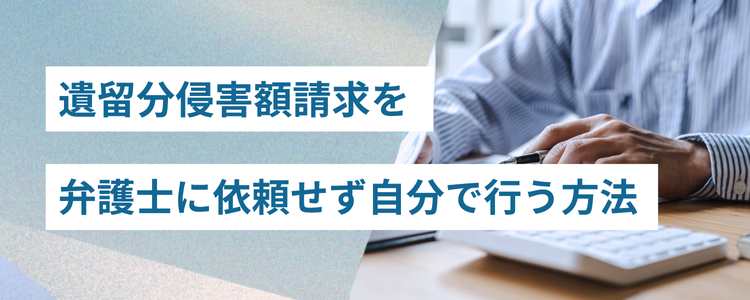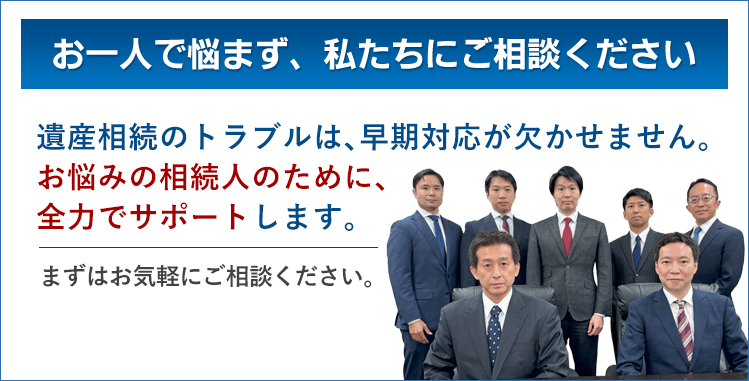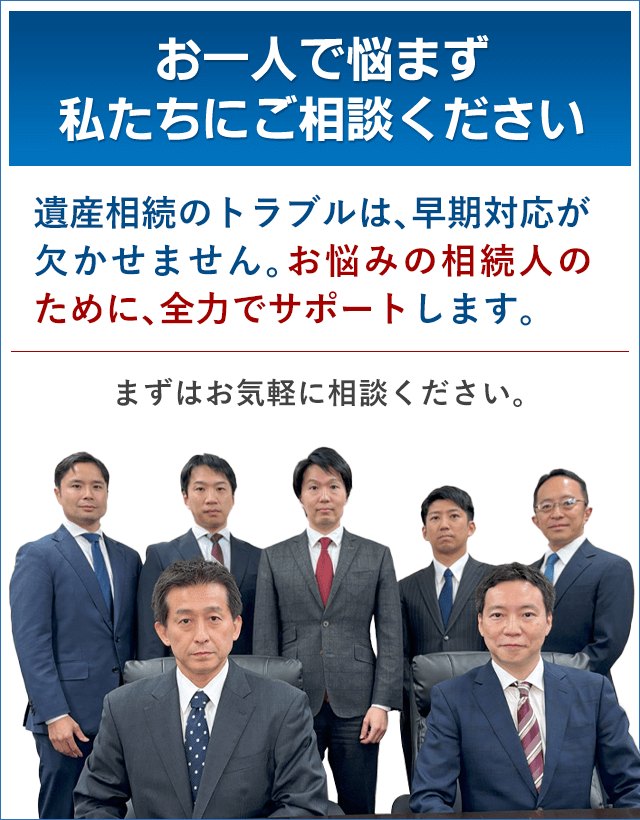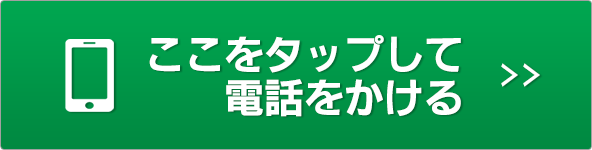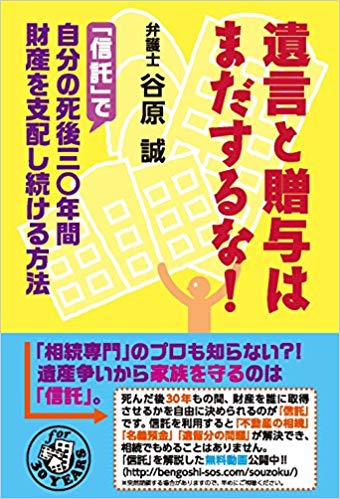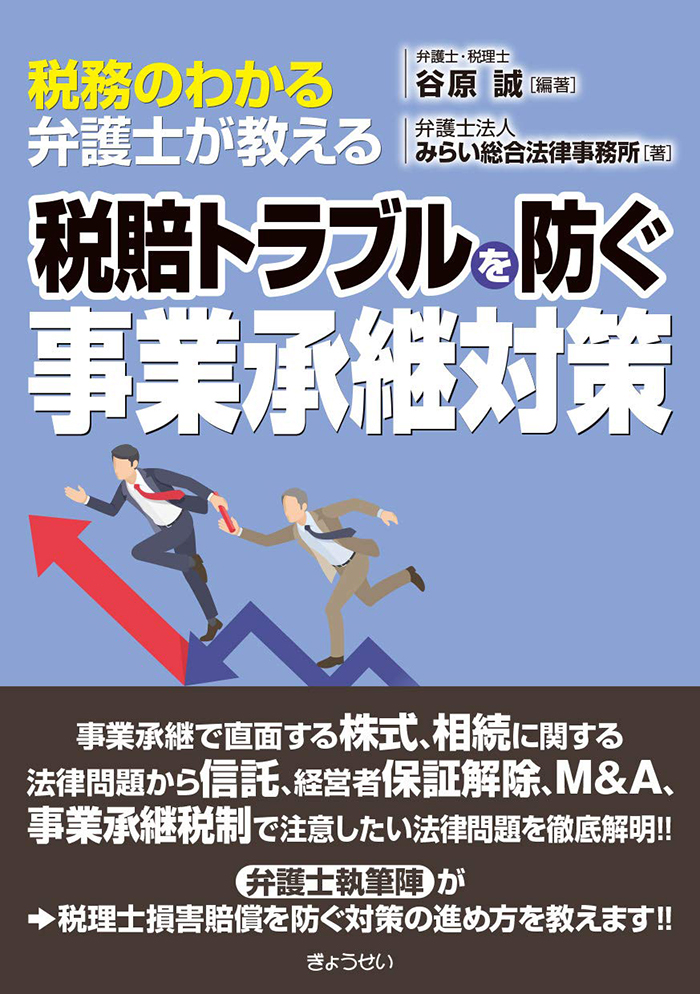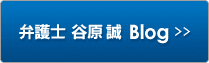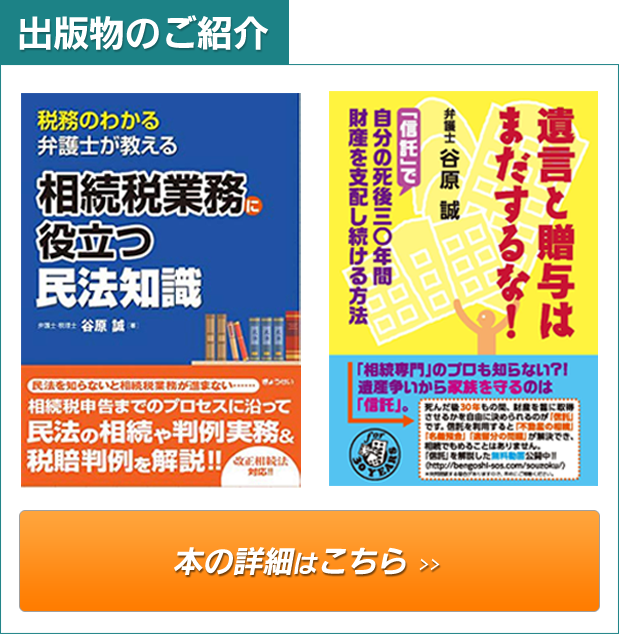遺留分侵害額請求を弁護士に依頼せず自分で行う方法
遺留分侵害額請求は、弁護士に依頼せずに自分で手続きを進めることも可能です。
遺留分侵害額請求をする場合、相続財産の内容を調べて遺留分を計算し、内容証明郵便で請求すれば、話し合いで解決できるケースもあります。
また、他の相続人から遺留分侵害額請求をされた場合も、話し合いにより解決することができるケースもあります。
ただし、手続きには法律知識や正確な計算が求められるため、リスクを理解した上で慎重に進めることが大切です。
ここでは、遺留分侵害請求を弁護士に依頼せず自分で行う方法や注意点などについて解説します。
目次
遺留分侵害額請求とは
相続財産は、被相続人と一定の関係を有する相続人が最低限の財産を分けられるように法律で一定の権利が保障されています。
その権利が「遺留分」で、遺留分侵害額請求はこの権利を行使するための手続きです。
まずは、遺留分侵害額請求が認められる相続人の範囲や計算方法について解説します。
侵害請求の権利が認められる
相続人の範囲
遺留分侵害額請求は、全ての相続人ができるわけではありません。
民法では、配偶者・直系卑属(子供)・直系尊属(父母など)にのみ遺留分の権利が認められています。
つまり、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で財産をもらえない場合でも請求することはできません。
例えば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、それぞれに遺留分があります。
もし遺言によって財産の全てが特定の一人の子供に渡されたとしても、配偶者や他の子供は自分の遺留分を主張して金銭で取り戻すことが可能ですが、兄弟姉妹は財産を受け取ることができません。
遺留分侵害額請求の対象になる
財産と計算方法
遺留分の対象になるのは、相続開始時点における遺産総額に贈与した財産を足したものから債務を差し引いた純資産です。
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合 |
|---|---|
| 配偶者と子供がいる場合 | 法定相続分の2分の1 |
| 配偶者のみ、または子供のみの場合 | 法定相続分の2分の1 |
| 直系尊属のみが 相続人の場合 | 法定相続分の3分の1 |
| 兄弟姉妹のみが 相続人の場合 | なし |
この割合を基に、侵害された金額を算出し、請求額を決定します。
ここには、被相続人が生前に行った贈与も一部含まれる場合があります。
例えば、生前に特定の子供へ多額の援助や不動産の贈与があった場合、それを遺産に戻して計算します。
正確な財産評価や割合を把握することが、請求をスムーズに進めるための重要なポイントです。
遺留分侵害額請求を
自分で行う場合の流れ
遺留分侵害額請求は、自分でも進めることも可能ですが、手順を理解しておかなければなりません。
トラブルを避けてスムーズに解決するためには、手順の流れを事前に把握しておくことが大切です。
遺留分侵害額請求を自分で行う場合の流れは、以下の通りになります。
遺留分の権利を確認する
遺留分侵害額請求を行う場合、まずは自分に遺留分を請求できる権利があるかどうかという点を確認します。
遺留分の権利があるのは、配偶者・子供・直系尊属(父母など)です。
兄弟姉妹には権利がありません。
また、相続人が複数いる場合には、それぞれの法定相続分を把握することが大切です。
遺留分侵害額請求を行う権利がある場合、遺言書の内容を確認して自分の取り分が侵害されているかどうかを整理します。
遺留分が明らかに減らされている場合、請求する正当な理由があることになります。
相続財産の内容を調査する
遺留分侵害額請求を行う前に、相続財産の把握も必要です。
預貯金、不動産、有価証券、保険金など、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を調べます。
また、生前に特定の相続人へ贈与していた財産も、遺留分の計算に影響するため確認しておきましょう。
相続財産の情報は、銀行・証券会社・法務局などで照会します。
戸籍や登記簿謄本などの公的書類を基に裏付けを取ることが大切です。
遺留分の金額を計算する
財産の調査を終えた後は、遺留分の金額を計算します。
計算の基本は、「相続財産の合計 + 一定の贈与財産 − 債務 × 遺留分割合」です。
遺留分割合に関しては、上項で記載した表を参考にしてください。
そして、この計算式で算出した金額が、他の相続人や受遺者に対して請求できる金銭的な権利になります。
財産の評価額を誤ると請求額が変わってしまうため、慎重に計算を行いましょう。
内容証明郵便を
他の相続人に送付する
請求額が確定したら、請求する相手に「遺留分侵害額請求を行う」旨を内容証明郵便で通知します。
この通知は、権利を正式に主張した証拠になり、また制限期間内に遺留分侵害額請求をしたことを証明する重要な手続きです。
内容証明郵便には、遺留分を請求する旨を明確に記載します。
送付後は相手方からの返事を待ち、今後の交渉方針を検討します。
話し合いで解決を目指す
内容証明を送った後は、相手と話し合いによる解決を目指すことが一般的です。
金額や支払い方法などを協議します。
協議で合意に至った場合は、トラブルを防ぐために示談書や合意書を作成しましょう。
交渉の際は感情的にならず、冷静に話を進めることが大切です。
解決しない場合は調停・訴訟へ
話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では第三者が間に入り、話し合いによる解決を促します。
調停でも解決しない場合は、訴訟へ移行し、裁判所が最終的な判断を下します。
裁判手続きは専門的で手間がかかるため、弁護士に依頼するケースが一般的といえます。
自分で遺留分侵害額請求を行う
場合のリスクと注意点
遺留分の侵害額は自分でも請求できますが、法律知識や実務経験がないとトラブルに発展する可能性があります。
自分で遺留分侵害額請求を行った場合のリスクや注意点について、知っておきましょう。
時効・除斥期間を過ぎると
請求できなくなる
遺留分侵害額請求には、法律で定められた時効があります。
「遺留分を侵害されたことを知った日から1年」または「相続開始から10年」を過ぎると、請求する権利が消滅します。
とくに遺言書の開封や遺産分割協議の時点で遺留分の侵害に気付くケースが多いため、その時点から1年がカウントされることが一般的です。
請求準備に時間がかかることもあるため、早めに内容証明を送るなど期限管理を意識して行動することが重要です。
証拠集めや裁判所の手続きは
手間と時間がかかる
自分で遺留分請求を進める場合、まずは相続財産の内容を証明する資料を集める必要があります。
預貯金の残高証明、不動産の登記簿、贈与の記録などを揃える作業は、関係機関とのやり取りも必要なので手間がかかります。
さらに、話し合いで解決しない場合は家庭裁判所への調停申立てを行いますが、申立書の作成や証拠の整理、主張の書面作成などは複雑です。
誤った記載や証拠の不足があると、請求が通らない可能性もあります。
時間と労力を考えると、途中から専門家のサポートを受ける選択も検討すべきでしょう。
遺留分の計算ミスで
トラブルになる可能性がある
遺留分の請求では、相続財産の正確な評価と計算を行わなければなりません。
預金や不動産の評価額に誤りがあれば、請求額が実際より多くなったり少なくなったりして、後のトラブルの原因になります。
また、被相続人が生前に行った贈与や特別受益の扱い方の誤りも、計算結果に影響します。
とくに不動産の時価評価や贈与時期の判定は難易度が高いため、専門家のサポートが必要になる場面です。
相手が誠実に対応してくれないケースもある
弁護士を代理人として立てない場合、軽く見られて相手が話し合いに応じないケースもあります。
また、話し合いになったとしても、感情的な対立に発展すれば、話し合いを進めることが難しくなるでしょう。
場合によっては家族関係の悪化につながる可能性もあります。
自分で進める場合は、冷静に事実と法的根拠を基に対応し、記録を残すことが重要です。
相手が誠実に対応しない時には、無理に交渉を続けず、調停や専門家への相談を検討しましょう。
調停や訴訟に発展した場合は
専門知識が必要になる
話し合いで解決できない場合、最終的には調停や訴訟へ進みます。
調停や訴訟では、法的主張の整理、証拠の提出、書面作成など専門的な知識が求められ、自力で対応することは難しくなります。
裁判では主張や証拠の出し方で結果が変わることもあるため、知識のない状態で対応することは不利になるリスクが高まります。
正当な権利を十分に主張できず、望む結果を得られないかもしれません。
そのため、調停や訴訟に移行する場合は、早めに弁護士への依頼を検討することを推奨します。
遺留分侵害額請求の費用の目安
自分で遺留分侵害額請求をする場合は費用を抑えられますが、弁護士に依頼すれば報酬や裁判費用が発生します。
自分で請求する場合と弁護士に依頼した場合の費用の目安を解説するので、請求方法を検討する参考にしてください。
自分で請求する場合の費用
自分で請求する場合、内容証明郵便の郵送代やコピー代などの実費だけで済むことが多いです。
例えば、内容証明郵便1通あたり数百円~千円程度、郵送手数料を含めても数千円以内で請求書を送ることが可能です。
ただし、相手が応じず調停や訴訟に発展した場合には、裁判所の印紙代や郵便代、交通費などが追加で必要になります。
そのため、開始当初は費用を抑えられていた場合でも、紛争が長引けば費用は予想以上にかかる点を知っておかなければなりません。
弁護士に依頼する場合の費用
弁護士に依頼する場合は、着手金や報酬金が発生します。
一般的には交渉の着手金が20~30万円程度、解決報酬として得られた金額の10~20%が報酬として加算されるケースが多いです。
ただし、難易度などにより増額することもあります。
必ず契約書を締結するようにしましょう。
また、調停や訴訟に進む場合は、難易度などにより、さらに追加の着手金や日当、裁判所に納める印紙代や交通費なども必要になります。
弁護士に依頼すれば費用はかかりますが、手続きの手間や計算ミス、交渉で不利になることを避けられるため、時間や精神的負担が軽減されます。
弁護士に遺留分侵害額請求を
依頼した場合のメリット
遺留分侵害額請求は自分で行うこともできますが、弁護士に依頼することで得られるメリットは大きいです。
弁護士に依頼した場合のメリットには、以下のようなことが挙げられます。
法律の専門知識に基づいて
正確に請求できる
弁護士に依頼する最大のメリットは、法律の専門知識を基に正確な請求ができる点です。
遺留分の金額を算出するには、財産評価や贈与の扱いなど複雑な法的判断が求められます。
弁護士であれば、過去の判例や実務の知識を踏まえ、適正な金額を請求することが可能です。
また、弁護士が代理人になることで、相手も請求を軽視しにくくなります。
弁護士が間に入ることで話し合いもスムーズに進みやすく、早期解決にもつながります。
時効や手続きのミスを防げる
弁護士に依頼すれば、時効や手続きのミスを防ぐことができます。
遺留分侵害額請求には「知った日から1年」「相続開始から10年」という期限が設けられており、期限を過ぎれば権利が消滅します。
さらに、内容証明郵便や調停申立書などの書類は、誤った形式で出すと無効になるリスクもあります。
弁護士はこれらの期限や書式を正確に管理し、ミスのない形で確実に手続きを進めます。
相手との交渉を
スムーズに進められる
弁護士が代理人として交渉に入ることで、相手との話し合いをスムーズに進められます。
感情的な対立になることを避け、冷静なやり取りが可能になるため、解決までの時間の短縮が期待できます。
自分で交渉すれば相手に軽く見られたり、話がこじれたりするケースも少なくありません。
弁護士が間に入ることで、相手も真剣に対応せざるを得ず、より現実的な解決案を引き出しやすくなるでしょう。
調停・訴訟になっても
安心して任せられる
弁護士に依頼していれば、調停や訴訟に発展しても安心して任せることができます。
家庭裁判所での調停や訴訟では、主張書面や証拠の提出、法的な議論の整理など高度な知識が必要です。
弁護士はこれらの手続きを代理して行い、依頼者の主張を代弁してくれます。
法廷でも不利にならないように主張を行い、より有利な和解や判決を導きやすくなります。
精神的な負担を軽減できる
弁護士に依頼すれば、複雑な手続きや相手との交渉を任せられるので、精神的な負担が大幅に軽減されます。
相続トラブルは感情的になりやすく、家族間での争いがストレスになるケースが多いです。
弁護士が代理人として手続きを進めてくれることで、依頼者は冷静に判断しながら解決を待つことができます。
専門家に任せる安心感は大きく、結果的に良好な人間関係を保ちながら問題を終結させることにもつながります。
まとめ
遺留分侵害額請求は自力でも行うことはでき、費用を抑えられるというメリットがあります。
しかし、時効や書類不備、計算ミス、交渉でのトラブルなど、リスクや注意すべき点も多いです。
一方で、弁護士に依頼すれば、法律の専門知識に基づいた正確な請求や、手続き上のミス防止、調停・訴訟対応まで任せられるため、安心して請求を進められます。
費用はかかりますが、手間や精神的な負担を減らせるため、早期から弁護士に相談するメリットは大きいと言えるでしょう。
ただし、弁護士にも得意・不得意があり、自分との相性もありますので、弁護士選びは慎重にするようにしましょう。