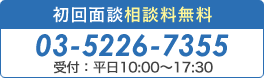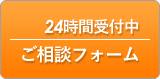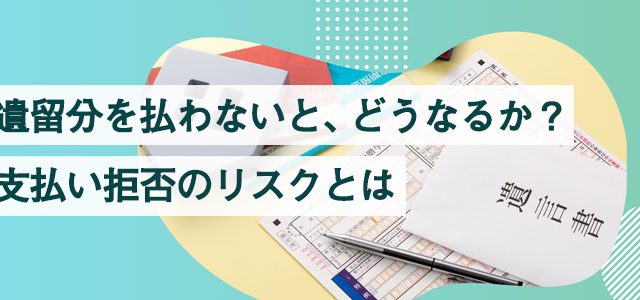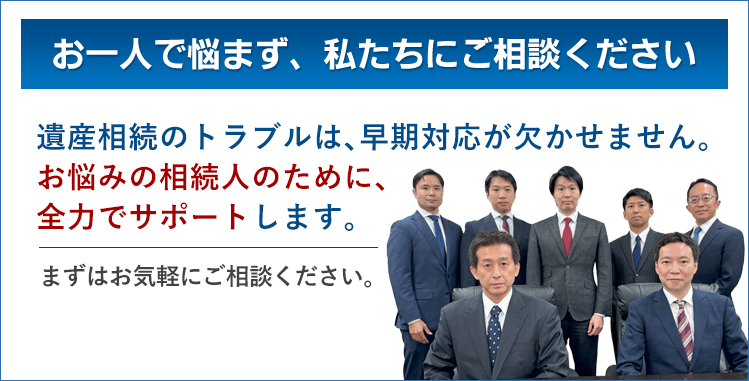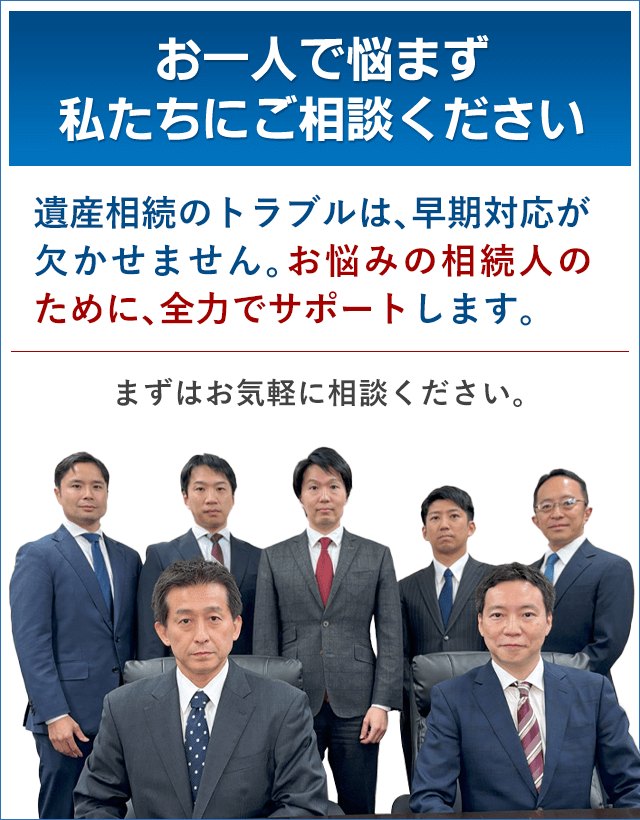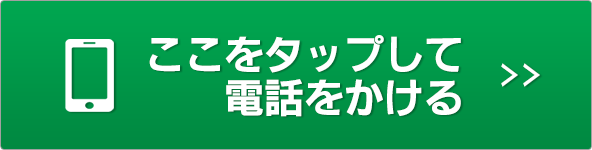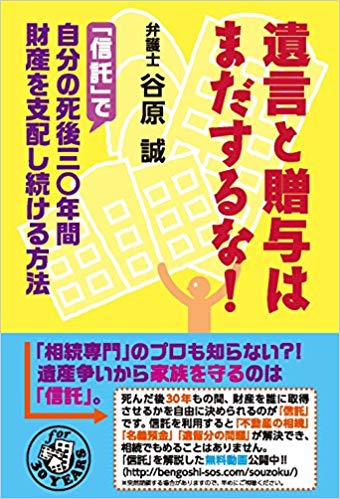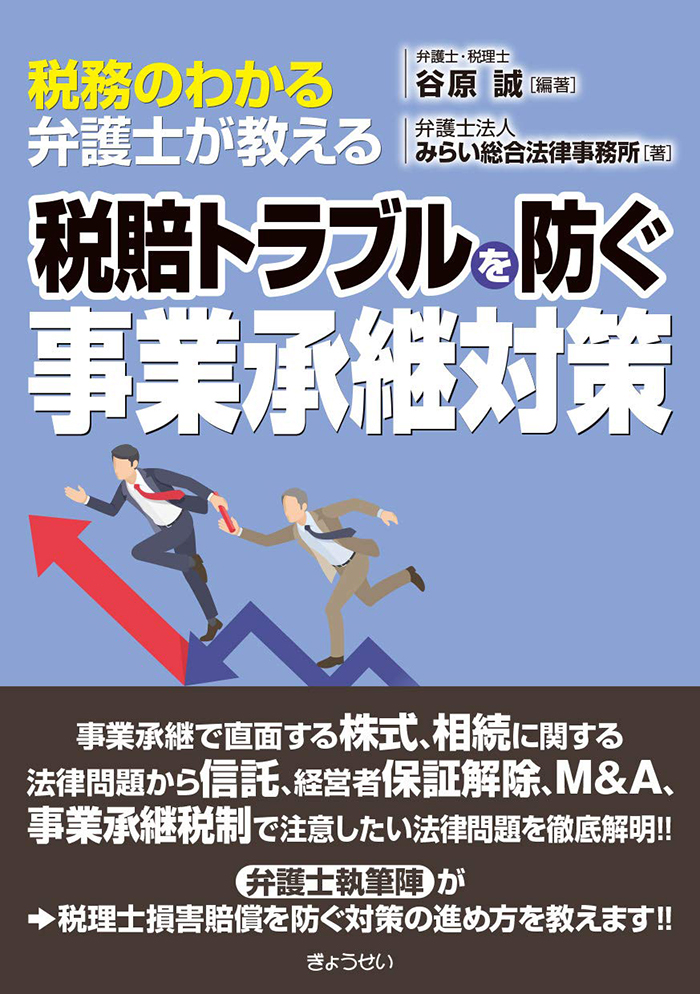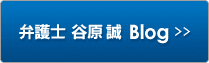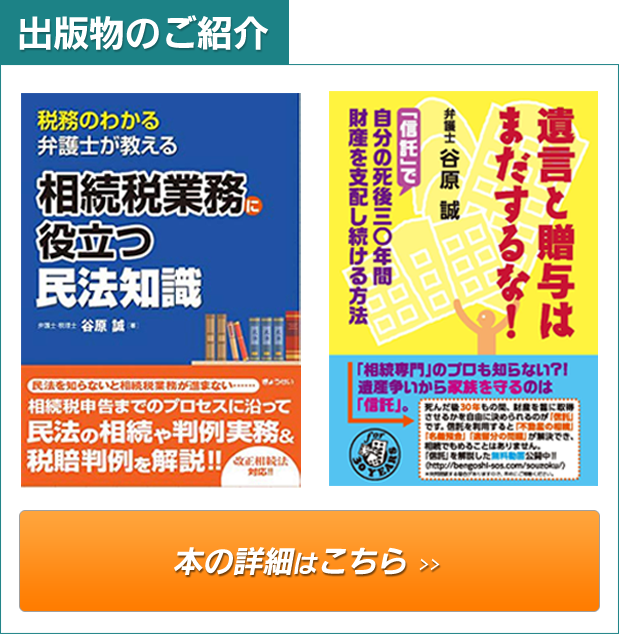死因贈与契約とは、どんな契約か?
ご自身(被相続人)の死後、財産を「誰に」「何を」「どれだけ」「どのように」相続したいか──。
預貯金や現金、土地や建物などの不動産、株式……
配偶者(夫・妻)、子供(長男・長女・次男・次女など)、孫、あるいはそれ以外の人……
人生の数だけ、ご自身の希望があり、家族や大切な人への思いがあると思いますが、法的には基本的に、財産は法定相続人(配偶者や子など)に引き継がれます。
では、法定相続人以外の人に財産を引き継がせたい時、どうすればいいのかというと、「死因贈与契約」というものがあります。
ちなみに、契約というのは複数当事者による意思の合致が必要です。
遺言は、遺言者の一方的意思表示により作成するものであり、契約ではありません。
そこで、遺言書以外で自分の死後、財産をどう処分する(引き継ぐ)かの方法として、メリットがある死因贈与契約を活用するという方法があるわけです。
そこで本記事では、死因贈与契約について、
- 死因贈与契約の具体的な内容
- 遺言による遺贈や生前贈与との違い
- 死因贈与契約のメリットとデメリット
- 死因贈与契約で注意するべきポイント
などについて解説していきます。
ぜひ最後まで読み進めて、死因贈与契約の知識を身につけ、有効に活用していただきたいと思います。
死因贈与契約について
知っておくと有利なポイント解説
- 1. 死因贈与契約は、生前のうちに
贈与者(財産を残す人)と
受贈者(受け取る人)が合意して
契約を締結するもので、
贈与者が亡くなったときに
効力を発揮する。 - 2. 受贈者が法定相続人でなくても
契約可能で、未成年者でも親権者の
同意があれば契約できる。 - 3. 原則として撤回することが可能。
- 4. 遺言による一方的な遺産譲渡ではなく契約であるため、希望する相手に確実に
財産を渡すことができるなどのメリットがある。 - 5.死因贈与契約を選択することで、
贈与者と受贈者の意思をより強く
反映できる
場合がある。 - 6. ただし、不動産に関する税金が
高くなってしまうなどのデメリットも
あるので
要注意。
死因贈与契約とは?
「贈与者」(財産をあげたいと考える人)と、「受贈者」(もらいたいと考える人)の合意に基づいて、無償で財産を譲渡する契約を「財産の贈与」といいます。
「死因贈与契約」というのは、贈与者の死亡によって贈与者の財産を無償で受贈者に与える契約ということになります。
そのため、死因贈与の効力は贈与者が亡くなった時点で発生し、財産の移転が行なわれます。
当事者が成人でなければ、契約などの法律行為を行なうことはできませんが、死因贈与契約の場合は親権者の同意を得られれば、受贈者が未成年者であっても契約が可能です。
贈与者は、いつでも死因贈与の全部または一部を撤回することができます(最高裁昭和57年4月30日判決、民集36巻4号763頁)。
ただし、負担付死因贈与契約で受贈者が負担の履行をした場合には撤回はできない、とした判例があります(最高裁昭和57年4月30日判決、民法百選Ⅲ第85)。
法定相続人ではない人(事実婚や同性のパートナーなど)に、自分の財産を遺したい場合は、死因贈与契約を結んでおくことで自分の死後、相手に財産を渡すことができます。
負担付死因贈与契約とは
負担付死因贈与契約とは、贈与者が亡くなった場合に財産を贈与する代わりに、受贈者に特定の義務や負担を課す契約です。
成立するため、贈与者の意思を確実に
実現できる可能性が高い。
② 死後の相続紛争を予防する効果が
期待できる。
などの特徴があります。
たとえば、贈与者が「私の介護を最後までしてくれたら、死後に自宅を譲る」、「自分の死後、ペットの世話をしてくれることを条件に、財産の一部を譲る」といった内容などが該当します。
遺言書による遺贈・生前贈与と死因贈与契約の違いは?
死因贈与に似たものに「遺贈」がありますが、前提となる条件が異なります。
「遺贈」というのは、贈与者が遺言によって受贈者(譲り受ける人)を指定し、遺産の一部またはすべてを渡す(贈与する)ことです。
たとえば法律上、相続では子が第一順位となり、その子(孫)は法定相続人にはなりません。
(子が亡くなっていなければ、代襲相続で孫が相続人になります)
そのため、被相続人が遺産の一部を孫に渡したい場合は、遺言書で孫への遺贈について定めることができます。
遺贈は単独行為であり一方的な意思表示なので、死因贈与のように贈与者と受贈者との間に契約関係はありません。
なぜなら、贈与者は自身の財産を誰に遺贈させるのかについて、遺言書で一方的に伝えることになるからです。
そのため、贈与者が亡くなった後、受贈者が遺言書を確認した時に初めて遺贈された事実を知るといったケースもあります。
遺贈は死因贈与のような契約ではないため、受贈者は遺贈された財産を放棄することができるという特徴もあります。
<遺言書による遺贈と死因贈与契約の違い
一覧>
| 遺贈 | 死因贈与 契約 | |
|---|---|---|
| 受贈者 (受け取る側)の 事前承諾 | 不要 | 必要 |
| 遺産の内容を 秘密に できるか? | 可能 | 不可能 |
| 権利の放棄はできるか? | 可能 (包括遺贈の場合は、相続を 知った時 から 3か月以内) | 書面による契約の 場合は 不可能 |
| 書式の指定 | 遺言書に 決められた 書式がある (満たさない 場合は無効) | 書式の指定なし |
| 未成年者 への 承継は できるか? | 可能 | 親権者の 同意が必要 |
| 家庭裁判所の検認 | 自筆証書 遺言、 秘密証書遺言の場合は必要 (法務局で 保管して いた 自筆証書 遺言・ 公正証書 遺言は不要) | 不要 |
| 不動産取得時の税金 (登録 免許税・ 不動産 取得税) | 相続人への遺贈 (相続):低い 相続人 以外への 遺贈:高い | 高い |
| 撤回の可否 | いつでも 撤回できる (新しい 遺言書を 作成すると 後の 遺言書が 優先する) | いつでも 撤回できる (ただし 負担付死因 贈与で 条件の大半 を履行して いた場合は 不可) |
遺言書による遺贈と死因贈与契約のどちらの方法を選択するかは、家族の状況や財産の種類などによって違ってくるので、よく検討する必要があります。
なお、「生前贈与」は贈与者が生きているうちに受贈者に財産を無償で渡す契約のため、贈与税の課税対象となりますが、死因贈与は相続税の課税対象になります。
死因贈与は「贈与」と名前がついていますが、死因贈与では贈与者の死亡によって効力が発生するからです。
税金については後ほど解説しますが、難しい部分があるため、弁護士や税理士に相談されることをおすすめします。
死因贈与のメリット
次に、贈与者と受贈者それぞれにとってのメリットについて見てみます。
贈与者のメリット
1.自分が希望する相手に確実に
財産を渡すことができる
死因贈与は、生前に贈与者と受贈者の間で契約を行なうため、贈与者が亡くなった後に受贈者はその財産を放棄することはできません。
そのため、確実に財産を渡すことができる仕組みだともいえます。
2.契約書に誤りがあっても
契約の履行ができる
法律上、贈与契約は口頭でもできるため、書面化は必須ではありません。
そのため、仮に書面の形式に間違いがあっても契約の履行ができます。
ただし、あとから法的なトラブルが起きないとは限らないので、基本的には「死因贈与契約書」を作成して契約を取り交わし、書面を保管しておくべきだといえます。
受贈者のメリット
1.負担付死因贈与なら
受贈者の権利を守ることができる
死因贈与では遺贈に関する規定が準用されるため、基本的にいつでも撤回することが可能です。
しかし、そうなると受贈者としては死因贈与契約を締結しても、履行されるかどうかわからない状態になってしまいます。
そこで、負担付死因贈与を活用することで受贈者の権利を守ることができます。
契約の条件となっている義務や負担が履行されていれば、負担の内容にもよりますが、負担付死因贈与では贈与者から一方的に撤回することができなくなるからです。
2.不動産を仮登記して
権利を保全しておくことができる
死因贈与契約では、贈与者と受贈者が贈与に合意している事実があるため、仮登記(始期付所有権移転仮登記)を行なうことができます。
仮登記によって、贈与者が死亡した時に所有権が受贈者に移るようにしておくことができるので、受贈者の権利の保全ができるのです。
死因贈与のデメリット
死因贈与契約にはメリットだけでなく、次のようなデメリットもあることを知っておいてください。
贈与者のデメリット
1.相続人の間で争いが起きる場合がある
死因贈与によって、相続人以外の人が財産を受け取ると、法定相続人との間で争いが起きやすいので注意が必要です。
2.負担付死因贈与契約は
撤回できないケースがある
負担付死因贈与契約の場合、たとえば贈与者の介護を行なう、ペットの世話をするなどの一定の負担事項について受贈者が実行した場合は、あとから契約を撤回できません。
受贈者のデメリット
1.不動産に関する税金が
高くなってしまう
相続の場合と比べて、死因贈与では不動産の登録免許税や不動産取得税が高くなってしまいます。
そのため、受贈者が法定相続人であれば相続をしたほうが税金は安くなります。
2.相続税がかかる場合がある
死因贈与契約では贈与税はかかりませんが、贈与者の財産の金額によっては相続税がかかる場合があります。
すると、評価額が大きい不動産を死因贈与したケースなどでは納税資金が足りなくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。
3.遺留分侵害額請求の対象になる
場合がある
民法で保証されている、遺言によっても侵害することができない相続人(配偶者や子など)の最低限の権利のことを「遺留分」といいます。
遺留分には遺族の生活を保障する目的があるため、たとえば亡くなった父親(被相続人)の遺言書に、「全財産は長男に相続させる」とか、「遺産のすべては再婚相手とその子供に相続させる」といった内容が記載されていても、他の相続人は遺留分を受け取ることができる仕組みになっています。
そのため、死因贈与契約の内容が法定相続人の遺留分を侵害した場合、受贈者は遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
受贈者と遺留分侵害額請求者で話し合いにより解決を図りますが、話がまとまらない場合は調停、訴訟へと発展する可能性もあります。
死因贈与契約に関わる
法律について
死因贈与は、贈与者の死亡後の財産を処分するという意味で遺言と同趣旨の法律行為であることから、遺贈に関する規定が準用されています(民法第554条)。
なお、相続税法では死因贈与は遺贈とみなされるため(相続税法第1条の3一)、相続税の納税が義務付けられています。
死因贈与と納税に関する注意点
不動産の登録免許税
不動産について、相続によって取得させる場合と死因贈与によって取得させる場合では、所有権移転登記にかかる登録免許税の税率が異なります。
- 相続によって取得させる場合の税率/1,000分の4(登録免許税法第9条、
別表第一の一(二)イ) - 死因贈与の場合の税率/1,000分の20(同ハ)
不動産取得税
不動産取得に関わる税金も、相続と贈与では次のような違いがあります。
- 相続(包括遺贈および被相続人から
相続人に対してなされた遺贈を含む)による取得の場合/課税されない - 死因贈与の場合/課税される
(地方税法第73条の7一)
【固定資産税3,000万円の住宅の場合】
| 相続 | 死因 贈与 | 遺贈 | |
|---|---|---|---|
| 不動産の登録 免許税 | 12万円(※) | 60万円 | 60万円 |
| 不動産 取得税 | 非課税 | 90万円 | 非課税 |
| 合計 | 12万円 | 150万円 | 60万円 |
※相続の場合の登録免許税は、免税措置で非課税となる場合もあります。
※令和7年11月時点。
贈与税
贈与によって財産を取得した時は、納税義務が発生します(国税通則法第15条2項5号)。
民法では、贈与は贈与契約の成立によって効力を生じます。
しかし、書面によらない贈与は、履行が終了するまで取り消し(撤回)ができる(民法第550条)ことから、「贈与により財産を取得した時」とは、書面によらない贈与の場合においては「贈与の履行の終った時」であるとされています(東京高裁昭和53年12月20日判決、税務訴訟資料103号800頁)。
なお、死因贈与契約の事例ではありませんが、書面によらない贈与に関する裁判例として次のものがあります。
「不動産を贈与する旨の公正証書を作成した場合に、公正証書は将来の不動産贈与を明らかにした文書にすぎないとして、書面によらない贈与であり、不動産の引き渡し、または所有権移転登記がなされた時に、その履行があったと判断した(名古屋高裁平成10年12月25日、租税百選第6版76)。」
死因贈与契約書について
死因贈与契約は、遺言ほど厳格なルールがないため、契約の当事者同士の合意があれば比較的簡単に契約を結ぶことができます。
前述したように、口約束でも成立するのですが、契約の内容や効力に関する後々のトラブル防止、回避のためには、やはり契約書をという形で書面に残しておくことが大切です。
ここでは、「不動産死因贈与契約書」のひな形をご用意しましたので参考にしてください。
・不動産死因贈与契約書のひな形はこちらから
死因贈与で注意すべきポイント
まとめ
契約書は公正証書にしておくと安心
前述したように、死因贈与契約は贈与者と受贈者の口頭での合意でも成立しますが、法的トラブルの防止や解決のためにも、「死因贈与契約書」を書面で作成して保管しておくべきです。
そしてさらに、死因贈与契約書を公正証書にしておくことをおすすめします。
不動産の仮登記や本登記手続きでは贈与者の承諾書や印鑑証明書の添付が不要になり、必要書類をそろえやすくなるので、手続きをスムーズに行なうことができるからです。
執行者を死因贈与契約書で
定めておく
贈与者が亡くなった後に死因贈与契約の内容を実行するため、財産の引き渡しなどを行なう人を執行者といいます。
たとえば、死因贈与によって不動産を譲り受けた場合、その不動産は本来なら相続財産になるはずのものだったと考えると、通常その登記の際には相続人全員と共同で名義変更の手続きが必要になります。
しかし、死因贈与契約書に執行者を定めておけば本登記の際、執行者と受贈者のみで手続きを進めることができるという利点があるのです。
なお、執行人は受贈者本人が務めることもできるため、受贈者を執行者とする契約を締結しておけば、受贈者だけで本登記の手続きができることを覚えておいてください。
配偶者居住権も
死因贈与契約書で設定できる
「配偶者居住権」というのは、夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者が亡くなった人が所有していた建物に亡くなるまで、または一定の期間、居住することができる権利です。
たとえば、被相続人の夫が亡くなり、配偶者である妻と3人の子供が相続人である場合で、遺産相続会議の結果、法定相続割合に従って実家の不動産を分割して相続するとなったケースで考えてみます。
その際、不動産を売却してその金額を分割するなら、妻はこの家に住めなくなってしまいます。
こうした状況に備えて、死因贈与契約書に配偶者居住権を設定する旨を明記しておくことで、死因贈与でも配偶者居住権を取得することができるのです。
なお、配偶者居住権が認められるには次のすべての条件を満たす必要があります。
② 相続開始時に亡くなった人が、
居住建物を配偶者以外の者と
共有していない
こと。
③ 遺産分割・遺贈・死因贈与・
家庭裁判所の審判によって
配偶者居住権を
取得したこと。
【参考資料】:配偶者居住権とは何ですか?(法務局)
要注意!死因贈与の効力が
生じない場合とは?
次のようなケースでは死因贈与の効力が生じず、相続を計画どおりに進められなくなる可能性があるため注意が必要です。
受贈者が先に
亡くなってしまった場合
死因贈与は遺贈の規定を準用することになっているため、遺言者の死亡より前に受遺者が死亡した時は、その効力は生じません(民法第994条)。
そのため、通常の贈与契約のように、受贈者が死亡した場合には受贈者の子などの相続人がその地位を引き継ぐことにならないのです。
贈与者が受贈者の相続人に財産を渡したいのであれば、あらためて受贈者の相続人と死因贈与契約を締結する必要があります。
贈与者が死因贈与の内容と
異なる遺言書を作成した場合
これも遺贈の規定に準ずるものですが、内容が被っている死因贈与と遺言書の両方がある場合、遺言書が死因贈与契約書よりも新しく書かれていたなら、死因贈与の効力は生じないと判断されてしまいます(民法第1023条)。
つまり日付が重要で、日付が新しいものが優先されるわけです。
そのため、逆に死因贈与契約書の日付のほうが遺言書より新しければ、そちらが優先されます。
死因贈与を考えているなら
弁護士に相談してください!
ここまで見てきたように、死因贈与は財産の渡し方の自由度が高い制度で、メリットのある方法です。
しかし、メリットとデメリットがあり、契約書作成においては法的に注意するべきポイントもあります。
それらを考え合わせたうえで、死因贈与で財産を確実に、渡したい人に残したいなら、まずは一度、弁護士にご相談ください。
弁護士法人みらい総合法律事務所は全国対応で、随時、無料相談を行なっています(事案によりますので、お問い合わせください)。
死因贈与でお困りの時は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡ください。