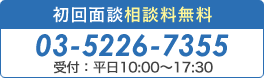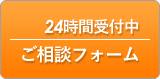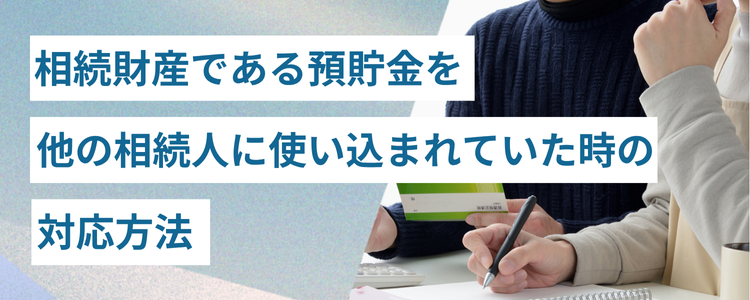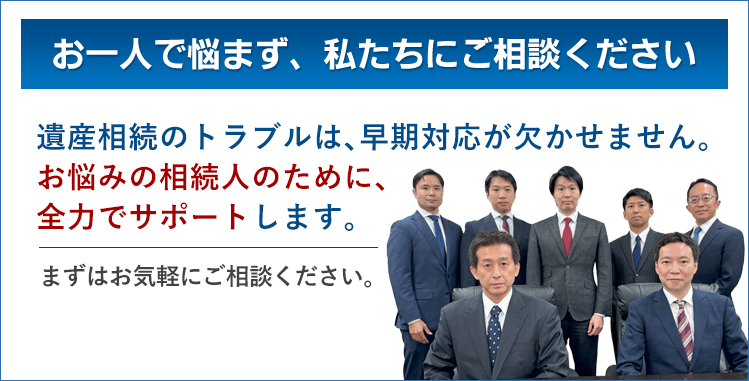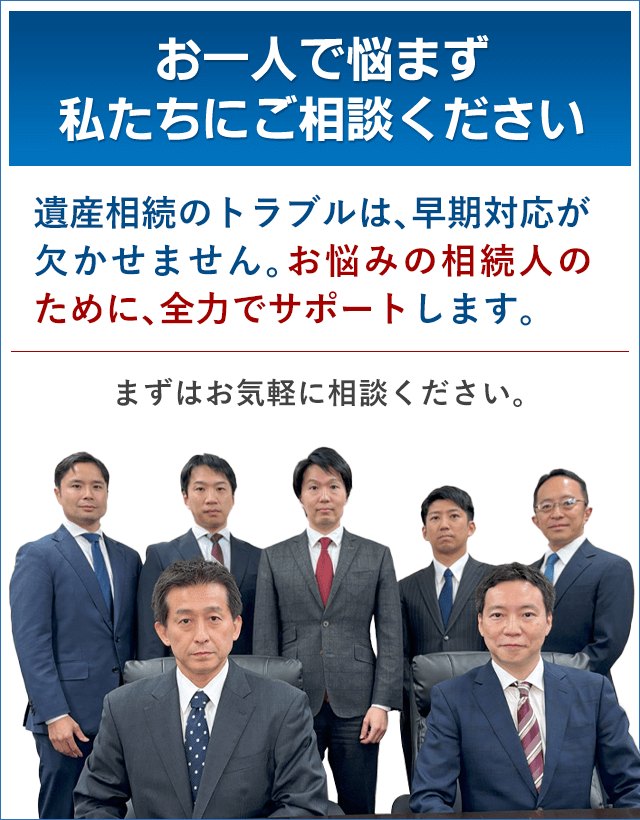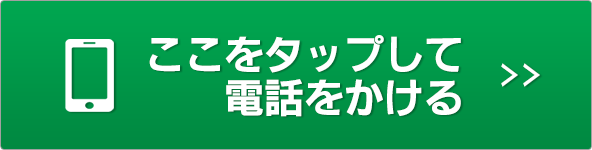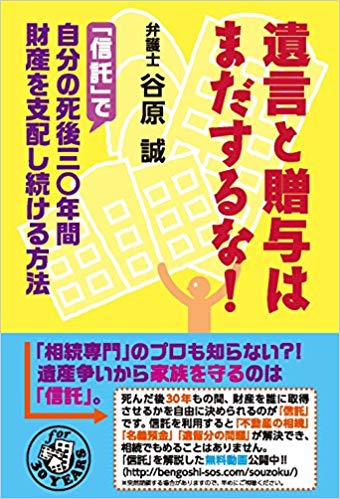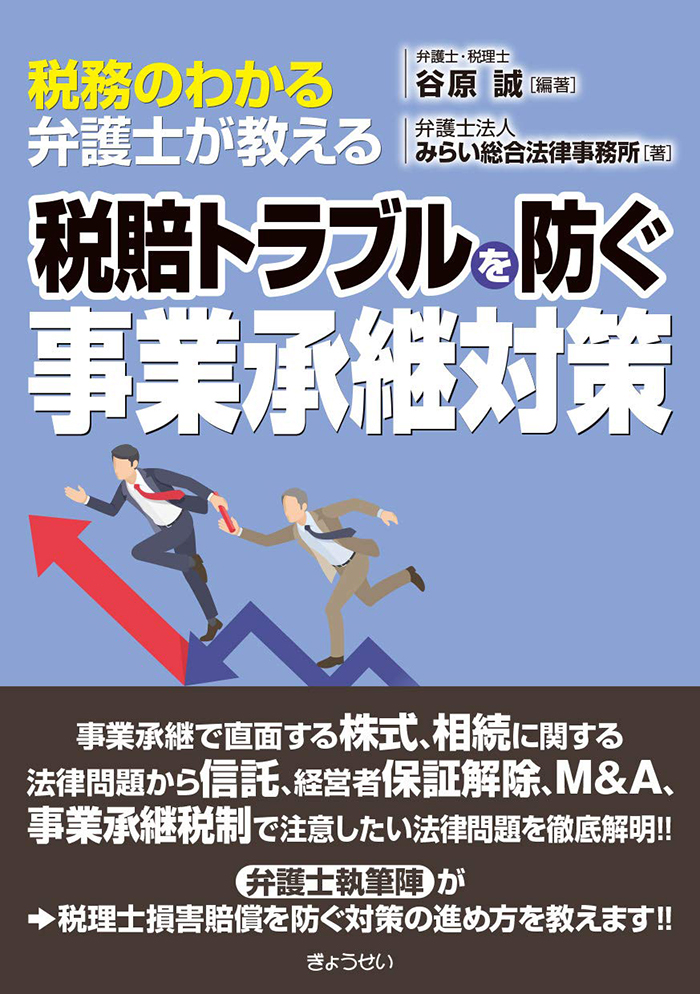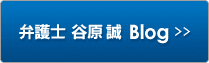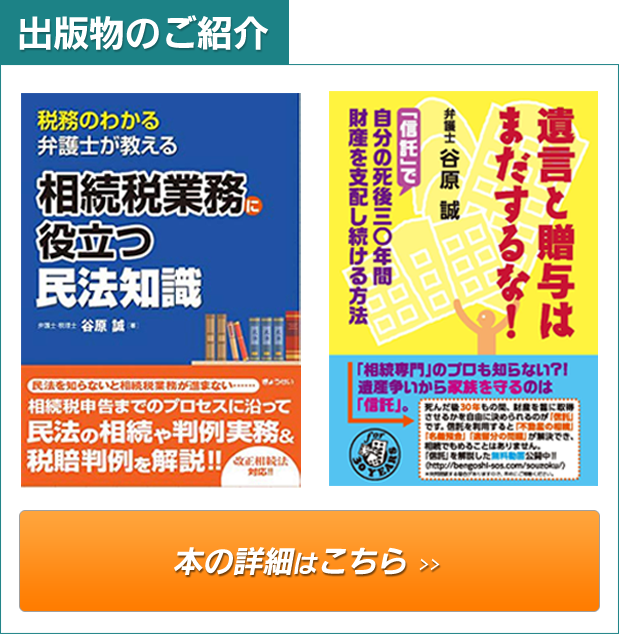相続財産である預貯金を他の相続人に使い込まれていた時の対応方法
親や配偶者などが亡くなって相続が発生した後に、「預貯金が勝手に引き出されていた」「気づいたら残高がほとんどなかった」などのトラブルに直面することもあるでしょう。
万が一、他の相続人によって相続財産である預貯金が使い込まれていた場合、法的な問題にも発展する可能性があります。
ここでは、相続財産の預貯金の使い込みが行われた場合の対応方法や、証拠の集め方などを具体的に解説します。
相続財産の預貯金の使い込みとは
被相続人が遺した相続財産には、現金や不動産だけでなく、銀行口座の預貯金も含まれます。
相続財産の預貯金が、他の相続人によって無断で引き出されていた場合、「使い込み」としてトラブルになる可能性があります。
まずは、相続財産に含まれる預貯金と使い込みの基本的な考え方について見ていきましょう。
使い込みに該当する行為とは
相続財産の「使い込み」とは、他の相続人に無断で被相続人の財産を自分のために処分・使用する行為を指します。
預貯金の引き出しや振込などが典型な例です。
相続が開始する前か後かによって、法的な扱いや問題点も異なります。
相続開始前の使い込み
相続が始まる前、つまり被相続人がまだ生存している間に相続財産が使い込まれることがあります。
例えば、キャッシュカードや通帳を預かった相続人が、本人の同意なく預金を引き出すケースなどです。
こうした場合、介護費や生活費のためという理由であったとしても、被相続人の意思に反していたり、金額が不相応であったりすれば、「不法行為」や「不当利得」に該当する可能性があります。
また、本人の認知能力が低下していた場合や、引き出しについての記録・同意が残っていない場合には、相続開始後に他の相続人から使い込みを疑われ、法的な請求や争いに発展することも考えられます。
相続開始後の使い込み
相続開始後は、すぐに金融機関が口座を凍結するとは限らないため、その間に相続人の一人が預貯金を引き出すケースもあります。
遺産分割が確定する前に預貯金を引き出せば、遺産を勝手に処分したものと判断されます。
こうした行為は、法律上「共同相続人の持分権を侵害する行為」とされ、他の相続人から返還請求の対象になることがあります。
とくに自分の法定相続分を超えて金銭を取得した場合や、遺産分割の協議が行われていない状態で引き出しが行われた場合、裁判でも不利になりやすいです。
引き出し行為が悪意あるものと判断されれば、損害賠償や利息付きでの返還を命じられるかもしれません。
その後の遺産分割協議にも大きな影響を与えるため、使い込みには注意が必要です。
使い込みが問題になる理由
相続財産の使い込みは、お金の問題だけではなく、法的な面や相続人同士の感情面で深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。
まず、法律上の問題としては、相続財産の使い込みは他の相続人の権利を侵害する行為であり、不当利得や不法行為に該当します。
場合によっては民事訴訟や刑事責任が問われる可能性があります。
そして、感情面の問題としては、「勝手にお金を使われた」という被害感情が生まれ、兄弟姉妹間など相続人同士の信頼が大きく損なわれる原因になりかねません。
他の相続人にとっては、本来受け取れるはずだった取り分が不当に減らされることになるため、不公平感や不満が強まるでしょう。
そうなると、遺産分割協議が円滑に進まなくなる原因になります。
使い込みが疑われる場合は早期に対応し、事実関係の確認と必要な対処を取ることが重要です。
使い込みが疑われる場合に
証拠を集める方法
相続財産の使い込みが疑われる場合、まずは「客観的な証拠」を確保することが重要です。
相手が使い込みを否定してきた場合でも、証拠があれば法的な対応が可能になります。
実際にどのような証拠を集めればよいのか、具体的な方法は以下の通りです。
通帳・入出金明細の取得
預貯金の使い込みの基本となる証拠は、通帳や入出金明細です。
通帳や入出金明細からは、誰が・いつ・どの口座から・どのような形でお金を引き出したのかを確認できます。
相続開始後であれば、相続人として金融機関に対し、被相続人の取引履歴を開示してもらうことが可能です。
この場合、死亡日から過去5年分程度の明細の開示が一般的です。
また、相続開始前の使い込みが疑われる場合も、金融機関の取引履歴は重要な証拠になります。
例えば、本人が入院していた、認知症で判断能力が低下していたなどの時期に、不審な引き出しがあれば、使い込みを裏付ける材料となるでしょう。
最高裁平成21年1月22日判決は、共同相続人の1人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるとしています。
メールやLINEなどによる
相手とのやり取り
他の相続人が使い込みをしている疑いがある場合、その人物とのやり取りも重要な証拠です。
LINEやメール、SNSのメッセージなどには、金銭のやり取りや預金の引き出しについての発言が残っていることがあります。
LINEのやり取りはスクリーンショットなどで全文を保存し、必要に応じてバックアップを取っておくことが望まれます。
発言の時期も証拠になるため、日時が分かる画面も保全しておきましょう。
また、口頭での会話の場合でも、相手が事実を認めた発言を録音しておけば、交渉や裁判において有効な証拠になります。
親の生活状況と
照らし合わせた分析
預貯金が引き出されていたとしても、「何に使われたのか」という点が明確にならなければ、使い込みの有無の判断が難しいといえます。
そこで、被相続人の生活状況と出金内容を照らし合わせることが、使い込みの判断に役立ちます。
例えば、高額な引き出しが頻繁に行われていたにも関わらず、生活費や介護費として妥当な支出が見当たらない場合、不自然な出金として使い込みを疑う根拠になります。
また、本人が入院中や施設入所中で実質的にお金を使っていない時期に、多額の出金があった場合も使い込みが疑われます。
施設費の領収書や、病院の診療明細、生活費の支出状況などの記録をまとめて保管しながら、引き出された用途が妥当かどうかを総合的に分析すると良いでしょう。
相続財産の預貯金が
使い込まれた場合の対応方法
相続財産の使い込みが明らかになった場合、すぐに法的手段に訴えるのではなく、まずは状況に応じた適切な対応を検討することが大切です。
円満な解決を図るためには、段階的に対応する必要があります。
ここからは、それぞれの方法と注意点について解説します。
相続人同士での話し合い
使い込みの疑いがある場合、まずは相続人同士で話し合いをすることが一般的です。
とくに、使い込みの用途が被相続人の介護費や生活費に充てられていたような場合、事情を確認すれば、納得できる説明を受けられることもあります。
この段階では、「いつ・いくら・何の目的で」引き出されたのか、そして「本人の同意があったのか」などの事実を具体的に聞き出すことが重要です。
証拠がある場合は、相手に証拠を見せながら丁寧に確認しましょう。
話し合いの内容は、メモや録音で記録を残しておくと、後から協議や法的手続きに役立ちます。
感情的にならず、冷静に話し合うことが大切です。
弁護士など第三者を交えることで、スムーズに進む場合もあります。
遺産分割協議で
使い込み分を調整する
相続財産の使い込みが発覚した場合でも、協議の中で調整することによって円満に解決できるケースもあります。
例えば、使い込んだ金額と用途が明確であれば、その分を差し引いて遺産分割を行う方法が一般的です。
そうすれば、他の相続人の取り分を調整できるため、公平になります。
遺産分割協議書の中でも使い込み分の調整があった旨を記載しておけば、後のトラブル予防にもつながります。
ただし、相手が使い込みの事実を認めない場合や、金額に争いがある場合には、調停などの公的な手続きを併用することも視野に入れましょう。
遺産があるものとみなす制度
被相続人の死亡の時には被相続人に属していたものの、相続開始後に処分されて存在しなくなった財産については、遺産分割の対象になりません。
しかし、民法では、次のような制度があります。
②もし、遺産分割前の遺産処分が共同相続人の1人または数人によって行われたときは、その者の同意は要しないで①の同意をすることができる(同条2項)
これらの同意がなされた場合は、遺産分割時に存在しなくても、その財産が存在するものとして遺産分割をすることになります。
調停・審判
話し合いで納得できる解決が得られない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」や「民事訴訟」などの法的手段を検討します。
遺産分割調停では、第三者である調停委員が間に入り、相続人同士の意見をまとめて合意を目指します。
調停でも解決しない場合は、審判へ移行する流れです。
民事訴訟
明らかに不正な使い込みがあり、返還を求める必要がある場合には、「不当利得返還請求」や「損害賠償請求」の民事訴訟を起こすことも可能です。
法的手段を選ぶ場合には、証拠の整理や法的知識が必要になるため、弁護士へ相談することを推奨します。
訴訟になれば時間と費用はかかりますが、最終的な結論を出すことができます。
使い込まれた相続財産の預貯金を
取り戻せないケース
相続財産の使い込みが疑われる場合でも、全てのケースで使いこまれた預貯金を取り戻せるとは限りません。
たとえ不審な出金があっても、法律上問題がないと判断されることや、証拠が不十分で請求が認められないこともあります。
実際に返還を求めることが難しい代表的なケースは、以下の通りです。
親の「贈与」と判断される場合
引き出されたお金が「被相続人(親)が自分の意思で贈与したもの」と判断される場合、使い込みではなく正当な処分とみなされ、返還を求めることは難しくなります。
例えば、被相続人が生前に自分の意思で指示している場合や、過去に同様の金銭のやり取りが継続的にあった場合などは、贈与として認められることがあります。
また、口頭のやり取りであっても、録音やメモによる意思表示の証拠が残っていれば、贈与の成立が認定される可能性が高まります。
贈与と判断されれば、相続財産として戻すことはできず、遺産分割の対象にもなりません。
但し、自分の遺留分を侵害する贈与がされていた場合は、遺留分侵害額請求権を行使することができます。
証拠が不十分で
立証できない場合
実際に使い込みがあったとしても、使い込みを裏付ける証拠が不十分な場合、返還を求める法的手続きは成立しません。
裁判では、誰が・いつ・いくら・どのように引き出したか、お金が何に使われたかという点まで、客観的な資料や証言で示す必要があります。
例えば、通帳の写しがない、金融機関の取引履歴を取得していない、本人との会話記録がないといった場合は、相手が「正当な支出だった」と主張すれば反証できません。
そのため、請求が認められないリスクが高まります。
証拠の確保は早い段階から行い、曖昧な記憶や感情だけでは法的主張として通用しないことを知っておきましょう。
すでに時効が成立している場合
損害賠償請求や不当利得返還請求には、「消滅時効」が法律で定められています。
消滅時効は、法律構成により異なりますが、たとえば、不法行為に基づく損害賠償請求権であれば、被相続人の財産が使い込まれたことを知った時から3年、または使い込みが行われてから20年です。
この期間が経過すれば、原則として請求権は時効により消滅します。
そのため、長期間放置していた場合や、死亡後に時間が経ってから問題に気付いた場合には、すでに時効が成立している可能性があるので注意が必要です。
ただし、時効が進行していた場合でも、返還の一部を認めた場合には、時効の更新が認められる場合もあります。
まずは、時効の起算点を確認し、専門家に相談することが重要です。
被相続人の生前行為として
法的に問題がない場合
引き出し行為が、被相続人自身の意思で行われた「正当な財産処分」は法的に問題がないと判断されます。
例えば、被相続人が自らATMで出金していたケースや、被相続人が代理人に頼んで支払いや贈与をしていたようなケースなどが挙げられます。
また、被相続人が高齢でも判断能力に問題がなく、自分の意思で財産を管理していた場合は、支出が合理的でないと感じたとしても、第三者が後から覆すことは困難です。
「被相続人の自由な財産処分」は、第三者からは使い込みに見えた場合でも、被相続人の意思を尊重するしかありません。
まとめ
相続財産の使い込みは、相続開始の前後を問わず、早期の対応が重要です。
不審な点に気付いた場合は、まずは証拠を集め、冷静に落ち着いて事実関係を整理しましょう。
当事者間だけでの話し合いが難しい場合や、不安な場合は、弁護士に任せることも可能です。
また、場合によって法的手段でも取り戻せないケースがあるため、慎重に判断しましょう。
少しでも不安や疑問がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
遺産相続でお困りの時は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡ください。