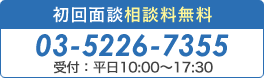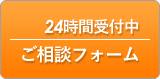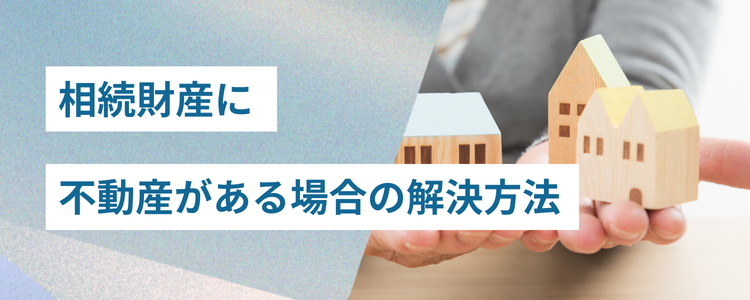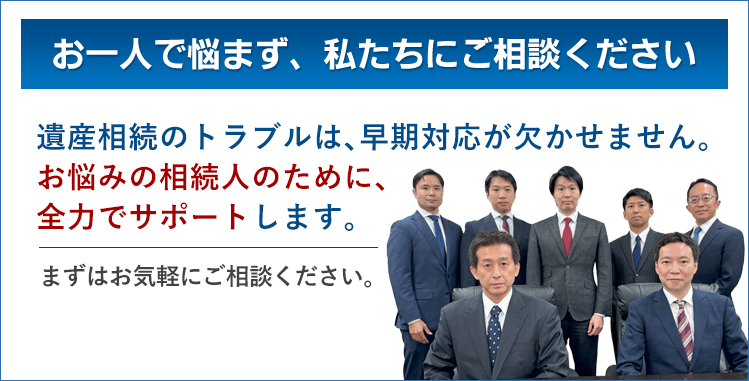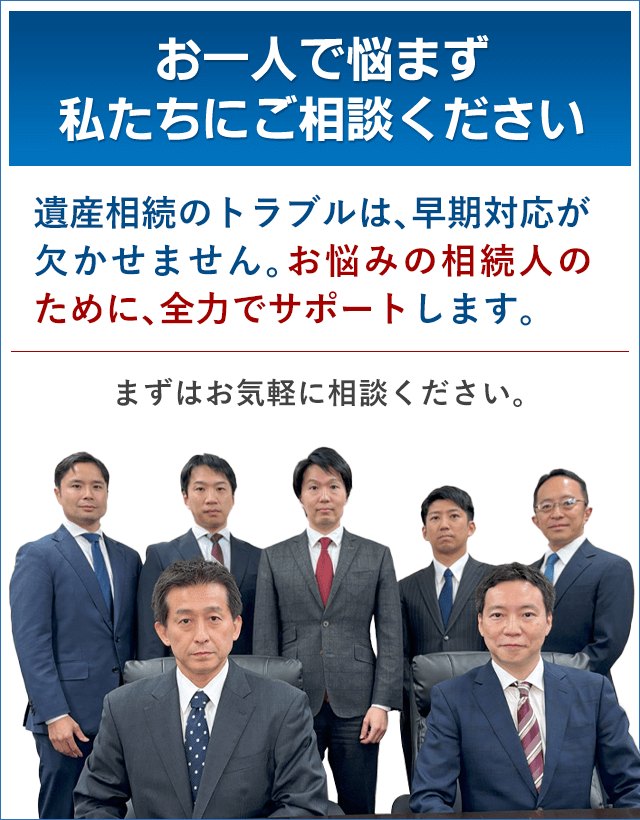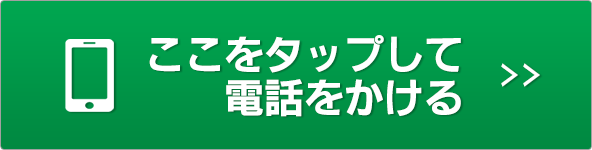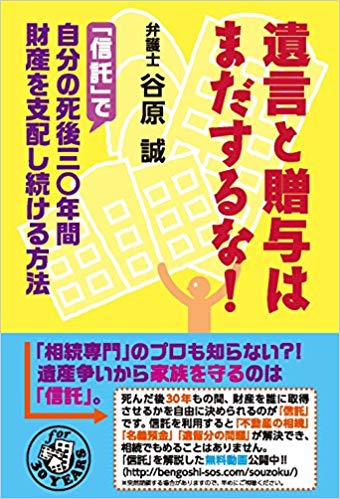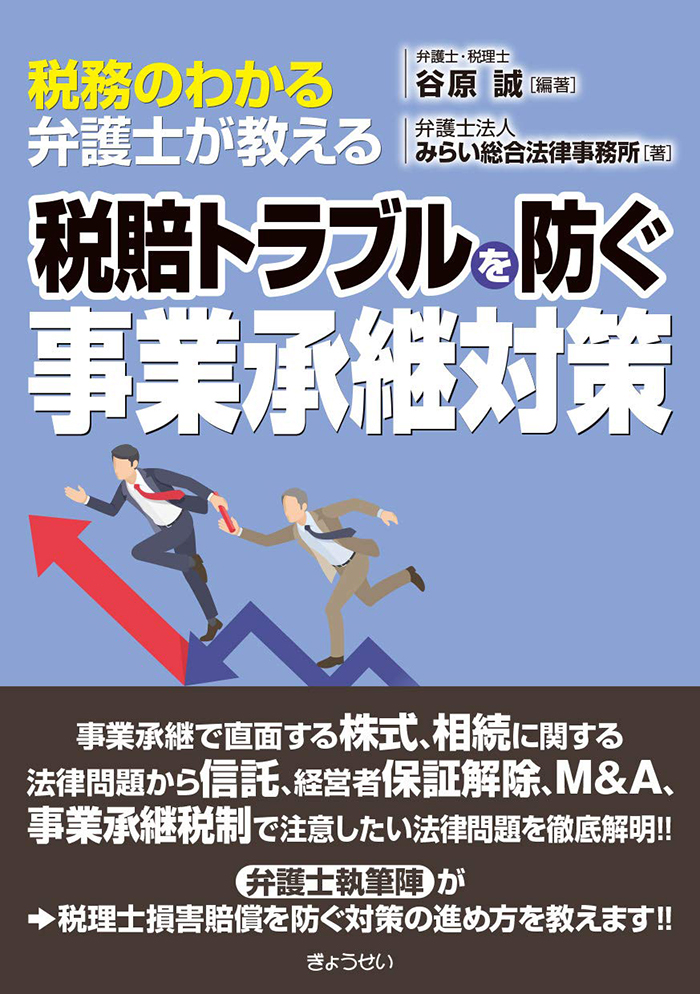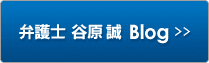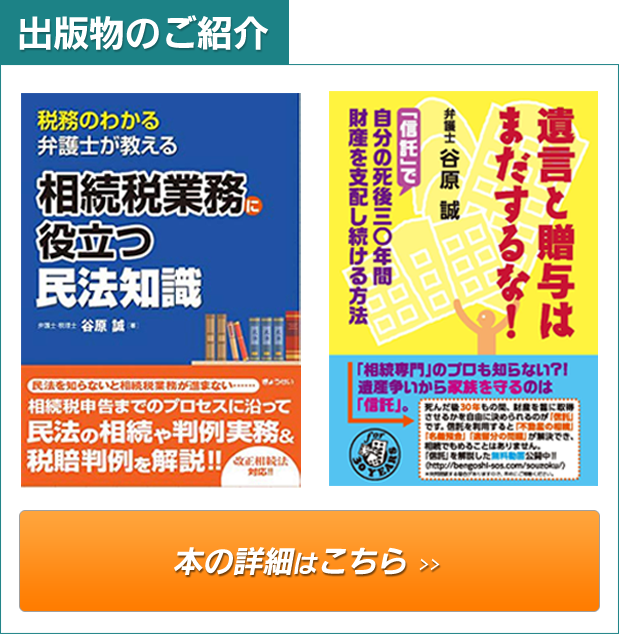相続財産に不動産がある場合の解決方法
相続で実家や土地などの不動産がある場合、被相続人の死亡によって法定相続人の共有となります。
この「不動産」は、売却や活用の判断が難しく、相続人同士のトラブルを招きやすい財産と言えます。
ここでは、相続の不動産を放置するリスク、円満に解決するための具体的な方法、生前にトラブルにならないようにするための方法も解説しています。
相続財産の不動産にお悩みの方は、参考にしてください。
目次
不動産が相続財産として発生する
仕組み
相続の際、家や土地などの不動産は現金のように分けられないため、法定相続人全員で共有することになります。
なぜ相続で不動産の共有状態が発生するのでしょうか?
まずは、不動産が発生する仕組みと、不動産がどのような状態を指すのか解説します。
相続で共有状態になる理由
不動産は、分割することが難しい財産です。
例えば、亡くなった被相続人の財産に家や土地があり、複数の相続人で相続する場合、それぞれの法定相続分に応じて不動産の権利を持つことになります。
この状態を共有と呼びます。
現金のように不動産は平等に分けにくいため、共有状態が生じるという仕組みです。
また、遺言書が存在せず遺産分割協議がまとまらない場合には、遺産分割が成立するまで共有のままになります。
遺産共有の状態とは?
遺産に不動産がある場合、複数の相続人がそれぞれ同じ不動産の持分(所有割合)を持つことになります。
この状態で相続登記をすると、登記簿上には、各相続人の名前と持分割合が記載されます。
例えば、相続人が2人いれば「1/2ずつ」と表記されます。
この場合、不動産全体を処分したり貸したりするには、相続人全員の同意が必要です。
また、日常的な清掃や修繕などの管理行為は、持分の過半数の同意で行えます。
ただし、大規模な修繕やリフォームなど大きな判断になる場合は、全員一致が原則です。
共有状態の不動産を放置する
リスク
共有名義の不動産をそのままにしておけば、さまざまな問題へ発展するリスクがあります。
「今は使っていないから」「兄弟仲が良いから大丈夫」などと油断していれば、後で売却や管理が難しくなって相続人同士の関係が悪化するかもしれません。
不動産を放置することで起きる主なリスクは、以下の通りです。
勝手に売却や活用ができない
不動産は、売却をする場合、相続人全員の同意が必要です。
一人でも反対する人がいれば、売却はできなくなります。
例えば、「古くなった実家を売って現金で分けたい」と考えても、他の相続人が「思い出のある家だから残したい」と反対すれば、その計画は実現できません。
相続人の意見が一致せずに空き家のまま放置されれば、老朽化や資産価値の低下を招く可能性があります。
共有状態では、自分の意思だけでは不動産を有効活用できないという点がデメリットになります。
固定資産税や維持費が
負担になる
不動産を所有していれば、毎年の固定資産税や修繕費、管理費などの負担が発生します。
これらの費用は持分割合に応じて負担するのが原則ですが、負担割合で揉めることもあるでしょう。
誰かが支払いを怠れば他の相続人が立て替えなければならず、トラブルの原因になる可能性があります。
さらに、固定資産税を滞納すれば延滞料が発生し、最悪の場合には差し押さえのリスクもあるため注意が必要です。
利用していない不動産であったとしても維持管理の義務は残るため、所有している限りは維持費がかかることを知っておかなければなりません。
相続人間でのトラブルに
なりやすい
不動産は、家族関係を悪化させやすい要因のひとつです。
「売りたい」「残したい」「貸したい」など不動産に対する意見の違いが対立を生み、感情的な争いに発展することがあります。
とくに相続人が多い場合、話し合いがまとまりにくく、問題が長期化する傾向があります。
関係が悪化すれば、弁護士や裁判所を介さなければ解決できない事態にもなりかねません。
家族の関係を守るためにも、不動産は早めの対応が必要です。
相続が重なれば
持分が細分化して複雑になる
不動産を放置したままさらに相続が発生すると、持分が次世代へと細分化されていきます。
そうすると、相続人の数が増えてしまい、誰がどのくらいの割合の権利を持っているのか把握が難しくなります。
一件の土地に10人以上の相続人が存在するというケースも珍しくありません。
相続人が増えるほど不動産に関する意思決定が複雑になり、売却や管理がますます難しくなります。
さらに、連絡が取れない相続人がいれば、裁判所を通した複雑な手続きが必要です。
こうした手続きは、解決までに多大な時間と費用がかかります。
不動産がある場合の解決方法
不動産は複数人で「一つの不動産を一緒に所有している状態」になるため、扱いが難しい相続財産です。
放置しても不動産の問題は解決することはなく、時間が経つほど複雑になるため、早期に対処することが大切です。
ここからは、不動産がある場合の代表的な解決方法を紹介します。
遺産分割をする
共有状態を解消するための方法が遺産分割です。
相続人それぞれが持つ持分を実際の不動産として分けたり、代金として清算したり方法です。
不動産を遺産分割する方法には、現物分割・換価分割・代償分割の3つがあります。
現物分割
現物分割とは、対象の不動産を区分けし、それぞれが単独で所有する方法です。
例えば、二世帯住宅を左右に分けたり、広い土地を相続人同士で分筆して所有したりする方法が挙げられます。
現物分割は、各自が独立して利用できる方法と言えるでしょう。
ただし、建物や土地の形状によっては公平な分け方が難しく、分筆登記や測量などのコストも発生するケースもあります。
換価分割
換価分割は、不動産を売却し、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。
「誰も住まない」「使い道がない」場合に有効で、最もスムーズに不動産を清算できる手段といえます。
売却により不動産の管理義務もなくなるため、維持費の負担を解消できる点もメリットです。
ただし、市場価格やタイミングによって得られる金額が変動するため注意が必要です。
代償分割
代償分割は、不動産を一人の相続人が取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。
例えば、長男が実家を相続し、他の兄弟に持分相当の現金を支払う方法になります。
「実家を残したい」「親の介護を担ってきた人に住み続けてもらいたい」など相続人の誰かが不動産へ住む場合に選ばれることが多いです。
ただし、代償金を用意する資金力が必要なため、事前に資金計画を立ておかなければなりません。
他の相続人の同意を得て
不動産を売却する
相続人全員の同意が得られれば、不動産全体を売却して代金を分配することが可能です。
ただし、相続人全員の協力が前提になるため、信頼関係があるうちに話し合いを進めることが大切です。
この方法は、換価分割と同様に現金で公平に分けることができることや、管理や維持の負担を解消できるというメリットがあります。
しかし、売却価格や仲介業者の選定を巡って意見が分かれることもあるため、慎重に話し合いを進めましょう。
家庭裁判所に遺産分割の
調停・審判を申し立てる
話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて解決を目指します。
調停では、調停委員が間に入り、公平な立場から双方が合意できるようにサポートします。
それでも合意に至らない場合には、裁判官が審判として分割方法を決定します。
時間や費用はかかりますが、法的効力があるため、長期的なトラブルを避けられることが利点です。
相続人同士で感情的な対立が生じている場合や、連絡が取れない相続人がいる場合などには有効な手段といえます。
不動産の売却・買取を進める際のポイント
遺産分割前に遺産である不動産を売却・買取する際は、相続人の合意や手続きの進め方、税金など注意すべき点が多くあります。
スムーズに進めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。
相続人全員の
同意を得ることから始める
不動産全体を売却する場合には、相続人全員の同意が必要です。
一人でも反対すれば売却は進められないため、まずは全員で現状を共有し、売却の目的や条件について話し合うことから始めましょう。
また、合意が取れたら「窓口になって進める人」や「売却代金の分配方法」などを明確に決め、トラブルになることを予防します。
家族間での感情的なすれ違いを避けるためにも、弁護士など第三者を交えて冷静に進めるという方法もあります。
売却時にかかる税金・手数料を把握しておく
不動産を売却する際には、譲渡所得税や住民税などの税金が発生します。
売却益(売却価格-取得費・譲渡費用)に課税されるため、相続した不動産の取得時期や評価額を把握しておく必要があります。
また、不動産会社に仲介を依頼する場合には仲介手数料、登記変更の際には登録免許税や司法書士報酬などの費用もかかります。
相続人間で費用負担を決めておかなければ、後から支払いでトラブルになる可能性があります。
事前に税理士や不動産会社へ相談し、想定される税金・手数料を見積もっておくと安心です。
トラブルがある場合は
弁護士に相談する
相続人の中に売却へ反対する人がいる場合や、相続人間での意見の食い違いが大きい場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士は、遺産分割の交渉代理や、調停・審判の申し立てなど、法的な手続きをスムーズに進めるサポートが可能です。
また、契約書の確認や、買取業者とのトラブル防止にも有効です。
「自分の持分をどう処分すべきか」「他の相続人が話し合いに応じてくれない」などの悩みを抱えたまま放置すれば、解決までの時間が長引く可能性があります。
専門家に相談することで、感情的な対立を避けつつ、最適な解決策を見つけやすくなります。
不動産の相続トラブルを
防ぐための事前対策
不動産は、相続時にトラブルの原因となることが少なくありません。
事前に適切な対策を講じておくことで相続人同士の争いを防ぎ、円滑に財産を分けることが可能です。
ここからは、事前に取り組める不動産の相続対策を紹介します。
遺言書で共有状態になることを防ぐ
遺言書を作成しておくことで、相続人間で共有状態になることを避けられます。
例えば、特定の相続人に不動産を単独で相続させる内容を遺言書に記しておけば、共有によるトラブルを未然に防げます。
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言など複数の形式がありますが、公正証書遺言は紛失や無効のリスクを抑えられる点で安心です。
事前に弁護士へ相談し、法的効力を確認して作成することが重要です。
生前贈与や
遺産分割協議などにおける工夫
生前贈与を活用し、相続開始前に不動産を処分しておく方法もあります。
例えば、親が生前に子供の一人に土地や建物を贈与しておくことで、将来的な共有状態を回避できます。
また、遺産分割協議においても、早めに話し合いを始め、分配方法や管理方法を具体的に決めておくことが大切です。
遺産分割協議書を作成して合意内容を文書化しておけば、後からの争いを避けやすくなります。
生前からも弁護士に相談できる
不動産の相続トラブルは、相続開始後だけでなく生前からの対策によって防ぐことができます。
弁護士に相談すれば、遺言書の作成や生前贈与の進め方、相続税や不動産の評価に関する注意点など、法的な観点から最適なアドバイスを受けられます。
また、家族間で意見がまとまらない場合や、複雑な共有関係がある場合も、弁護士が間に入ることで、感情的な対立を避けやすくなります。
早めに弁護士へ相談することで、相続開始後の手続きやトラブル対応の負担を軽減でき、安心して不動産の管理・分配を進めることが可能です。
まとめ
相続財産に不動産がある場合、放置するとトラブルになりやすいです。
不動産の解決策として、遺産分割や売却、生前贈与、遺言書作成などがあり、事前の話し合いや計画が重要です。
とくに相続人間で意見がまとまらない場合や、複雑な不動産がある場合は、早めに弁護士に相談することで法的に安全かつ円滑な解決が可能です。
迷ったら専門家の力を借り、安心して相続対策を進めましょう。
遺産相続でお困りの時は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡ください。