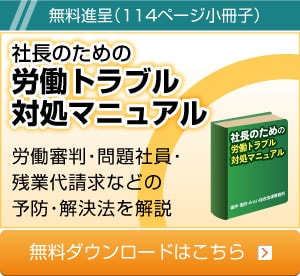この記事では、以下の内容について解説しています。
- 「武富士事件」(最高裁判所 平成23年2月18日判決)
- 「二重課税事件」 (最高裁判所 平成22年7月6日付判決)
- 最後に
「武富士事件」(最高裁判所 平成23年2月18日判決)
それでは、近時、税務当局側が敗訴し、大きな社会的耳目を集めた税務訴訟の事例を紹介します。
いわゆる「武富士事件」(最高裁判所 平成23年2月18日判決)
事案の概要は、消費者金融最大手の㈱武富士の元専務(創業者の長男)が、香港に赴任中、両親から約1600億円の海外資産(オランダの会社の持分)の贈与を受けたことについて、贈与税の納税義務を負わないと考え、これを納付しませんでした。
これに対し、国税東京が申告漏れを指摘し、一旦、約1330億円を追徴課税し、長男は一旦約1330億円を納付しました。
しかし、最終的に、長男は、訴訟により約2000億円(一旦収めた約1330億円の利子も含めて)を取り戻すことができました。
なぜ、税務当局と納税者の見解の相違によりこれほどの納税額の差が生じ、また、最高裁判所が納税者(長男)の言い分を認めたのでしょうか。
一般に、贈与を受けた者は、贈与税の支払義務を負います。
しかし、上記贈与が行われた平成11年12月27日当時の法律では、贈与税が課税されるためには、①贈与を受ける財産か、②贈与を受ける者の所在のどちらかが国内でなければなりませんでした。
つまり、①財産も、②贈与を受ける者の所在がいずれも海外の場合には、贈与税が課税されないのです。
本事案では、①財産が海外にあることは明らかなので、②贈与を受ける者、すなわち長男が贈与を受けた時点で海外に所在しているのか、国内に所在しているかについて、双方に見解の相違があり、争いとなりました。
最終的に、最高裁判所は、長男が贈与を受けた時点では国内に住所を有していないと判断し、贈与税の納税義務はないと判断しました。
その根拠は、主に、Ⅰ長男が香港に赴任を開始(平成9年6月29日に出国)してから約2年半後に贈与を受けていること、Ⅱ住民登録について香港へ転出の届出をしていたこと、Ⅲ通算約3年半にわたる香港滞在期間中の3分の2を香港の居宅に滞在していたこと、Ⅳ香港で現地法人の業務に従事していた等です。
この点、税務当局側は、長男側が贈与税回避を可能にする状況を整えるために上記のような滞在日数の調整を行ったに過ぎないのであるから、贈与税の納税義務を負うと争いました。
しかし、最高裁判所は、住所については、「客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当」として、上記Ⅰ~Ⅳの事情に基づき、長男は香港の居宅に生活の本拠たる実体を具備していたと認定し、贈与税を課税する要件を満たしていないと判断しました。
主観的に贈与税回避の目的があったとしても、客観的な生活の実体が消滅するものではないと考えています。
その上で、上記長男の様な方法で贈与税の回避を容認するのが適当でないというのであれば、立法によって対処すべきとしました。
これにより、長男は、約2000億円の還付を受けることができました。
「二重課税事件」 (最高裁判所 平成22年7月6日付判決)
続いて、年金払い型の生命保険に対し、相続税と所得税の両方を課すのは違法な二重課税になると判断した事例を紹介します。
この事案では、長崎市の主婦が、平成14年に夫が死亡したことにより、死亡保険金の一時金4000万円に加え、10年間にわたって総額2300万円を年金で受け取れる権利(年金受給権)を取得し、1年目分の230万円を受取りました。
この死亡保険金のうち、一時金で受け取るもの(4000万円)は、相続税の課税対象とされ、所得税は課税されません。
したがって、この4000万円については二重課税の問題は生じません。
一方で、年金で受け取る2300万円の部分について、税務当局は、1380万円(相続税法24条1項1号による60%)について相続税の課税対象とし、更に毎年受給する230万円についても雑所得の収入金額として所得税も課しました。
この税務当局の課税処分に対し、最高裁判所は、1年目の230万円の年金について課された所得税について、違法な二重課税と判断しました。
税務当局の見解は、年金受給権と毎年支払われる保険金は法的に異なる財産であるから、相続税と所得税の双方が課税可能というものです。
しかし、最高裁判所は、1年目の年金230万円は、全額が元本で運用益がないため、所得税は課税できないと判断しました。
すなわち、まず、所得税法9条1項15号は、相続等により取得する財産は所得税を課さないと定めています。
この相続等により取得する財産の意味について、最高裁判所は、「当該財産の取得の時における価格に相当する経済的価値」であり、相続税の課税対象となるものであるから、所得税法9条1項15号の趣旨は、相続税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして、同一の経済的価値に対する相続税と所得税との二重課税を排除したものと解しています。
次に、相続税法3条1項1号は、被相続人の死亡により相続人が生命保険契約の保険金を取得した場合には、この相続人が、この保険金の一定割合の部分を相続により取得したものとみなす旨を定めます(いわゆる「みなし相続」といわれます)。
この保険金には、年金の方法により支払を受けるものも含まれます。
そして、最高裁判所は、本件のように、年金を受け取る権利を相続により取得するとみなされる場合には、個々の年金の支給額について、被相続人死亡時の現在価値(=将来にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人死亡時の現在価値に引き直したもの)とそうでない部分(運用益に該当するもの)に分けて考えました。
その上で、現在価値の部分については、上記所得税法9条1項15号により課税対象とならないとしました。
このような考えに立った上で、最高裁判所は、毎年受取る230万円のうち、妻が受取った第1回目のものは、夫の死亡日が支給日であり、支給額と現在価値とが一致する(運用価値がない)ことから、所得税を課すことは許されないと判断しました。
この最高裁判決の影響は大きく、生命保険を年金払いの方法により受取った遺族は、毎年受取る年金額のうち、二重課税された部分(=運用益以外の部分)の金額については所得税の還付請求ができることになります。
その方法は、所得税の確定申告を済ませている納税者については更正の請求を、確定申告を済ませていない納税者は過去5年間にわたって確定申告することにより還付可能となります。
このように、身近な問題でも、税務訴訟により還付を受けるきっかけが存在するのです。
最後に
以上の青色申告の取消の事例や、近時の最高裁判例をみても、税金に関しては、納税者と当局との間に見解の相違が生じ、最終的には、最終的な判断権者である裁判所が、納税者の勝訴を言い渡すことがあります。
これにより、一旦収めた税が、利息を含めて還付されることがあります。
国民が納税の義務を負うことは憲法30条で定められていますが、同様に憲法84条は納税に厳格な条件を要求しており、税務当局がこれに違反していれば納税者勝訴の判決が言い渡されます。
当局の判断が誤っているということも、現に生じているのです。
したがって、税務当局との間に見解の相違が生じる場合には、税務当局の処分が正しいものかどうか、改めて検証する必要があるでしょう。