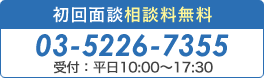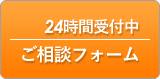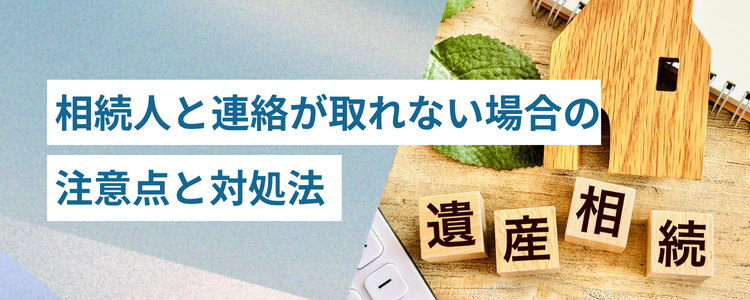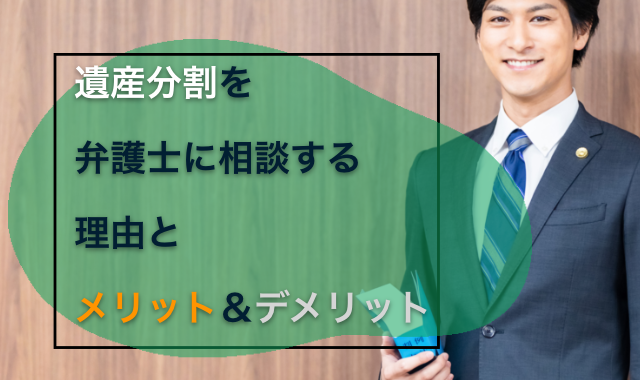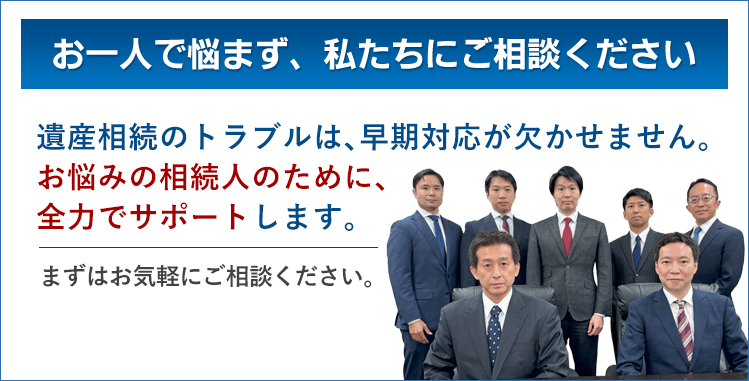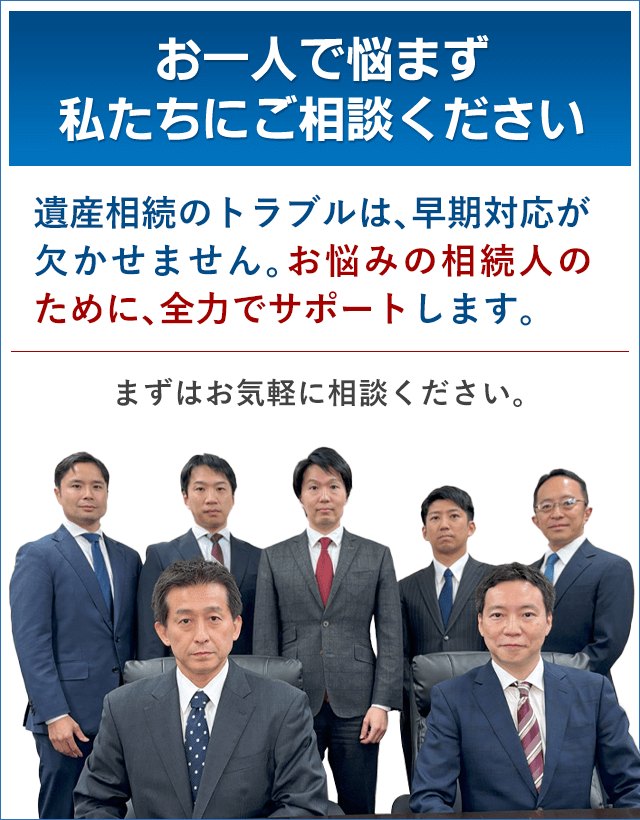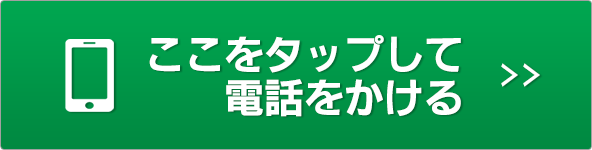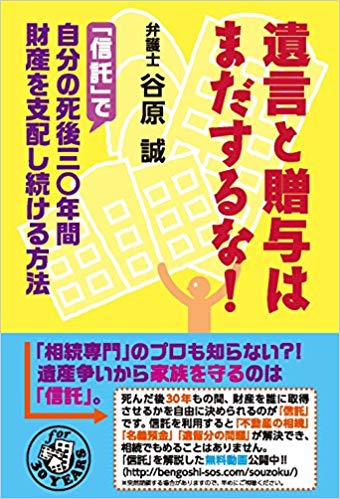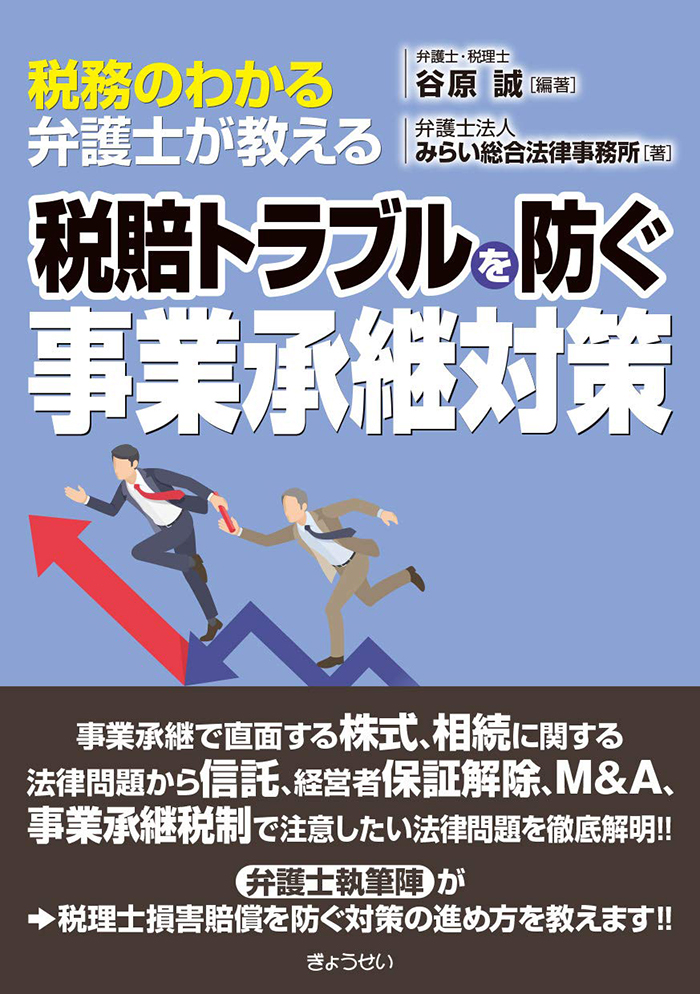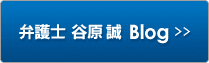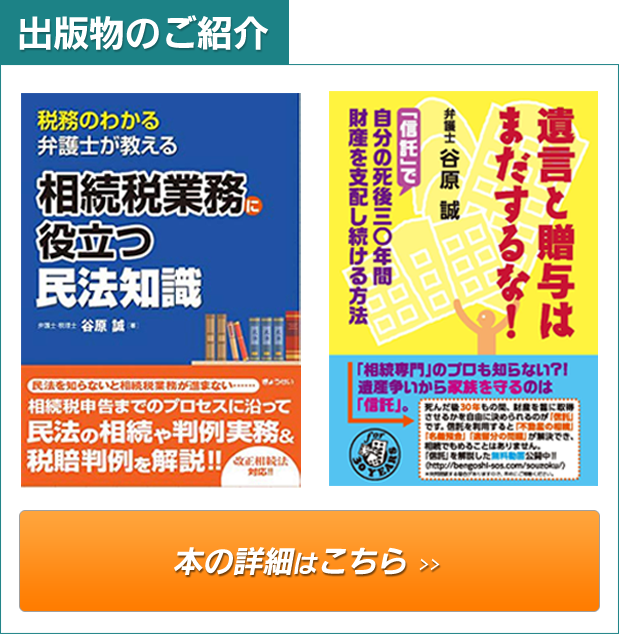相続手続きで連絡の取れない相続人がいた場合の注意点と対処法
相続手続きを進めるためには、相続人全員と連絡を取り、遺産分割の場合には、遺産分割協議や合意が必要です。
しかし、連絡がつかない相続人がいるケースもあるでしょう。
この場合、手続きが思うように進められず、遺産分割が成立しないまま長期化するリスクがあります。
適切に対処しなければ、相続全体の遅延やトラブルに発展する可能性があるため、早めの対応が重要です。
ここでは、連絡の取れない相続人がいる場合の注意点や具体的な対処法を解説します。
目次
相続手続きは相続人全員に
連絡が必要?
相続手続きは、亡くなった方の財産を正しく分配するため行われる手続きなので、相続人全員に連絡を取ることが原則です。
しかし、相続人の中には、疎遠になっているケースや所在が不明なケースもあるでしょう。
まずは、相続人全員に連絡を取ることは必須なのかどうかという点について解説します。
相続人全員に連絡することは
必須
相続手続きを進めるには、相続人全員の関与が必要です。
とくに遺産分割協議を行う場合、全ての法定相続人に連絡を取り、協議に参加してもらわなければなりません。
連絡を取りたくない相手であっても、個人的な感情を優先して手続きを進めてしまうと、後から大きな問題に発展するリスクがあります。
「連絡先が分からない」「住居が分からないので連絡の取りようがない」などの理由がある場合も同様です。
また、相続人の人数が多くなる場合は、誰が法定相続人に該当するかの確認する作業も重要になります。
戸籍を辿ると思わぬ人物が相続人として判明することもあるため、早い段階での調査と対応が求められます。
相続手続きを勝手に進めれば
無効になる
一人でも相続人の同意を得ていないまま、個人の判断で相続手続きを進めてしまうことは危険です。
例えば、不動産の名義変更や銀行口座の解約・引き出しなどを、他の相続人の了承なく行った場合、手続きは無効となり、私文書偽造罪などの犯罪として刑事処罰を受ける可能性もあります。
また、勝手に財産を処分した行為が「遺産の使い込み」と見なされれば、民事上の損害賠償請求を受けることも考えられます。
こうしたリスクを回避するためにも、相続手続きは相続人全員の同意のもとで進めることが必須といえます。
万が一、一部の相続人と連絡がつかない場合でも、勝手に省いて手続きを進めるのではなく、「相続手続きで連絡の取れない相続人がいる場合の対処法」で紹介する対処法を試してください。
連絡の取れない
相続人がいるからと
相続手続きを放置するリスク
相続手続きを進めるためには相続人全員と連絡を取る必要がありますが、連絡が取れないからと手続き自体を放置しようと考える人もいるかもしれません。
しかし、相続手続きを放置すれば、以下のようなリスクを負うことになります。
相続税の申告遅れによる
ペナルティが発生する
相続税の申告期限は、原則として「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。
そして、相続税の申告には、各相続人の財産取得状況を基に課税額を計算する必要があるため、相続人全員と連絡を取って遺産分割の状況を正確に把握しなければなりません。
しかし、連絡の取れない相続人がいれば遺産分割協議が進まないため、相続税の申告が期限に間に合わなくなるリスクがあります。
期限後の申告になれば、「延滞税」や「無申告加算税」が課されます。
そうすれば、本来払う必要のなかった税金を負担することになります。
相続税の申告期限までに遺産分割できなかった場合は、「未分割」のまま申告を先にして、遺産分割協議を続けることになります。
相続登記の義務化により
放置すると罰則がある
2024年4月から相続登記が義務化されました。
これにより、相続人は、不動産の所有権を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行うことが法律で義務付けられました。
万が一、正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
連絡が取れない相続人がいて遺産分割協議が進まなければ、不動産の名義変更ができないまま3年を過ぎてしまうことがあるかもしれません。
連絡が取れない人がいる場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てるなど、早めの対応が必要です。
資産の凍結状態が続く
相続手続きが完了するまで、被相続人名義の銀行口座や不動産、株式などは基本的に自由に処分・使用することができません。
連絡の取れない相続人が1人でもいると、遺産分割協議が成立せず、これらの資産が凍結状態になってしまいます。
例えば、葬儀費用を故人の口座から捻出しようとしても引き出せず、喪主が立て替えることになったり、事業用不動産が相続できずに運営に支障が出たりするケースもあります。
また、空き家になった不動産の管理ができず、近隣からの苦情や固定資産税の滞納が発生することもあるでしょう。
相続人の連絡が取れないまま放置することは、資産に関するトラブルを引き起こす可能性があるため注意が必要です。
他の相続人との関係悪化・
トラブルの原因になる
連絡の取れない相続人がいる状態を放置していると、残りの相続人同士で不満や不信感が積み重なり、親族関係の悪化につながることがあります。
「なぜ連絡を取らないのか」「なぜ相続手続きが進めないのか」といった疑念から、感情的な対立に発展することもあるでしょう。
さらに、相続手続きが進まないことに対して不満を持つ相続人が、家庭裁判所に調停を申し立てたり、訴訟に発展したりすることも考えられます。
トラブルが複雑化すれば相続そのものが長期化し、精神的・金銭的な負担が大きくなります。
相続手続きで連絡の取れない
相続人がいる場合の対処法
相続人の中で連絡が取れない人がいると、遺産分割協議が成立せず、全体の手続きが滞ってしまいます。
こうした場合は放置するのではなく、段階を踏んで適切に対応することが大事です。
連絡の取れない相続人がいる場合は、以下の流れで対処することが一般的です。
戸籍や住民票で所在を確認する
連絡の取れない相続人がいる場合にまず行うことは、連絡がつかない相続人の所在や生存の確認です。
被相続人の戸籍をたどって相続人を確定させた後に、対象者の最新の住民票や戸籍の附票を取得することで、現在の住所や転居履歴を確認できます。
この確認を行えば、住所変更で連絡が届いていなかっただけなのか、所在が不明なのか、状況を把握できます。
また、高齢の相続人の場合はすでに亡くなっていて、代襲相続人としてその子供が相続人になっているケースもあるでしょう。
住民票等で得られる情報を基に、まずは基本的な接触手段を試みることが一般的です。
手紙や調査会社を使って
接触を試みる
住民票の住所に手紙を送っても返送される場合や、電話が不通で連絡が取れない場合は、内容証明郵便などの公的な通知手段を使って相手に連絡を試みましょう。
相続手続きの必要性や連絡を求めている旨を文書として記録に残すことで、今後の手続きに備えた証拠にもなります。
また、内容証明を送付しても連絡が取れない場合は、調査会社などに依頼して相手の現在の居住地や連絡先を特定してもらうという手段もあります。
不在者財産管理人の
申立てをする
内容証明や調査などをしても連絡が取れない場合や見つからない場合には、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることを検討します。
この申し立ては、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任し、行方不明の相続人に代わってその利益を保護しつつ遺産分割協議に参加するための制度です。
管理人には通常、司法書士や弁護士が務めます。
ただし、選任には申し立ての理由や、これまでの連絡・調査の経緯を示す必要があります。
失踪宣告をする
相続人が長期間行方不明で、調査や不在者財産管理人の選任申立てなどでも解決しない場合、最後の手段として「失踪宣告」を家庭裁判所に申し立てることを検討します。
失踪宣告には2種類あり、通常失踪は7年間行方が分からない場合、特別失踪は災害や事故などの危難に巻き込まれて1年間生死不明である場合に認められます。
失踪宣告がされると、その相続人は法律上死亡したものとみなされるため、相続手続きを進められるようになります。
ただし、失踪宣告は相続人の存在を法律上消す重大な手続きになるため、後で本人が現れた場合には財産の返還義務などが生じる可能性があります。
申立てには慎重さが求められるため、弁護士など専門家に相談しながら進めることが望ましいでしょう。
連絡が取れない相続人が
見つかった場合の対応方法
所在不明だった相続人が見つかっても、すぐに手続きが進むとは限りません。
相手が協議に応じてくれるかどうかは別問題であり、慎重な対応が求められます。
連絡がついた相続人に対し、どのように協議へ応じてもらえるように進めるべきか解説します。
相続の状況を伝える
連絡がついた相続人に対し、いきなり遺産分割協議を求めるのではなく、まずは相続発生の経緯や現在の状況を丁寧に説明しましょう。
長年音信不通だった相手に突然法律的な話をしても、警戒心や不信感を持たれてしまう可能性があります。
書面や電話、必要に応じて訪問するなど、相手が安心できるよう誠実な姿勢で連絡することが大切です。
相手が現状を理解し、前向きに話し合いに参加する意欲を持つことができれば、協議をスムーズに進められるようになります。
内容証明郵便で
協議の出席を求める
丁寧な連絡をしても反応がない場合や、協議への参加意思が曖昧な場合には、内容証明郵便で協議への出席を求める通知を送ることが有効です。
内容証明で送付することで、「相続手続きを進める意思があること」「協議に参加してもらいたいこと」を証拠として残せます。
内容証明に法的拘束力はありませんが、相手に対して手続きの重要性を伝える強い意思表示になります。
また、後で調停や裁判に発展した場合でも、話し合いを尽くしたことの証明として利用できます。
連絡は取れたものの
相続人が非協力的な場合の対処法
相続人全員と連絡が取れたにものの、特定の相続人が協議に応じない場合や、感情的な対立によって非協力的な態度をとる場合もあるでしょう。
こうしたケースでは、相続手続きが長引いてしまいます。
非協力的な相続人がいる場合の対処方法には、以下のような方法が有効です。
証拠を残すようにする
連絡が取れているにも関わらず、「協議の場に出てこない」「返事をしない」「書類に署名しない」といったケースは珍しくありません。
電話や口頭で催促しても応じてもらえない場合は、書面で協議への参加を求める通知を送ることが有効です。
「〇月〇日までにご返答ください」という期限を設けることで、対応を引き延ばされることが防げるでしょう。
こうした対応にも非協力的な場合は、家庭裁判所への申し立てを検討することになります。
勝手に財産を処分された場合は早急に法的措置を取る
遺産分割協議が終わっていないにも関わらず、不動産を貸し出したり、預貯金を引き出したりなど、勝手な行動をとる相続人もいるでしょう。
こうした行為は、「相続財産の持ち出し」に該当し、法的に問題のある行為です。
勝手に財産を処分されるなどの行為があった場合は、証拠となる記録を収集し、家庭裁判所に「財産の保全」を申し立てることができます。
また、金銭的損害が出ている場合は、損害賠償請求をすることも可能です。
他の相続人の不利益を防ぐためにも、こうしたトラブルが起こった際には早期に専門家へ相談しましょう。
調停・審判で法的に手続きを
前に進める
協議が成立しない、もしくは協議そのものができない状態が続く場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることを検討しましょう。
調停では、裁判所の調停委員が介入し、相続人同士の合意を目指します。
調停でも合意に至らなければ、遺産分割審判に移行し、裁判所が法的に分割方法を決定します。
審判の結果は、当事者の意思に関係なく法的な決定力を持つため、非協力的な相続人がいても手続きを前に進めることが可能です。
調停や審判にはある程度の時間と費用がかかりますが、放置によるリスクを回避できる手段といえます。
まとめ
相続手続きは、相続人全員の協力があってこそ円滑に進められるものです。
しかし、実際には「連絡がつかない」「見つかったけれど協力してくれない」「勝手な行動を取る」といったケースも少なくありません。
こうした問題を放置すれば、相続登記や相続税の申告が遅れ、過料や延滞税の発生などのリスクがあります。
複雑になった相続問題は一人で抱えるのではなく、相続に強い弁護士へ早めに相談することが解決への近道です。
法的手段を取るべきタイミングや進め方、トラブルを防ぐための工夫など、プロの視点から的確なアドバイスを受けることができます。
遺産分割でお困りの時は一人で悩まず、まずは一度、ご連絡ください。