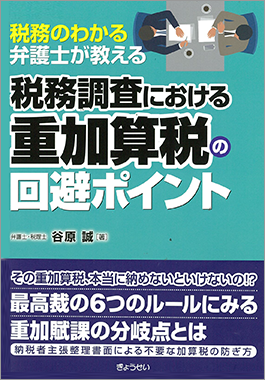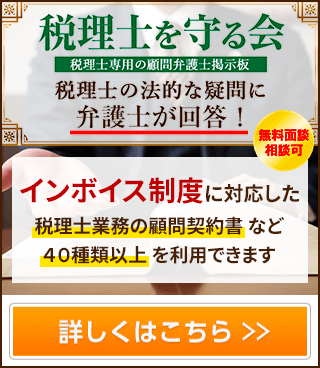重加算税と7年遡及の関係について解説します。
租税債権の徴収権は、原則として、法定納期限から5年です(国税通則法72条1項)。
しかし、「偽りその他不正の行為」により税額を免れた場合は、7年となります(同法70条5項)。
これに対し、重加算税の要件は、「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装」となっています。
制度趣旨が異なることから、文言も異なっていますので、両者は、全くイコールではありません。
しかし、過去の判例上、両者の線引は明確になされていません。
この点、横浜地裁平成16年3月17日判決は、国税通則法第70条5項の趣旨を「納税者が「偽りその他不正の行為」によって税額を免れたときは、同条の前各項が規定する期間より延伸された期間まで、更正、決定等をすることができる旨を規定しているが、これは、納税者が「偽りその他不正の行為」によって税額を免れようとしたときには、課税庁による国税の賦課権の行使が困難となることはいうまでもないところ、このような場合、その者に対する適正な課税の機会を確保し、納税者間の公平を確保する必要があることや、賦課権の行使が困難となる原因を自ら生み出した以上、租税法律関係の早期安定に係るその者の利益を考慮する必要性に乏しいことなどから、通常の場合よりも長期間その国税の賦課を可能として、適正・公平な課税の実現を図ることとしたものということができる。」としています。
その上で、「偽りその他不正の行為」を「このような、通則法70条5項の趣旨からすれば、同項が規定する「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作を行うことをいうものと解するのが相当である(福岡高等裁判所昭和51年6月30日判決・税務訴訟資料89号123頁、最高裁判所昭和52年1月25日第三小法廷判決・訟務月報23巻3号563頁参照)。」としました。
これに対し、最高裁平成7年4月28日判決(民集49巻4号1193頁、TAINS Z209-7518)は、「重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて隠ぺい、仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を科することによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もつて申告納税制度による適正な徴税の実現を確保しようとするものである。」としています。
そして、国税庁は、「課税処分に当たっての留意点」(平成25年4月 大阪国税局 法人課税課、TAINS H250400課税処分留意点178頁)において、「『隠蔽』とは、課税標準等又は税額の計算の基礎となる事実について、これを隠蔽し、あるいは故意に脱漏することをいい、また『仮装』とは、財産あるいは取引上の名義等に関し、あたかも、それが真実であるかのように装う等、故意に事実を歪曲することをいう(名古屋地裁昭和55年10月13日判決)」としています。
以上より、「偽りその他不正行為」と「隠蔽し、又は仮装」は、大まかには、ほぼ重なると理解しておいて良いと思いますが、「偽りその他不正の行為」を認定して7年遡及を認めつつ、重加算税の他の要件「納税者が」を満たさず(第三者の行為が納税者の行為と同視できない)、重加算税を否定した裁決例もあります(平成23年7月6日裁決)。
したがって、個別事案毎に、それぞれの要件に当てはめて確認していく必要があります。