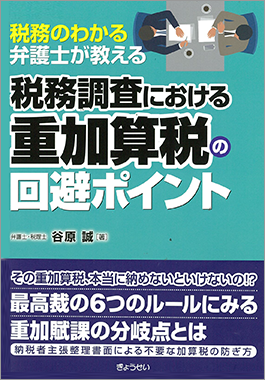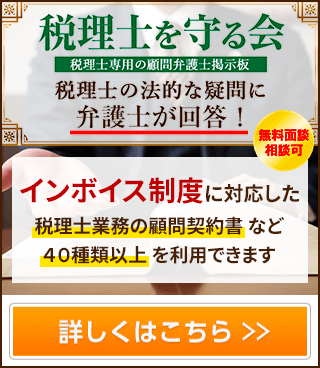今回は、飲食交際費該当性に関する裁判例のご紹介です。
東京地裁令和5年5月12日判決です。
(事案)
原告は2社あり、代表者は同一です。
原告Aは、宣伝、広告の企画、制作等の業務を行うとともに、かっぽう料理店を経営していた。
原告Bは、グラフィック媒体における広告等の企画及び制作等の業務を行うとともに、日本酒バルを経営していた。
原告らの顧客や取引先はおおむね重複しており、例えば、C社の広告業務も、共に同じ広告代理店を通じて原告らが受注していた。
原告らは、課税庁より税務調査を受け、交際費及びその他の費用として計上した飲食等の代金の一部は、交際費等に当たらないと指摘されたため、修正申告をしたが、その後更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けたため、出訴した。
(注意点)
本件では、修正申告に応じた上で更正の請求をし、更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けたため、出訴した、というものであり、立証責任が納税者側にある事案ですので、更正処分を争う場合より納税者側の立証の負担が重い点に注意が必要です。
(判決)
中小法人の50%損金算入の対象となる「接待飲食費」の帳簿記載要件を満たしていないことから、特例の適用はない旨の認定をしています。
その上で、交際費等の損金該当性については、以下のような基準を立てています。(三要件説)
法人が支出した飲食等の代金が交際費等に該当するといえるためには、当該支出に係る飲食等の日時が特定されていることを前提に、
(1)当該支出の相手方が事業に関係のある者等であること、
(2)当該支出の目的が相手方との親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図ることにあること、
(3)当該支出の態様が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること
を要するというべきである。
その上で、
・法人の支出した飲食等の代金が交際費等に該当するためには、その支出の目的が一般的・抽象的なものでは足りず、具体的に当該法人の業務と関連性があるものであることを要するというべきである。
・単に人脈を広げるという抽象的な必要性があるというだけでは、具体的に原告らの業務と関連性があるということはできない。
と判示しています。
この判決の立場からは、人脈を広げる必要性も抽象的なものでは足りず、具体的に受注先となりうる人脈など業務との具体的関連性が必要になる、ということになります。