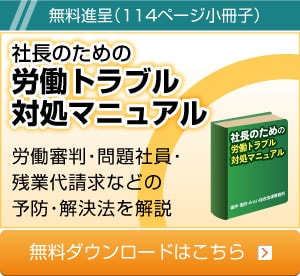会社役員の会社に対する責任原因
会社法は、会社の役員が、会社に対して損害賠償責任を負う場合と、会社以外の第三者に対して損害賠償責任を負う場合を定めています。
会社役員の会社に対する責任原因としては、1. 任務懈怠、2. 利益相反取引、3. 利益供与、4. 違法な剰余金配当が挙げられます。
- 取締役は、会社に対し、その任務を怠ったことにより生じた損害を賠償する責任を負います。
具体的な法令違反はもちろん、業務執行に関する注意義務違反、他の取締役に対する監視・監督義務違反等が任務懈怠の内容になります。
業務執行に関する注意義務違反として問題になるのが、経営判断の原則です。
会社経営においては、流動的な状況のもとで、冒険的な判断が経営者に対し要求されるものであって、結果として会社に損失を与えたとしても、それを全て損害賠償責任の対象とすることは、会社経営を不当に萎縮させるおそれがあります。
そのため、当該状況下で、事実認識・意思決定過程に不注意がなければ、取締役には広い裁量の幅が認められることを判示する裁判例は多いところです。
- 利益相反取引によって会社に損害が生じたときは、
1.直接取引の相手方である取締役または第三者のため会社と取引をした取締役、2.会社を代表し当該取引をすることを決定した取締役、3.当該取引に関する取締役会の承認決議に賛成した取締役は、その任務を怠ったものと推定されます。2、3の取締役および1の取締役のうち直接取引の相手方である者以外のものは、会社の損害発生に関し過失がないことを証明して責任を免れることができるが、1の取締役のうち直接取引の相手方である者の責任は、無過失責任にとされ、また、責任の一部免除も認められません。
- 株主の権利行使に関し会社・子会社の計算において財産上の利益を供与することに関与した取締役は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、供与した利益の価額に相当する額を会社に対し支払う義務を負います。
利益供与をした取締役には無過失責任が課されています。
- 違法な剰余金分配に関与した取締役は、分配された額を会社に支払う義務を負いますが、無過失を証明したときはその義務を免れます。
任務懈怠行為
ある取締役の任務懈怠行為が取締役会等の決議に基づいてなされた場合、その決議に賛成した取締役は、旧商法では、行為をした取締役とみなされていたが、会社法ではそのような規定を置かず、賛成票を投じた行為自体に任務懈怠があったかどうかで責任の有無が判断されます。
ただし、利益相反行為を承認した取締役会決議に賛成した取締役は任務懈怠を推定されます。
また、決議に参加した取締役は議事録に異議をとどめない場合には決議に賛成したものと推定されます。
責任の認められる取締役らは連帯して責任を負います。
取締役の責任をすべて免除するためには、総株主の同意が必要です。
一部免除の方法としては、株主総会決議によるもの、定款の定めに基づく取締役・取締役会の決定によるもの、社外取締役との間に締結された責任限定契約によるものがあります。
悪意・重過失
取締役がその職務を行うについて悪意・重過失があったときは、当該取締役は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います。
この責任の性質について、判例は、会社の経済社会に占める地位および取締役の職務の重要性を考慮し、第三者保護の立場から、取締役が悪意・重過失により会社に対する任務を懈怠し第三者に損害を被らせたときは、当該任務懈怠行為と第三者との間に因果関係がある限り、直接損害・間接損害を問わず、取締役に損害賠償の責任を負わせたものと解しています。
直接損害の典型例は、会社の資金繰りが悪化していたにもかかわらず、返済見込みのない借入をしたり、代金支払見込みのない商品購入等をしたりして、契約相手方である第三者が損害を被る場合です。
間接損害の典型例は、取締役の放漫経営により会社が倒産した場合に会社債権者が被る損害です。
取締役会設置会社の取締役
取締役会設置会社の取締役は、取締役会の招集権限や代表取締役の選定及び解職の権限を有していることにかんがみて、取締役会の審議ないし決議を通じて代表取締役らの業務の執行を監視すべき権利義務を有するとされ、その監視義務は、取締役会に上程された事項に限られず、これを怠ることは任務懈怠にあたると考えられています。
責任を負う取締役の範囲については、名目的取締役(後述)、登記簿上の取締役、事実上の取締役等の問題があります。
登記簿上の取締役
登記簿上の取締役については、株主総会の選任決議がないが、取締役として登記されることを承諾し不実の登記の出現に加功した者は、取締役でないことを善意の第三者に対抗することができず、したがって第三者に対する責任を免れないとした判例があります。
その後の判例は、辞任登記未了の元取締役について、1、辞任後もなお積極的に取締役として対外的・内部的に行為をあえてしたか、または、2、不実の登記を残存させることにつき登記申請者に明示的な承諾を与えていたと等の場合にのみ責任が認められると判断しました。
正式に取締役に選任されていないにもかかわらず、事実上会社業務を執行している者(事実上の取締役)については、第三者に対する責任を認める裁判例も否定する裁判例もあります。
名目的取締役
名目的取締役とは、当該取締役と会社との間において、取締役としての職務を果たさなくてもよいという旨の合意のもとで、有効に取締役に選任されている者をいいます。
旧商法下においては、会社の規模を問わず3人の取締役の選任を要求していたことから、このような名目的取締役を生んでいたとも考えられます。
名目的取締役であっても、取締役の義務である代表取締役の業務執行に対する監視・監督義務を負うとされています。
そのため、名目的取締役に対する監視義務違反は、中小企業において追求される例が多く見られます。
旧商法下の裁判例においては、監視義務を尽くしても侵害行為について知り得なかったとするもの、監視義務を尽くしても侵害行為を阻止し得なかったとするもの、重過失がないとするものなど、名目的取締役の責任を否定する裁判例も少なくありませんでした。
しかし、これら裁判例の背景には、旧商法が会社の規模を問わずに3人の取締役の選任を要求したことで名目的取締役を生み、会社の規模を問わず取締役に就任した者に、常に一律に責任を負わせることは酷であるとの考えがあったものと思われます。
取締役は1人でもよく、柔軟な機関設計が可能になった会社法の下では、従前の議論が妥当せず、名目的取締役に対して厳しい判断が下される可能性も否定できません。
友人の会社のため、あるいは取引先に頼まれて、安易な気持ちで取締役になることは、今後は一層、注意しなければならないでしょう。