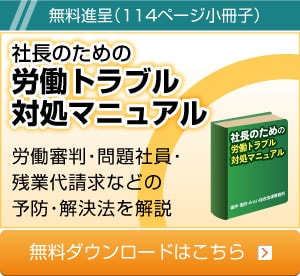話合い
貸主からの賃料増額請求、借主からの賃料減額請求どちらの場合も、まずは話合いによることとなります。
話合いにより合意に至れば、その額が新しい賃料となります。
なお、たとえ合意に至ったとしても、後で反故にされる可能性があるので、「言った」「言わない」の問題にならないよう、日付や署名・押印の入った合意書を残しておくべきです。
調停
合意に至らなかった場合は、調停という手続きを行います。
調停とは、間に裁判所に入ってもらい、当事者同士が話し合い、合意に達した場合に「調停調書」という公的な和解書類を作成する手続です。
調停では、裁判官と調停委員を交えながら、当事者同士で話し合うことになります。
経験豊富な調停委員が第三者としてアドバイスすることで、当事者のみでは合意に至らなかった協議がまとまることが期待されているのです。
もっとも、調停はあくまで話合いでの解決なので、当事者同士がお互いに譲り合うことが必要で、貸主・借主ともに全く譲歩しない場合には、調停で解決することは難しくなるでしょう。
裁判
調停においても合意に至らなかった場合は、訴訟を起こすことになります。
訴訟とは裁判所に対し、判決を求めて訴えを起こすことです。
訴訟では、不動産鑑定士の鑑定などをもとに、最終的に裁判所が適切な賃料を定めることになります。
ただ、訴訟を起こす場合、事前によく考えておきたいことがあります。
それは裁判をして採算がとれるのか、ということです。
訴訟にはそれなりの時間と費用がかかります。
弁護士を使うなら弁護士費用が必要ですし、これに加えて不動産鑑定士に支払う費用も、十数万円から、場合によっては数十万円にのぼります。
このように多額の費用がかかることから、裁判を起こしても採算がとれないという場合が多いのです。
なお、賃料の増減を請求する場合は、まずは話合いをすることが望ましいという考え方から、訴訟を起こす前に、調停を起こさなければならないと、法律によって決められています。
これを、調停前置主義といいます。
貸主側の対策
貸主にとって、賃料増額訴訟が採算の合わないものになるなら、貸主は賃料を増額させる別の方法を検討しなければなりません。
たとえば、一定期間ごとに一定の率で賃料が増額する旨の特約(自動増額条項)を契約書に盛り込んでおくことが考えられます。
借地借家法では、借主に不利な条項は無効とされていますが、増額率が固定資産税の上昇率によって決められるような合理的な内容である限り、有効とみなされる場合が多いでしょう。
もっとも、借主が、そもそも自動増額条項自体の有効性を争い、増額を拒否してきた場合は、貸主としては結局訴訟を提起するほかありません。
そう考えれば、この方法も万全ではないといえます。
とはいっても、このような条項があることから、貸主が賃料増額を拒否することは減少すると思われますので、意味がないわけではありません。
新賃料が確定するまで
話合い、調停、訴訟と経ている間、値上げ要求から新賃料が確定するまでには長い時間がかかります。
この間、借主側としてはいくら賃料を支払えばいいのか迷うかもしれません。
この点について、法律では「裁判で新賃料が確定するまでは、借主は相当と思われる額を賃料として支払えば足りる」としています(借地借家法32条2項)。
「相当と思われる額」とは、それまでの賃料額と理解すればいいでしょう。
その後、裁判で新しい賃料が確定し、貸主が支払っていた額がその額に満たなかった場合は、不足分に年1割の利息を加えた金額を支払ってもらうことになります。
もっとも、このような手順で借主が賃料を支払おうとしても、貸主としては値上げした賃料額でなければ受け取りたくないと考えるかもしれません。
賃料の受け取りを拒否した結果、借主がそのまま賃料を支払わなければ、賃料の不払いを理由に賃貸借契約を解除することが可能となります。
ただし、借主が「供託」という手続きを取った場合、契約を解除することはできません。
供託とは、簡単にいうと、賃料を第三者(国)に預けておく手続きのことです。
借主がこの「供託」という法律的な手続きにのっとって支払いを行っている限りは、貸主側がいくら納得できなくても、一方的に契約を解除することはできないのです。